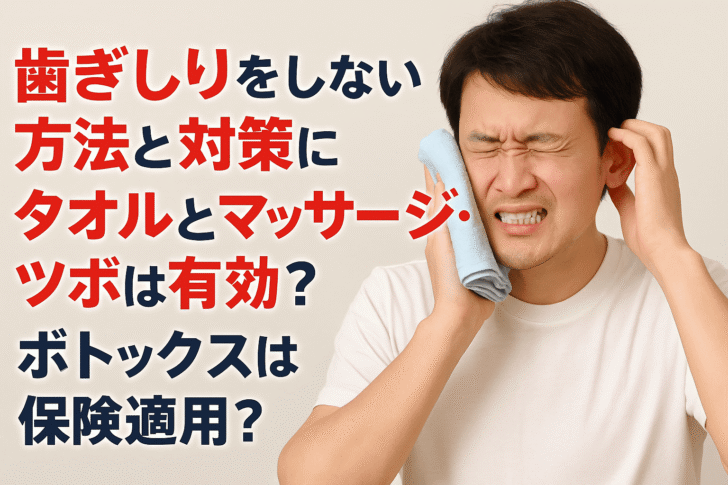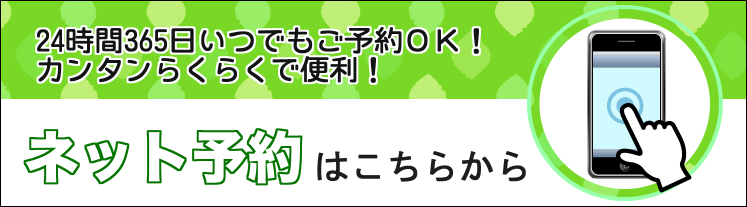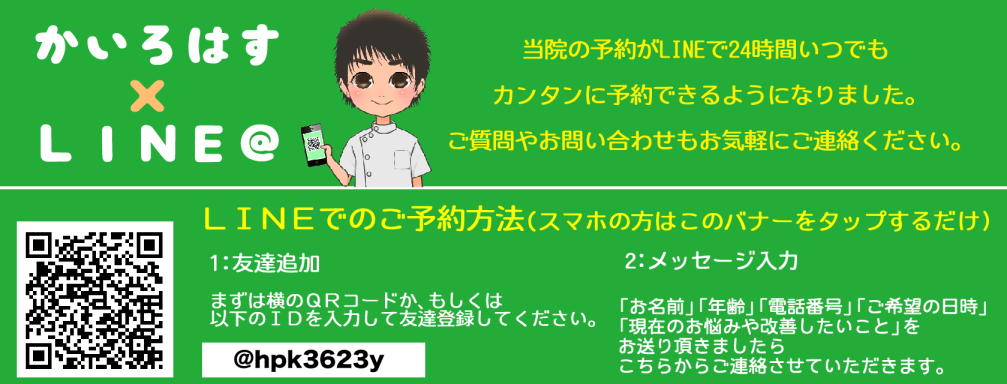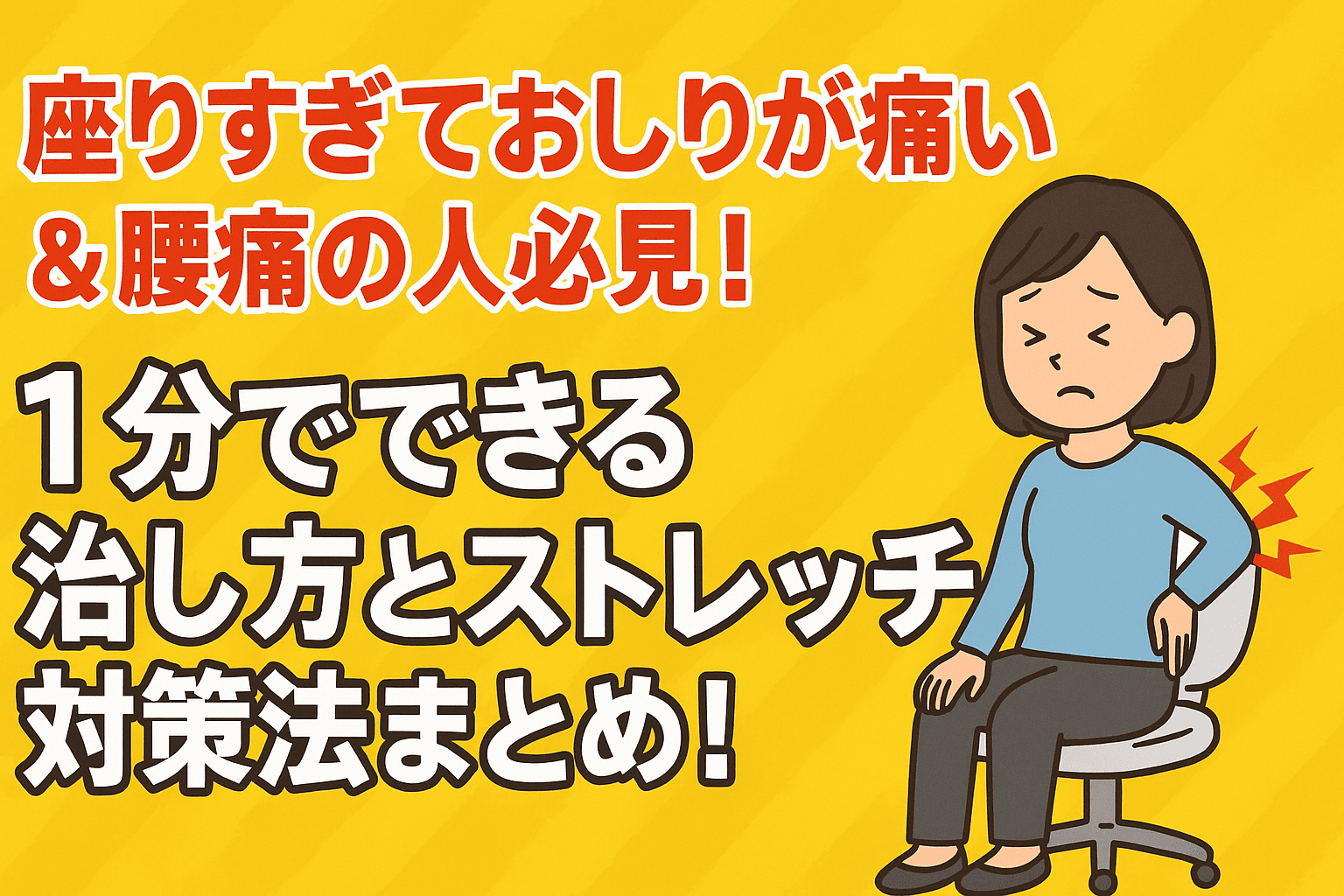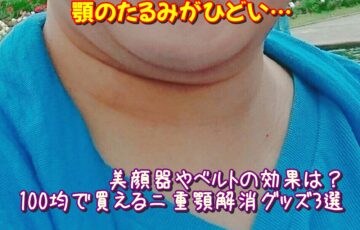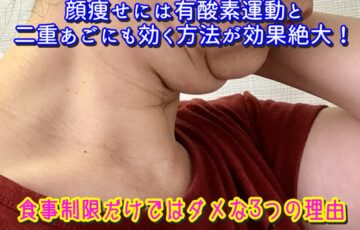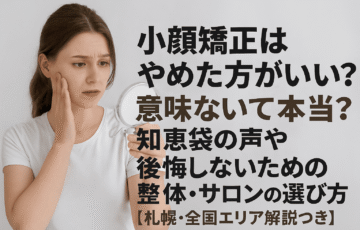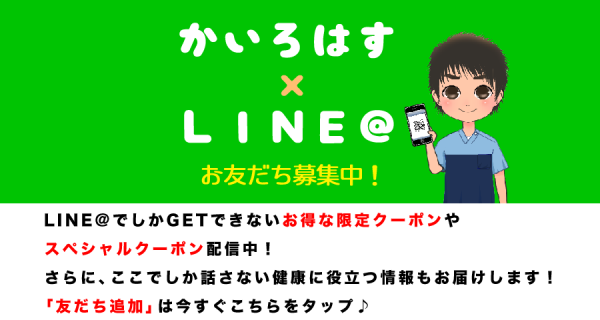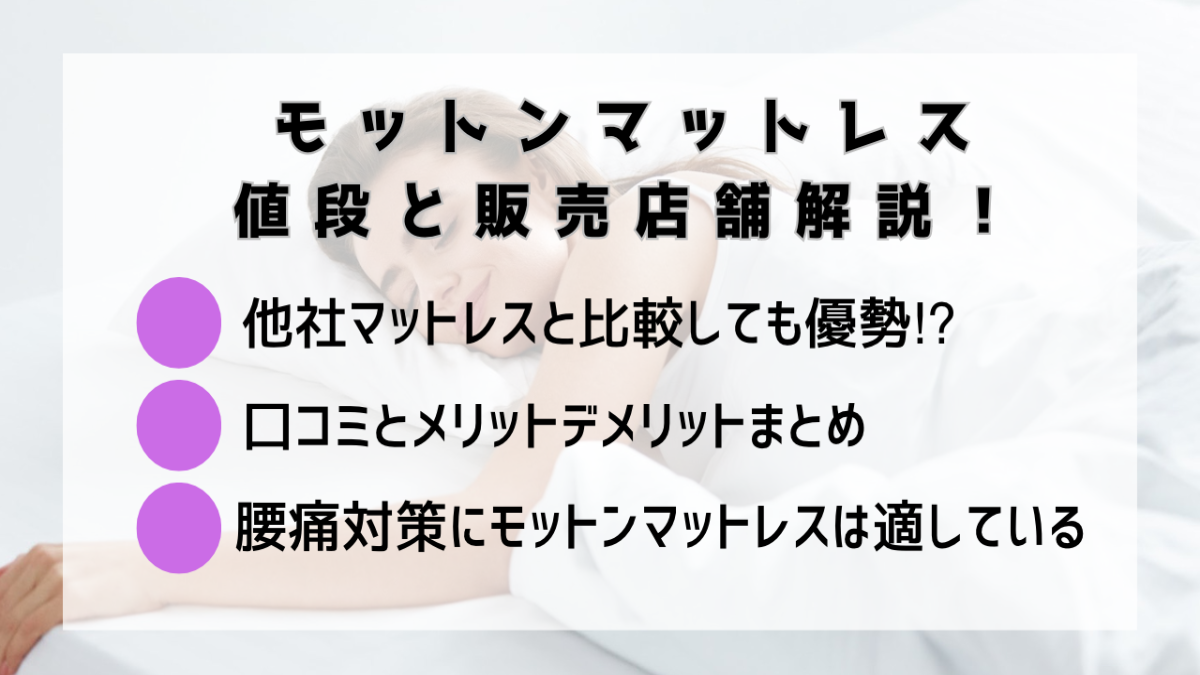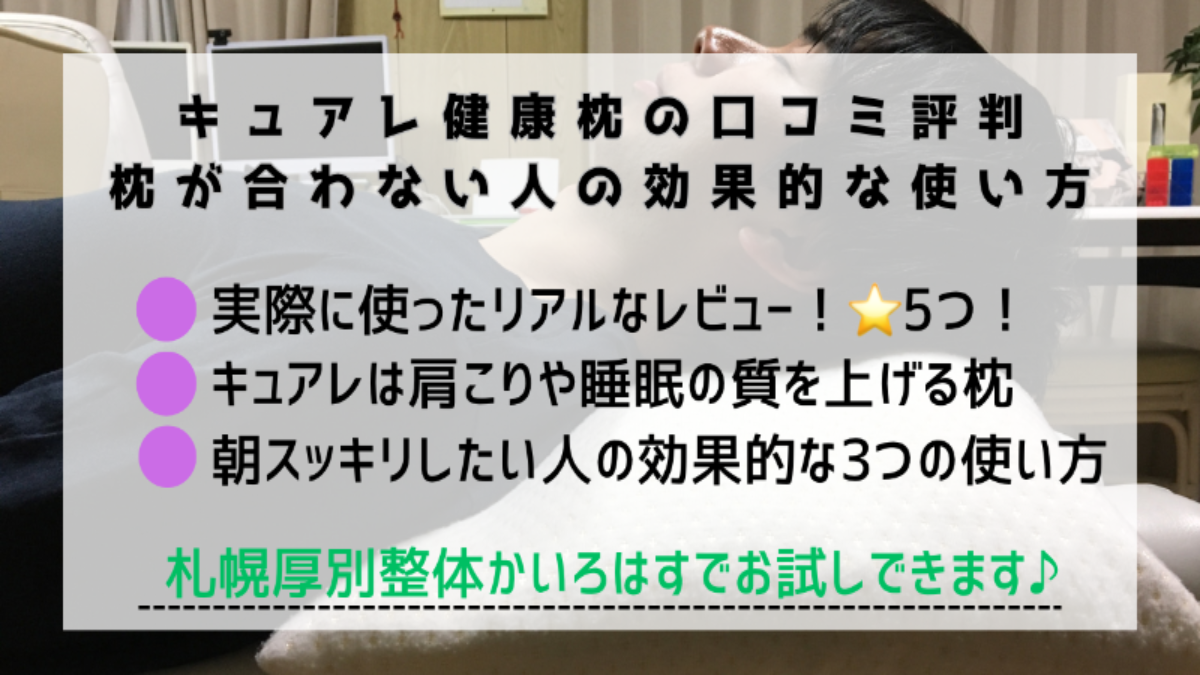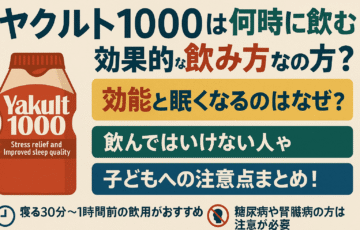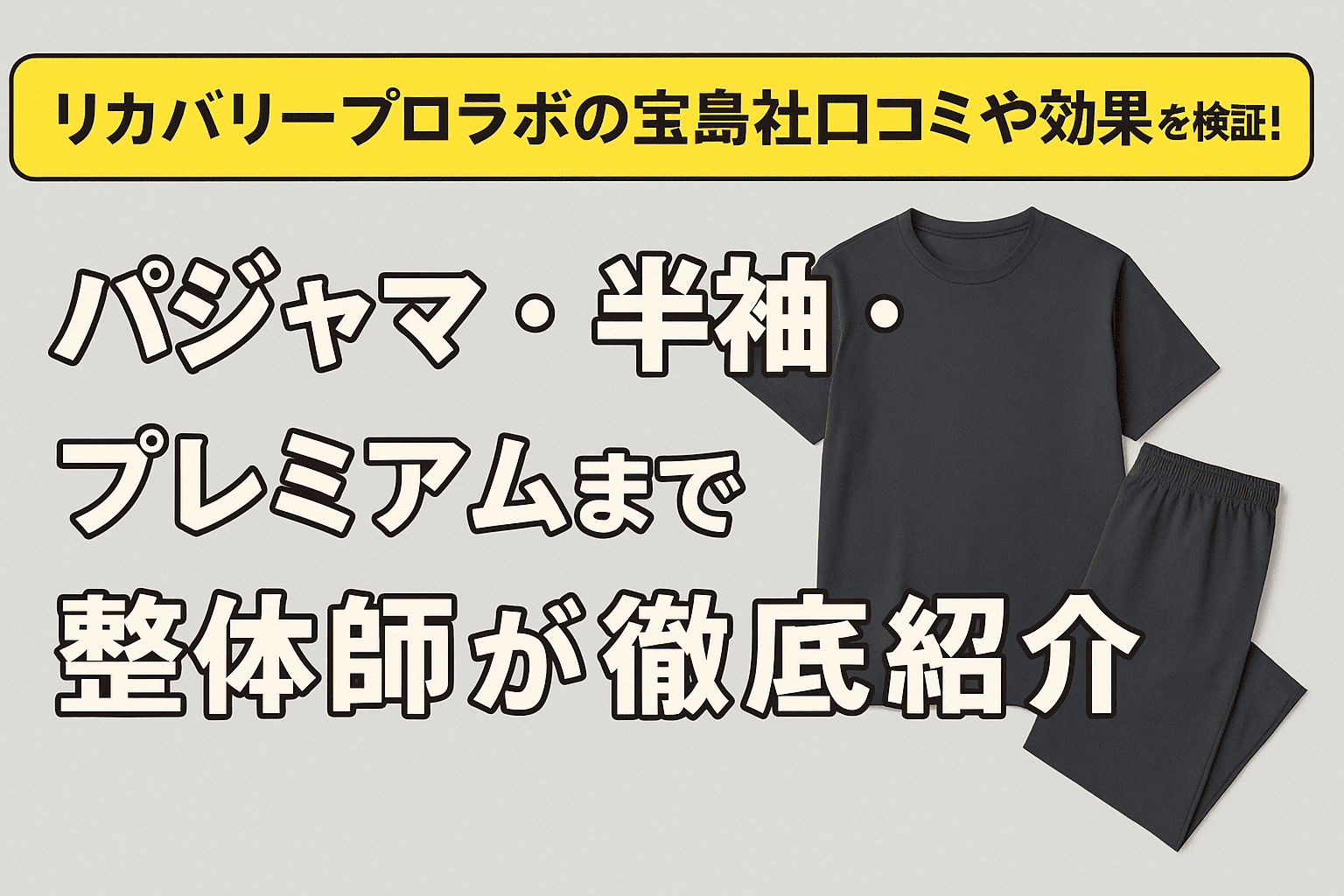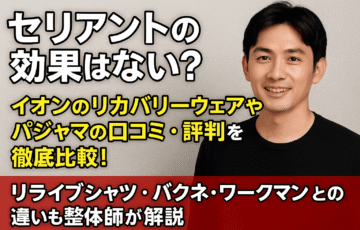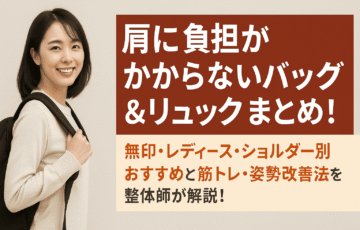- 寝ているときに歯ぎしりをしてしまう
- 朝起きたときに顎が重だるい
- パートナーから歯ぎしりの音がうるさいと言われて気になる
そんなお悩みを持つ方は少なくありません。
睡眠中に上下の歯を強い力でこすり合わせたり噛みしめたりする行為
無意識に行われるため、自分では気づかず、家族から指摘されて初めて自覚するケースも多いのです。
など、想像以上に体にさまざまな影響を及ぼします。

▶単なる癖と軽視すると・・・
- 歯が割れて治療が必要になった
- 顎が痛くて口が開けにくい
など深刻な状態になる場合もあるのです。
- グラインディング(ギリギリと音を立てるタイプ)
- クレンチング(強く噛みしめるタイプ)
- タッピング(歯をカチカチと鳴らすタイプ) など
▶影響
- 音が大きくパートナーの睡眠を妨げる
- 静かに噛みしめるだけで歯や顎にダメージを与える
どのタイプも長期間続けば歯や体への負担が蓄積していくため、早めの対策が大切です。
では、実際にどのような方法で対策できるのでしょうか。
一般的に知られているのは歯科で作るマウスピースですが、
などの方法も存在します。
また、重度のケースでは「ボトックス注射」によって咬筋を緩める治療が行われる場合もあり、保険適用になるケース・ならないケースがあるため、正しい知識が求められます。
さらに、子どもの歯ぎしり(1歳~5歳)と大人の歯ぎしりでは意味が違うことも押さえておきたいポイントです。
年齢やライフスタイルに合わせたアプローチが必要になります。
また、近年は
- 歯ぎしりをしない方法はあるの?
- 市販グッズやアプリは本当に役立つの?
- 歯ぎしりで削れた歯は治るの?
などといった検索も増えており、正確な情報を求める声が強まっています。

そこでこの記事では、整体師の立場から薬機法に抵触しない形で、歯ぎしりの原因や仕組み、セルフケア方法、歯科での治療、そして整体でできる全身アプローチまでを徹底的に解説していきます。
- 歯ぎしりはなぜ起こるのか?
- 放置するとどうなるのか?
- どのような方法で予防・軽減できるのか?
この記事を読むことで、歯ぎしりに関する疑問がクリアになり、今日から実践できる具体的な対策が見つかるはずです。
整体かいろはすでは、姿勢改善や顎・首・肩まわりの筋肉調整を通して、歯ぎしりに影響する体の緊張をやわらげるお手伝いをしています。
「マウスピースだけでは不安」「整体で体から整えたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
\札幌市厚別区で歯ぎしりや顎の違和感に悩んでいる方へ/
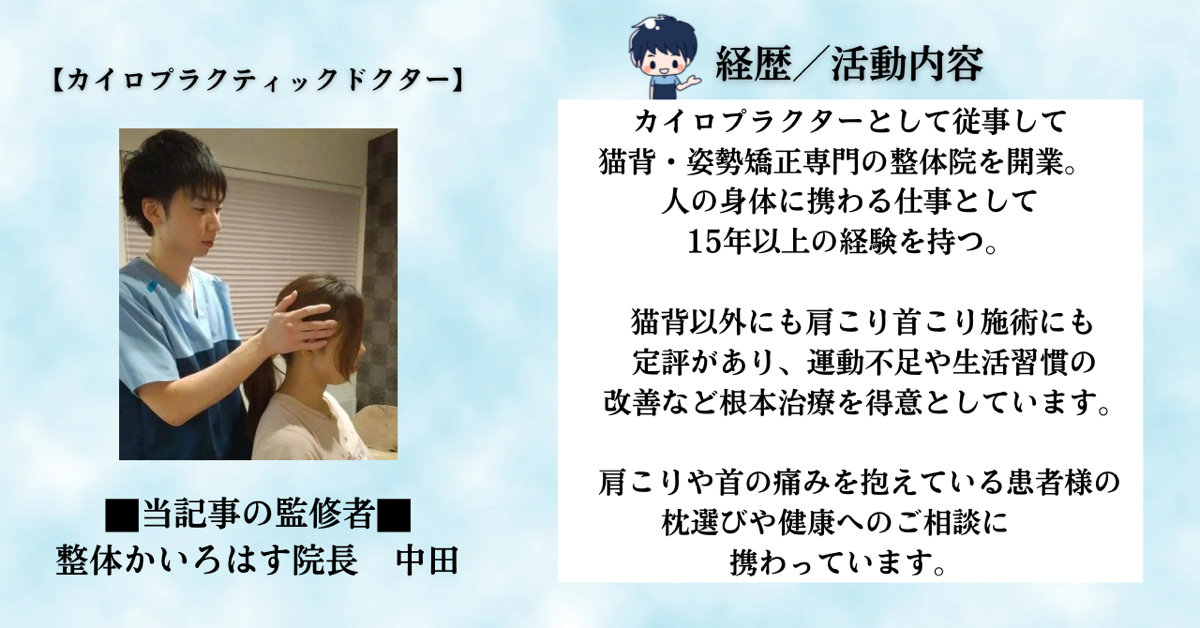
ページコンテンツ
歯ぎしりはなぜ起こる?原因と大人男性に多い理由
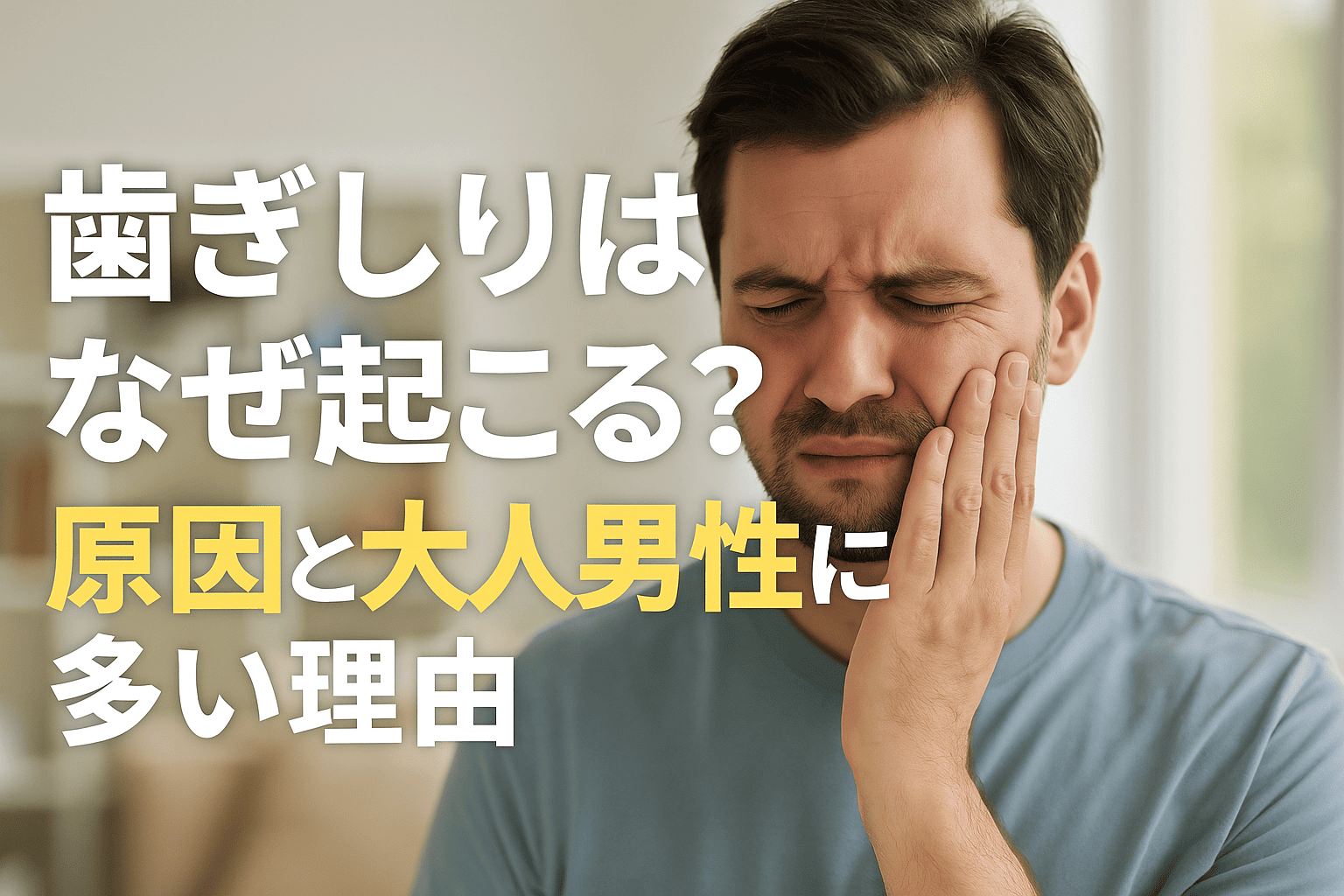
- ストレスによる歯ぎしり
- 噛み合わせ・歯並びの影響
- 生活習慣・体のクセ
- 大人男性に歯ぎしりが多い理由
- 放置するとどうなる?
▶主なポイント
- 歯ぎしりの主な原因は「ストレス」「噛み合わせ」「生活習慣」
- 大人男性に多いのは筋力・仕事ストレス・睡眠環境が関係
- 放置すると歯の削れや顎関節トラブルに直結
ストレスによる歯ぎしり
歯ぎしりの原因で最も多いのがストレスです。
人は緊張や不安を感じると、無意識に体を固めてしまい、その一つの表れが「噛みしめ」や「歯ぎしり」になります。
仕事や家庭でプレッシャーを抱えている方は、寝ている間にストレスを発散するかのように強く歯をこすり合わせることが多い
「夜眠っているはずなのに顎が疲れている」という人は、まさにこのタイプに当てはまります。
噛み合わせ・歯並びの影響
もう一つの大きな要因が噛み合わせの不調和です。
- 歯並びのズレ
- 片側ばかりで噛む習慣
などがあると、無意識に力のバランスを取ろうとして歯ぎしりが起きます。
さらに、長時間のスマホ・デスクワークで首や顎の位置がズレる「スマホ首」や「猫背」も噛み合わせに悪影響を与え、歯ぎしりのリスクを高めます。
生活習慣・体のクセ
生活習慣も無視できません。
- 寝る前のアルコール
- カフェインの摂取
などは、眠りを浅くし歯ぎしりを誘発します。
また、日中に食いしばりのクセがある人は、その延長で夜も歯ぎしりをしやすくなります。
- デスクワーク中に無意識に歯を噛みしめている
- 集中すると眉間にシワが寄る など
大人男性に歯ぎしりが多い理由
「歯ぎしり 原因 大人 男性」と検索されるように、男性は女性よりも歯ぎしりの影響を受けやすい傾向があります。
理由の一つは噛む筋肉(咬筋)の強さです。

さらに、仕事上のストレスや睡眠不足を抱える人が多いことも影響しています。
30代〜50代の働き盛りの男性は、疲労とストレスが重なり、寝ている間に強い歯ぎしりを繰り返すことが少なくない
放置するとどうなる?
- 歯が削れて知覚過敏になる
- 歯が欠ける
- 顎関節症につながる
など、深刻なトラブルに直結します。
特に大人男性の場合、噛む力が強いため進行が早く、「ある日突然歯が割れた」というケースもあります。
また、歯ぎしりは肩こりや頭痛・睡眠の質低下とも関係しており、心身の不調を招くサインでもあるのです。
✅ 整体院からのご提案
整体かいろはすでは、首・肩・顎まわりの筋肉をゆるめ、姿勢の歪みを整えることで、歯ぎしりの負担を軽減するサポートを行っています。
- マウスピースだけでは不安
- 体全体から根本的に整えたい
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
\歯ぎしりや顎の疲れが続いている方へ/
歯ぎしりを放置するとどうなる?歯や体への影響
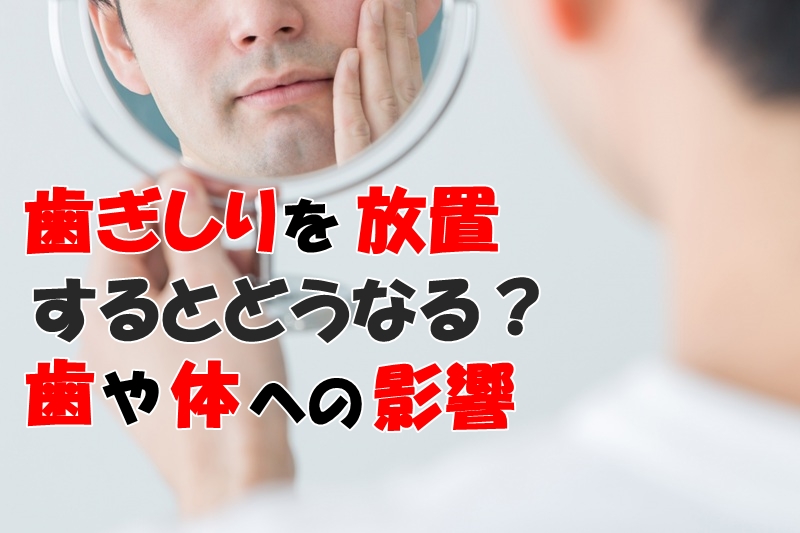
- 歯が削れる・欠けるリスク
- 顎関節や筋肉への負担
- 睡眠の質低下と疲労感
- 見逃しがちな全身への影響
▶主なポイント
- 歯ぎしりを放置すると歯が削れる・欠けるリスクがある
- 顎関節や筋肉に負担がかかり、頭痛・肩こりにもつながる
- 睡眠の質が下がり、全身の疲労感が取れにくくなる
歯が削れる・欠けるリスク
歯ぎしりは、寝ている間に体重の2倍以上もの力が歯にかかるといわれています。
- 歯が削れて平らになる
- 欠ける
- ひびが入る
といったトラブルが出やすくなります。

実際に歯科を受診して初めて「歯ぎしりで歯が削れている」と指摘される方も少なくありません。
顎関節や筋肉への負担
歯ぎしりは歯だけでなく、顎や周囲の筋肉にも大きな負担をかけます。
▶朝起きた時に・・・
- 顎が重だるい
- 口を開けにくい
などと感じるのは、夜間の歯ぎしりが原因かもしれません。
長期間続けば顎関節症を引き起こし、
- 「カクッ」と音が鳴る
- 口が開きにくい
- 顎関節に痛みが走る
などといった症状につながります。

睡眠の質低下と疲労感
歯ぎしりは無意識に筋肉を酷使しているため、睡眠の質を下げる大きな要因です。
- 朝起きても疲れが抜けない
- 日中に眠気が強い
「歯ぎしり 音」がうるさくて家族の眠りを妨げるケースも多く、本人だけでなく周囲にも悪影響を及ぼします。
さらに、眠りが浅くなることでホルモンバランスや自律神経にも負担がかかり、全身の不調が長引くきっかけになりやすいのです。
見逃しがちな全身への影響
歯ぎしりを軽視すると、歯や顎だけでなく、姿勢の悪化・首肩の筋緊張・ストレス増加といった全身のトラブルにつながります。
大人男性は筋力が強いため、歯や顎へのダメージが女性よりも進行しやすい
「ただの癖だから」と放置するのは危険であり、早めの対策が必要です。
✅ 整体院からのご提案
整体かいろはすでは、首・肩・顎まわりの筋肉のバランスを整え、歯ぎしりによる体の負担を軽減するサポートを行っています。
- 歯科でマウスピースを作ったけれど改善しない
- 睡眠の質を上げたい
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
\朝起きても顎や首が疲れている方へ/
歯ぎしりをしない方法まとめ
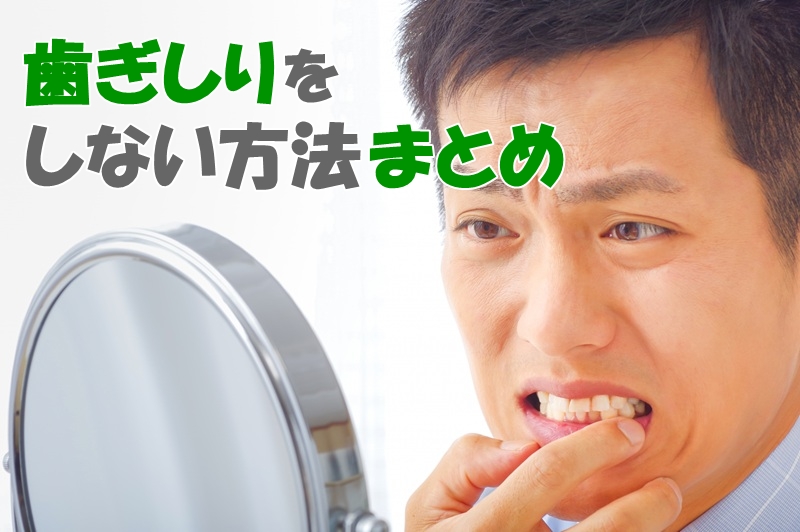
- 日中の食いしばりを減らす意識
- 寝姿勢・枕の工夫で歯ぎしり防止
- リラックス習慣を取り入れる
- 知恵袋でよくある「歯ぎしり治す簡単方法」との違い
▶主なポイント
- 歯ぎしりをしないためには日中の意識改善が大切
- 寝姿勢や枕など環境を整えることで予防が可能
- リラックス習慣を取り入れることが効果的
日中の食いしばりを減らす意識
「歯ぎしり しない 方法」を実現するために、まず見直したいのが日中の食いしばり癖です。
デスクワークやスマホ操作のときに無意識に歯を噛みしめていませんか?
実は、この日中の食いしばりが夜の歯ぎしりにつながるといわれています。
- 「上下の歯は離してリラックスする」ことを意識する
- 集中時に肩や顎が固まっていないか確認する
- 顎を軽くマッサージして筋肉の緊張をほぐす
などといった習慣を取り入れると、夜間の歯ぎしり予防につながります。
「噛みしめない状態を保つこと」が、歯ぎしり解消の第一歩です。
寝姿勢・枕の工夫で歯ぎしり防止
寝ている間の歯ぎしりは、自分の意志で止めるのが難しいため、環境を整えることが重要です。
「高すぎる・低すぎる」と首や顎に負担をかけ、歯ぎしりの原因になりやすい
▶おすすめ
- 首と頭が自然な角度になる高さの枕を選ぶ
- 横向き寝ではなく仰向けを基本にする
- 歯ぎしり対策用の専用枕を試してみる
など睡眠環境を整えることで「歯ぎしり防止」につながります。
リラックス習慣を取り入れる
「歯ぎしり 予防」には、寝る前のリラックスが効果的です。
ストレスが溜まったまま眠ると、無意識に歯ぎしりをしやすくなるからです。
- 就寝前に深呼吸や軽いストレッチをする
- 温かいお風呂に浸かって体をほぐす
- カフェインやアルコールを控える
といった習慣がおすすめです。
リラックスした状態で眠ること=歯ぎしりをしない方法につながるのです。
知恵袋でよくある「歯ぎしり治す簡単方法」との違い
インターネット上には「歯ぎしりを治す簡単な方法」としてさまざまな情報が紹介されていますが、短期間で完全に治すことは難しい場合が多いです。
セルフケア+環境改善+専門的ケアを組み合わせることが、長期的な予防と改善の近道となります。
✅ 整体院からのご提案
整体かいろはすでは、姿勢改善・首肩の緊張緩和・呼吸を整える施術を通して、歯ぎしりをしない環境づくりをサポートしています。
- 日中の食いしばりや寝る姿勢が気になる
- 根本から歯ぎしり対策をしたい
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
\歯ぎしりをやめたいけど「どうすればいいの?」と悩んでいる方へ/
歯ぎしり対策にタオルは有効?使い方と注意点

- タオルを使った歯ぎしり対策とは?
- タオルを使うときの正しい工夫
- タオルだけに頼るのは危険?
- タオルを活用したセルフケア例
▶主なポイント
- タオルを使った歯ぎしり対策は手軽に始められる
- 顎や首まわりの緊張を和らげる効果が期待できる
- 誤った使い方をすると逆効果になることもある
タオルを使った歯ぎしり対策とは?
「歯ぎしり対策タオル」という言葉を耳にしたことはありますか?
寝るときにタオルを顎の下や首の後ろに軽く当て、筋肉の緊張を緩める

また、タオルを丸めて口に軽く挟む方法を紹介しているケースもあります。
これは噛みしめる力を和らげることが目的ですが、誤ったやり方では呼吸を妨げる危険もあるため注意が必要です。
タオルを使うときの正しい工夫
タオルを使う場合は、以下のポイントを守りましょう。
▶ポイント
- 顎や首に負担がかからないよう、柔らかめのタオルを使用する
- 強く噛みしめたり口に詰め込んだりしない
- 清潔なタオルを使い、毎日交換する
特に枕と組み合わせて使うと、首や肩の角度が安定しやすく睡眠姿勢の改善につながるためおすすめです。
タオルだけに頼るのは危険?
「タオルを使えば歯ぎしりが治る」と思ってしまうのは誤解です。
あくまでタオルはサポート的な対策に過ぎません。

- マウスピース
- マッサージ
- ツボ押し
などと組み合わせることで効果を高められます。
タオルを活用したセルフケア例
- 温めたタオルを顎や首まわりに当てて筋肉をリラックスさせる
- 軽くストレッチをしてから眠る
- 枕の高さ調整としてタオルを折りたたんで入れる
睡眠の質を高めるだけでなく、歯ぎしりの防止にもつながるのでおすすめです。
✅ 整体院からのご提案
整体かいろはすでは、顎や首・肩の筋肉の緊張を根本からゆるめ、姿勢改善を行うことで、歯ぎしりの負担を軽減するサポートをしています。
- セルフケアだけでは不安
- 根本的に整えたい
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
\タオルを使っても歯ぎしりが改善しない方へ/
歯ぎしりに効くマッサージ&ツボ押し
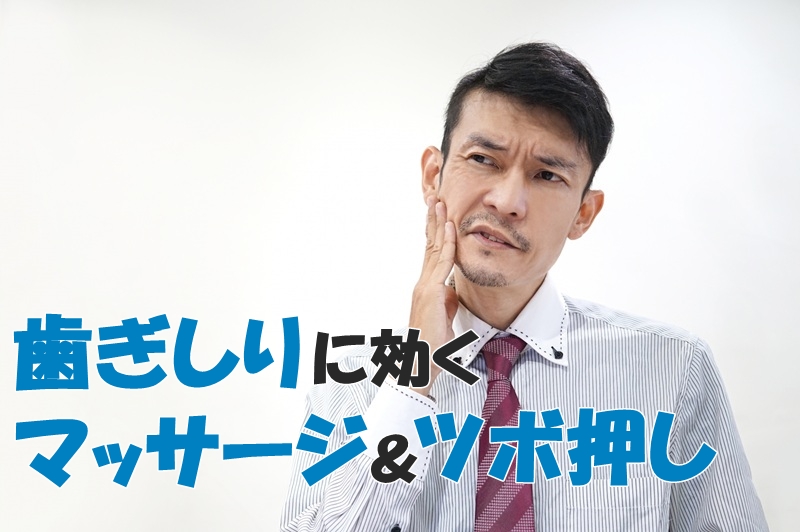
- 顎・こめかみをほぐすマッサージ
- 首・肩まわりのマッサージ
- 歯ぎしりに効くツボ
- マッサージやツボ押しの注意点
▶主なポイント
- マッサージで顎やこめかみの筋肉をゆるめる
- 首・肩をほぐすことで歯ぎしりの緊張を減らす
- ツボ押しは自律神経を整えるサポートになる
顎・こめかみをほぐすマッサージ
歯ぎしりで最も酷使されるのは咬筋(こうきん)と呼ばれる顎の筋肉です。
- 朝起きたときに顎が痛い
- 口を開けにくい
マッサージの方法はとても簡単で、人差し指と中指で頬の外側を円を描くように優しくほぐすだけ。
こめかみの部分(側頭筋)も一緒にマッサージすると、頭の緊張も取れてスッキリします。
首・肩まわりのマッサージ
歯ぎしりは顎だけでなく、首や肩の筋肉がこり固まっている人にも多く見られます。
デスクワークやスマホ操作が多い方は、首の後ろや肩の筋肉が常に緊張しているため、夜間に歯ぎしりが起こりやすい
首の後ろを軽く押したり、肩を回して血流を促すだけでも歯ぎしり対策になります。
歯ぎしりに効くツボ
「歯ぎしり ツボ」でよく紹介されるのが以下のポイントです。
▶ポイント
- 頬車(きょうしゃ):顎のエラ部分にあるツボで、顎まわりの緊張を和らげる
- 太陽(たいよう):こめかみのくぼみにあるツボで、頭痛や目の疲れにも有効
- 風池(ふうち):首の後ろ、後頭部の付け根にあるツボで、自律神経を整えリラックスを促す
これらのツボを息を吐きながら5秒ほどゆっくり押すと、副交感神経が優位になり、心身が落ち着いて歯ぎしりの予防につながります。
マッサージやツボ押しの注意点
- 強く押しすぎないこと
- 痛みがあるときは避けること
- 就寝前に短時間行うこと
といった点を守ることで、安心してセルフケアが続けられます。
✅ 整体院からのご提案
整体かいろはすでは、顎や首肩の筋肉をていねいに調整し、歯ぎしりの原因となる全身の緊張を和らげる施術を行っています。
- セルフケアだけでは不安
- もっと効果的にほぐしたい
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
\歯ぎしりによる顎の疲れや首肩のこりがつらい方へ/
歯ぎしりボトックスは保険適用される?
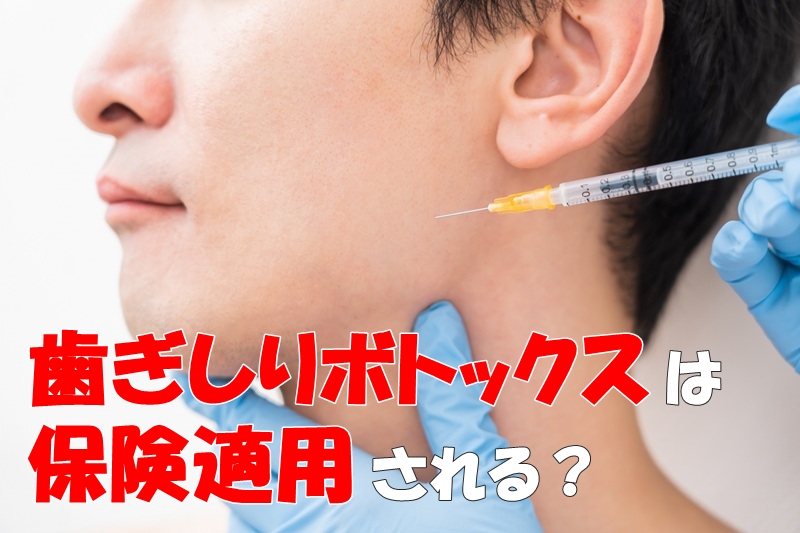
- ボトックス治療の仕組みと効果
- 保険適用の条件とは?
- 東京など都市部での事例
- ボトックスのメリットと注意点
▶主なポイント
- ボトックスは咬筋に作用して歯ぎしりを軽減する
- 保険適用になるケースと自費診療のケースがある
- 治療を受ける前にメリットとリスクを理解することが大切
ボトックス治療の仕組みと効果
噛むときに使う筋肉(咬筋)にボツリヌス毒素製剤を注射して筋肉の働きを弱める治療
筋肉がリラックスすることで噛みしめの力が軽減され、歯ぎしりの頻度や強さを抑える効果が期待できます。
特に、マウスピースを使っても改善しない重度の歯ぎしりや顎関節症の方に選ばれることが多い方法です。
保険適用の条件とは?
「歯ぎしりボトックス保険適用」と検索する方も多いですが、実際には一部のケースでのみ保険適用になるのが現状です。
顎関節症など明らかな疾患として診断された場合は保険が適用される可能性がある
ただし、「美容目的」や「予防目的」では基本的に自費診療となり、1回あたり数万円の費用がかかることが一般的です。
東京など都市部での事例
「歯ぎしりボトックス保険適用東京」といった検索が多いのは、都市部では専門クリニックや美容外科での施術例が多いためです。
東京など大都市では選択肢が豊富で、
- 歯科医院
- 美容外科
- 皮膚科
など複数の診療科でボトックスを取り扱っています。
ただし、費用や回数、効果の持続期間(通常3~6か月程度)は施設によって異なるため、事前に確認することが大切です。
ボトックスのメリットと注意点
▶メリット
- 即効性があり、効果を実感しやすい
- 顎の張りが軽減されフェイスラインがスッキリ見える場合もある
▶注意点
- 効果は一時的で定期的に繰り返す必要がある
- 注射部位の腫れや違和感が出ることがある
- 医師の経験や技術によって仕上がりが変わる
といったリスクがあることも知っておきましょう。
✅ 整体院からのご提案
整体かいろはすでは、ボトックスのような医療処置は行えませんが、顎や首肩の緊張を和らげ、姿勢から歯ぎしりにアプローチする施術を行っています。
- まずは体のバランスを整えたい
- 薬や注射に頼らず自然に改善したい
という方は、ぜひ当院にご相談ください。
\ボトックスを検討しているけれど迷っている方へ/
マウスピースは効果ある?歯ぎしり対策グッズを紹介

- マウスピースの効果と種類
- ドラッグストアで買える対策グッズ
- 枕や寝具を工夫する
- グッズの正しい活用法
▶主なポイント
- マウスピースは歯の摩耗や破損を防ぐ効果がある
- ドラッグストアでも買える市販品がある
- 枕や寝具の工夫も歯ぎしり予防に役立つ
マウスピースの効果と種類
歯ぎしり対策といえば、まず思い浮かぶのがマウスピースです。
「歯ぎしりマウスピース効果」と検索する人も多いように、マウスピースは歯が直接こすれ合うのを防ぎ、摩耗や破損を防止する効果があります。
- 歯科医院で作るオーダーメイド:フィット感が高く、長期的に使用可能
- 市販タイプ:手軽に購入できるが、フィット感や耐久性は劣る
症状の程度や目的に応じて選ぶことができます。

ドラッグストアで買える対策グッズ
「歯ぎしり対策ドラッグストア」で検索すると、さまざまな市販グッズがヒットします。
- 簡易型マウスピース
- 顎を支えるサポーター
- 歯ぎしり音を抑えるアイテム など
手軽に試せる点は魅力ですが、サイズが合わないと逆に顎に負担をかける可能性もあるため注意が必要です。
枕や寝具を工夫する
実は「歯ぎしり枕」も検索される人気ワードです。
枕の高さや硬さを見直すことで、首や顎にかかる負担を減らし、寝ている間の歯ぎしりを軽減できることがあります。
- 高さ調整ができる枕
- 首と頭をしっかり支える低反発枕
- 横向き寝よりも仰向けで使いやすい設計の枕
など寝具を工夫するだけでも、「朝起きたときの顎のだるさ」が和らぐケースは多いのです。
グッズの正しい活用法
マウスピースやグッズはあくまで補助的な対策です。
- 就寝前に顎や首を軽くマッサージする
- リラックスして眠れる環境を整える
- 定期的に歯科や整体でチェックする
といった習慣と組み合わせることで、効果を最大限に活かせます。
✅ 整体院からのご提案
整体かいろはすでは、枕や姿勢のアドバイスに加え、顎・首・肩の筋肉を整える施術を行っています。
- グッズだけでは不安
- 体のバランスも見直したい
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
\マウスピースを使っても歯ぎしりが気になる方へ/
子どもの歯ぎしり(1歳〜5歳)は心配?成長との関係
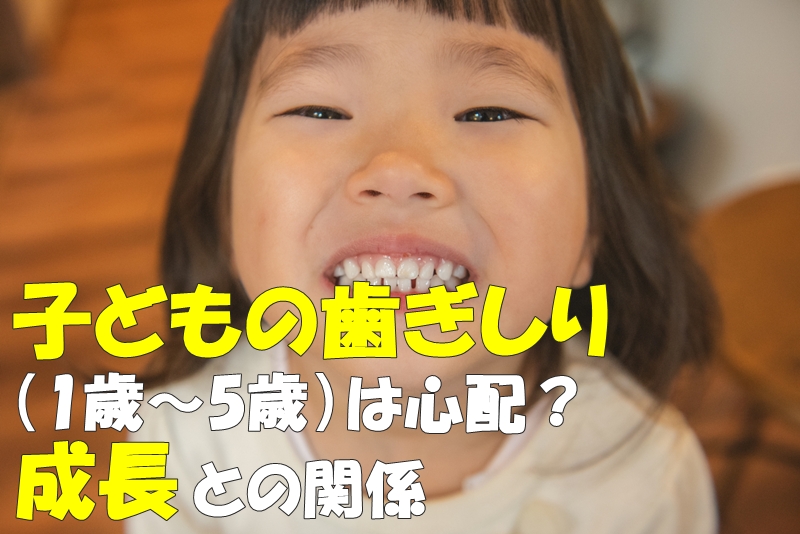
- 幼児期の歯ぎしりはよくあること
- 4歳・5歳の歯ぎしり
- 子どもの歯ぎしりで気をつけたいこと
- 親ができるサポート
▶主なポイント
- 幼児の歯ぎしりは一時的な成長のサインであることが多い
- 永久歯や顎の成長に伴って自然に落ち着くケースが多い
- 続く場合は小児歯科への相談が安心
幼児期の歯ぎしりはよくあること
「歯ぎしり 1歳」「歯ぎしり 一歳」と検索されるように、1歳前後から歯が生えそろい始める時期に歯ぎしりが見られることがあります。
これは歯や顎が発達していく過程で自然に起こる現象であり、成長に伴う一時的なものがほとんどです。
同様に「歯ぎしり 2歳」「歯ぎしり 3歳」といった年齢でもよく見られます。

4歳・5歳の歯ぎしり
「歯ぎしり 4歳」「歯ぎしり 5歳」と検索されるケースも多いです。
この時期は乳歯から永久歯へと生え変わる準備が始まるため、顎や歯の位置を調整する目的で歯ぎしりが続く場合があります。
歯並びや噛み合わせに関係していることもあるため、小児歯科でチェックしてもらうと安心!
子どもの歯ぎしりで気をつけたいこと
幼児の歯ぎしりは基本的に自然に収まりますが、以下のような場合は注意が必要です。
- 歯が大きく削れている
- 顎が痛いと訴える
- 日中も食いしばりをしている
- いびきや睡眠時無呼吸のような症状がある
こうしたサインがある場合は、歯科や小児科での診察を検討しましょう。
親ができるサポート
- 就寝前にリラックスできる環境を整える
- 枕の高さや寝姿勢を整える
- 強く叱らず、自然に様子を観察する
などといったサポートで十分なケースが多いです。
✅ 整体院からのご提案
整体かいろはすでは、子どもの姿勢チェックや体のバランス調整を行い、成長に合わせたサポートをしています。
- 歯ぎしりが長引いて心配
- 姿勢や噛み合わせも見てほしい
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
\お子さんの歯ぎしりや姿勢が気になる親御さんへ/
歯ぎしりをチェックする方法|録音アプリや日中の癖
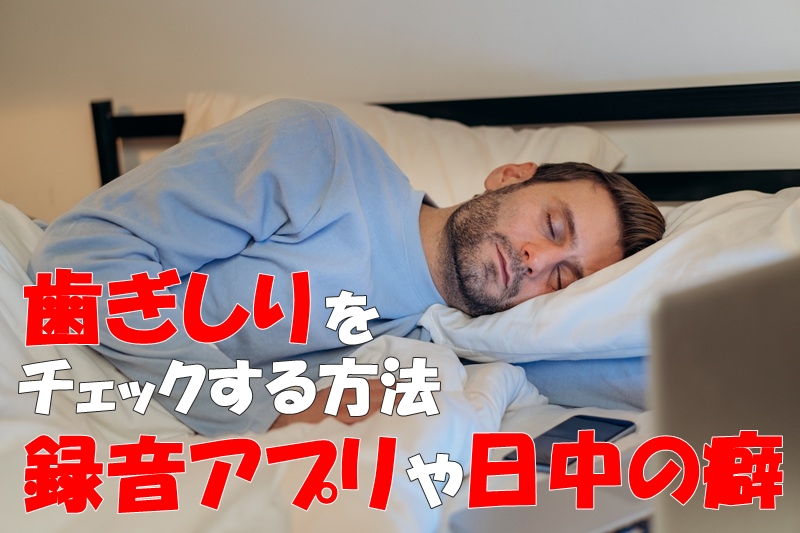
- 録音アプリで夜間の歯ぎしりをチェック
- 起きている時の食いしばりチェック
- 夢と歯ぎしりの関係
- 自分でできるチェックポイント
▶主なポイント
- 録音アプリで睡眠中の歯ぎしり音を確認できる
- 起きている時の食いしばり習慣を観察することも重要
- 夢や眠りの質が歯ぎしりに影響しているケースもある
録音アプリで夜間の歯ぎしりをチェック
「自分が歯ぎしりをしているかどうか分からない」という方は多いです。
そのときに役立つのが録音アプリです。

これを使えば「ギリギリ」「カチカチ」という歯ぎしり音を客観的に確認することができ、症状の有無や頻度を把握する助けになります。
起きている時の食いしばりチェック
「歯ぎしり起きてる時」という検索があるように、歯ぎしりは必ずしも睡眠中だけではありません。
- デスクワークや勉強中に上下の歯を強く噛みしめている
- 緊張すると顎に力が入ってしまう
- 無意識に舌で歯を押している
といった習慣は、日中の食いしばり=起きている時の歯ぎしりにあたります。
これを放置すると夜間の歯ぎしりも悪化するため、日常の癖をチェックすることが大切です。
夢と歯ぎしりの関係
「歯ぎしり夢」と検索されることもあります。
夢の中で緊張したりストレスを感じたりしていると、体が反応して歯ぎしりをすることがあります。

▶歯ぎしりが強く出ているサイン
- 最近よく夢を見る
- 眠りが浅い
自分でできるチェックポイント
- 朝起きたときに顎や首が疲れていないか
- 舌や頬の内側に噛み跡がないか
- パートナーに「音がうるさい」と言われないか
これらを確認することで、歯ぎしりの有無をセルフチェックできます。
✅ 整体院からのご提案
整体かいろはすでは、姿勢や筋肉の状態をチェックし、歯ぎしりの原因になりやすい首肩の緊張や顎の使い方を改善する施術を行っています。
- アプリで歯ぎしりを確認したけれど改善策が知りたい
- 起きている時の食いしばりが気になる
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
\歯ぎしりをしているか不安な方へ/
歯ぎしりは何科に相談すべき?整体でできることは?
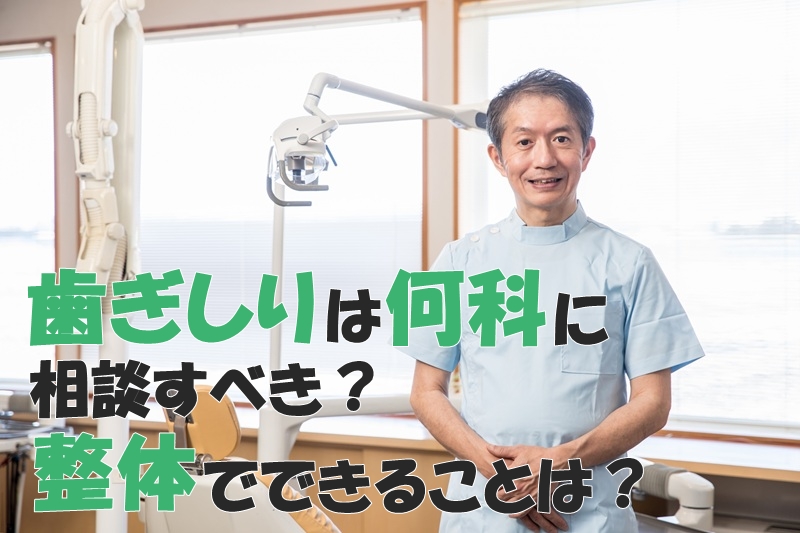
- 歯科医院に相談するケース
- その他の診療科
- 整体でできるサポート
- 夜の歯ぎしりと整体の関係
▶主なポイント
- 歯ぎしりは歯科医院に相談するのが基本
- 耳鼻咽喉科や心療内科が関係するケースもある
- 整体では姿勢や筋肉の緊張を整えてサポートできる
歯科医院に相談するケース
「歯ぎしり何科」と調べる方が多いように、基本的には歯科医院が最初の相談先です。
歯科では、
- 歯の摩耗やひび割れのチェック
- 噛み合わせや歯並びの確認
- マウスピースの作成
特に「歯ぎしりで口の中が痛い」「歯が削れてきた」という方は、まず歯科での診察をおすすめします。
その他の診療科
歯ぎしりは口だけでなく体全体の影響を受けます。
- 耳鼻咽喉科:いびきや睡眠時無呼吸が関係している場合
- 心療内科:ストレスや自律神経の乱れが大きい場合
- 整形外科:顎関節症に関連するケース
など、他の診療科と連携して治療を進めることもあります。
整体でできるサポート
「歯ぎしり 意味」と調べると「ストレス発散のサイン」という解説もあります。
つまり、体や心に負担がかかっているサインとして現れるのが歯ぎしりなのです。
- 首や肩の筋肉をゆるめて顎の負担を減らす
- 猫背やスマホ首を改善して噛み合わせを安定させる
- 呼吸や姿勢を整えて自律神経を落ち着かせる
といった施術を行うことで、歯ぎしりの間接的な改善をサポートできます。
夜の歯ぎしりと整体の関係
「歯ぎしり夜」という検索も多いですが、これは睡眠中の無意識の食いしばりを指しています。
- 日中も姿勢が悪い
- 首肩に慢性的なこりを抱えている
整体で全身の緊張を整えることで、夜の歯ぎしりが和らぐ可能性があります。
✅ 整体院からのご提案
整体かいろはすでは、歯科医院での治療と並行しながら、体全体のバランスを整えるサポートを行っています。
- 夜の歯ぎしりがつらい
- 口の中や顎が疲れる
という方は、ぜひ当院にご相談ください。
\歯ぎしりの相談先に迷っている方へ/
まとめ|歯ぎしりを予防するためにできること
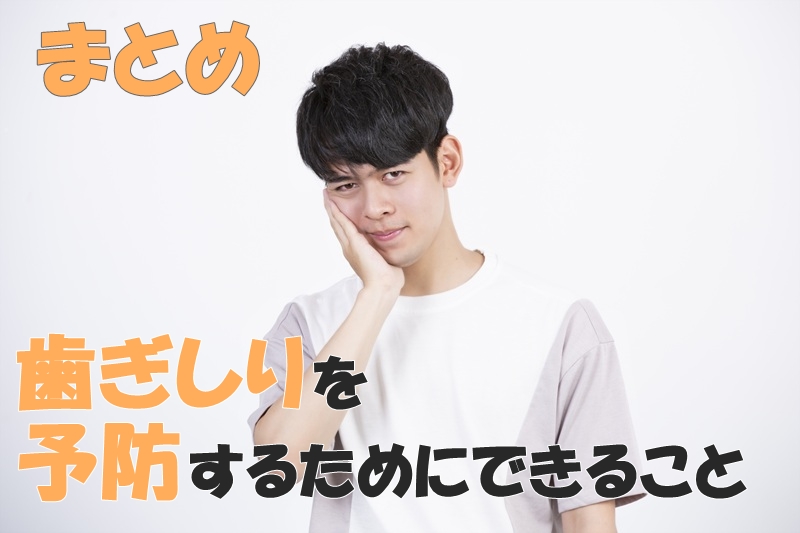
- 歯ぎしり対策の基本をおさらい
- 放置はリスクが大きい
- 年齢ごとの歯ぎしり対応
- 歯科と整体の併用でより安心
▶主なポイント
- 歯ぎしりは放置すると歯や顎、体全体に悪影響を及ぼす
- タオル・マッサージ・ツボ・マウスピース・ボトックスなど多角的な対策がある
- 整体で姿勢や筋肉の緊張を整えることも有効
歯ぎしり対策の基本をおさらい
- ストレス
- 噛み合わせ
- 生活習慣
- 姿勢の乱れ など
▶歯ぎしりをしない方法
- タオルを使ったセルフケア
- マッサージやツボ押し
- マウスピースや対策グッズ
- ボトックス注射(保険適用の有無は要確認)
など、複数の方法を組み合わせることが大切です。
放置はリスクが大きい
- 歯が削れる
- 歯が欠ける
- 顎関節症になる
- 肩こりや頭痛が悪化する
などといった深刻な問題に発展します。
また、睡眠の質が低下し、疲労感やストレス悪化の悪循環につながることもあります。

年齢ごとの歯ぎしり対応
- 幼児期(1歳〜5歳)の歯ぎしりは成長の一環で心配いらないケースが多い
- 大人の歯ぎしりは生活習慣・ストレス・姿勢改善が重要
- 高齢者は入れ歯や噛み合わせの不具合が影響する場合もある
このように、年齢やライフスタイルに応じた対策を選ぶことが必要です。
歯科と整体の併用でより安心
- 歯科医院・・・歯が削れた/マウスピースを作りたい
- 整体・・・首・肩・顎の緊張や姿勢の乱れが関係している
歯科と整体を併用することで、症状の進行を防ぎながら全身のコンディションを整えることができます。
✅ 整体院からのご提案
整体かいろはすでは、顎や首肩の緊張をほぐし、猫背やスマホ首といった姿勢の乱れを改善することで、歯ぎしりの負担を軽減するサポートを行っています。
- マウスピースやグッズだけでは不安
- 睡眠の質を改善したい
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
\歯ぎしりを根本から予防したい方へ/