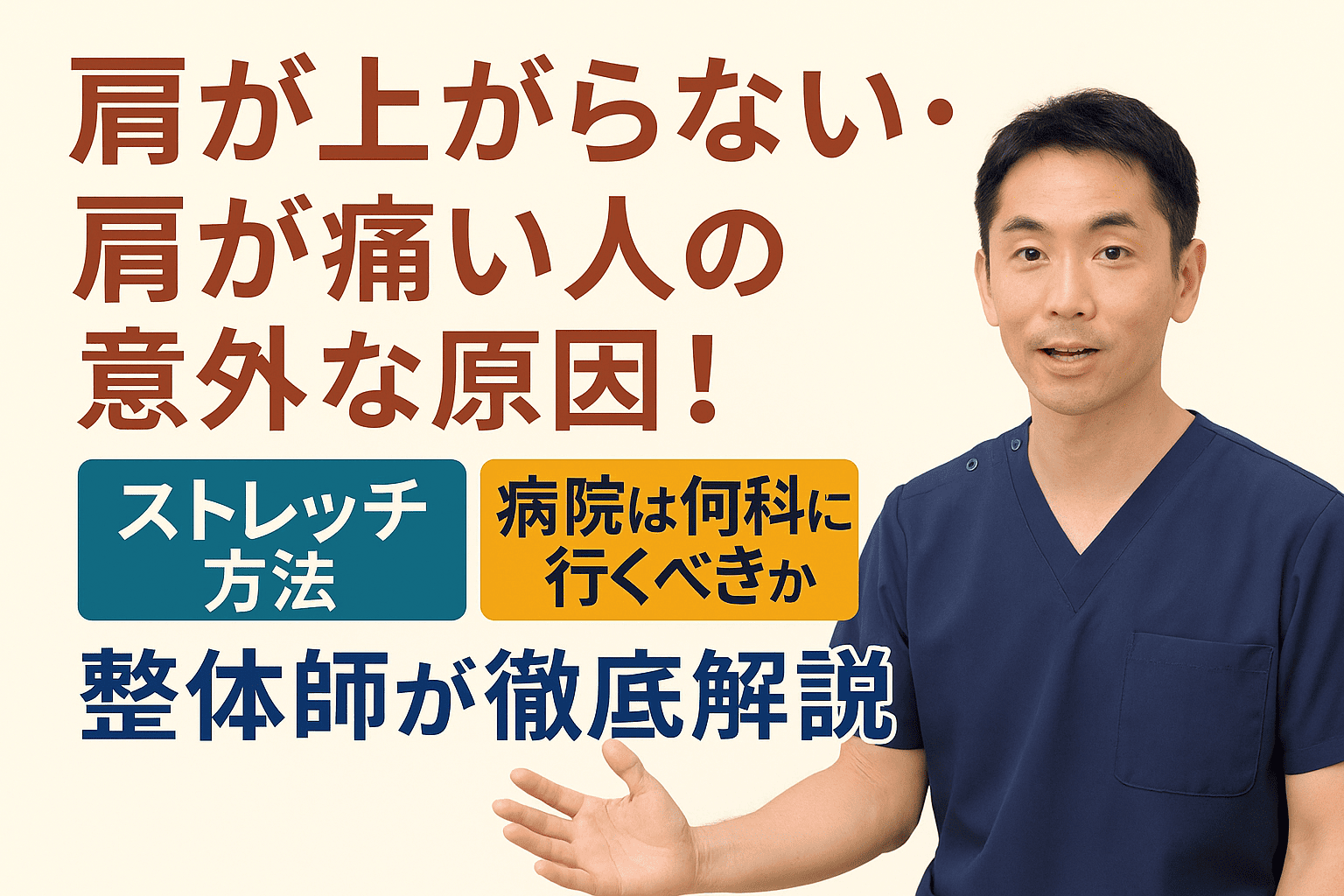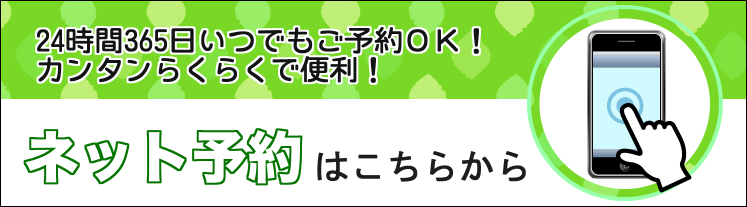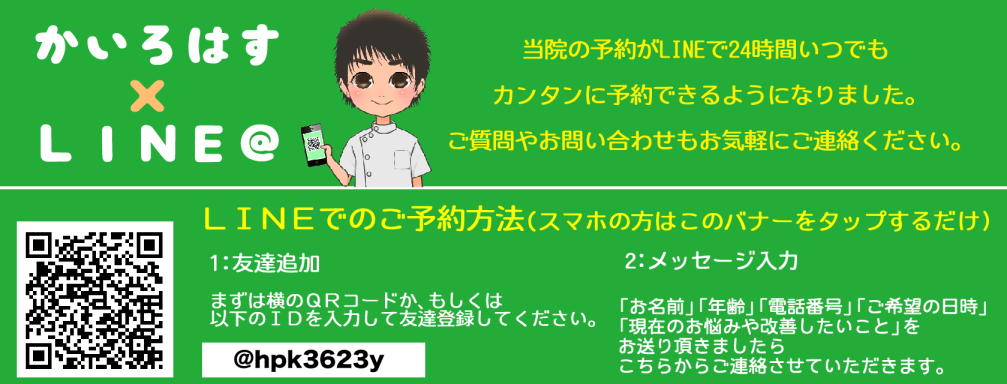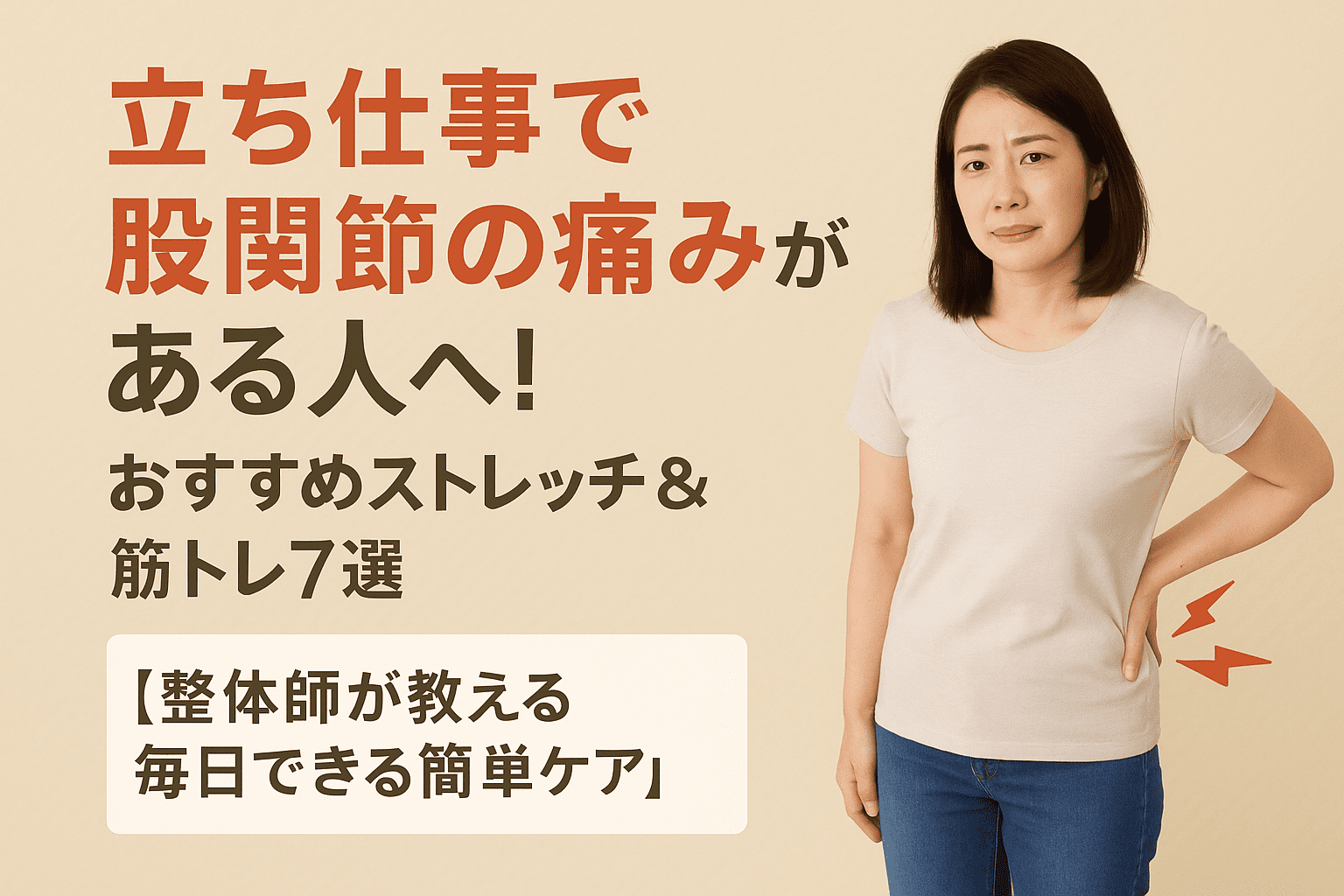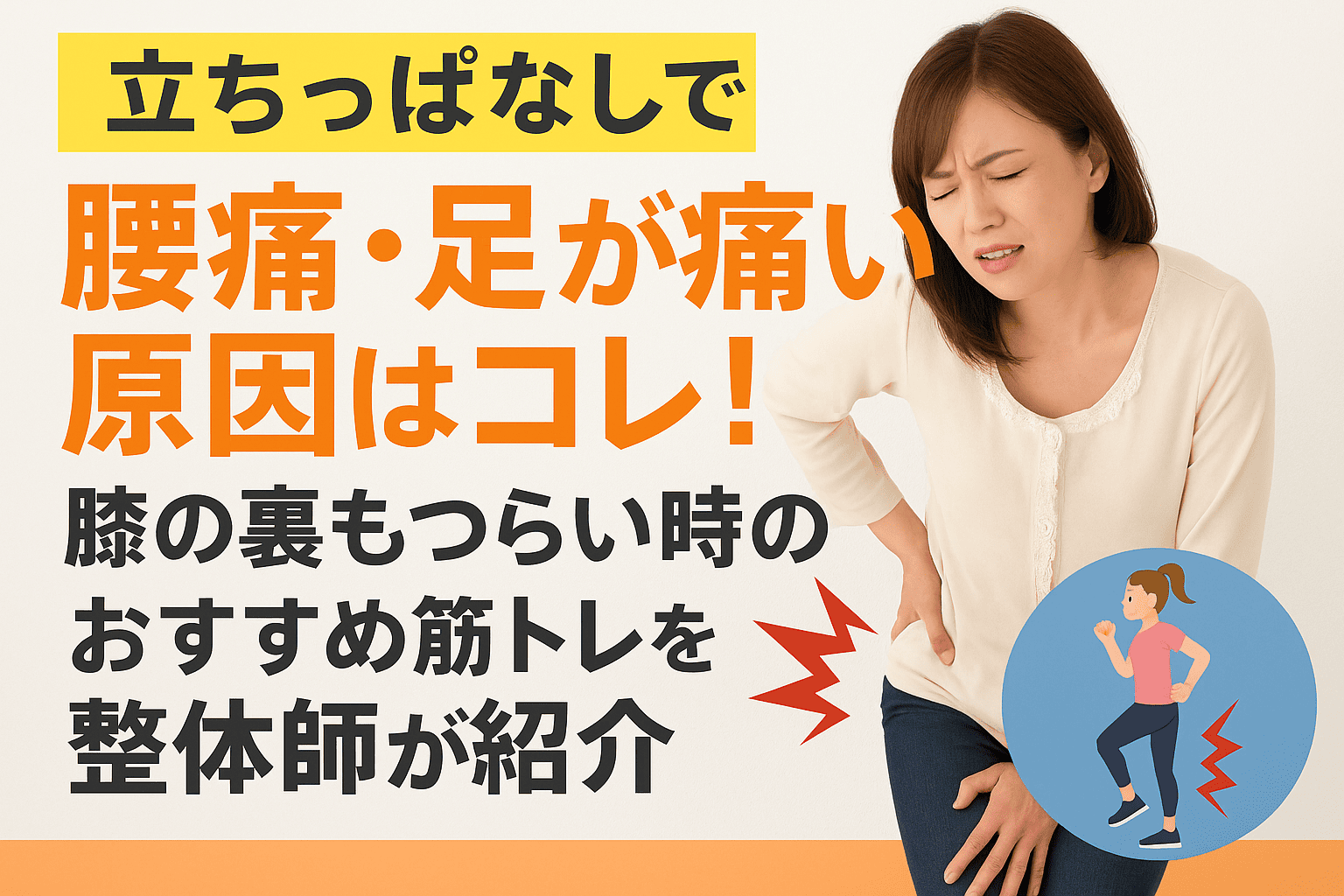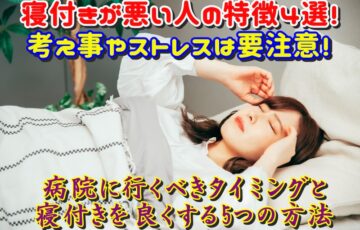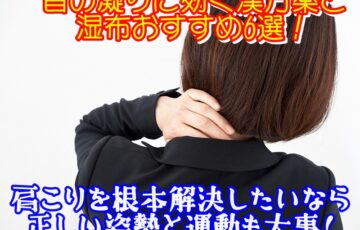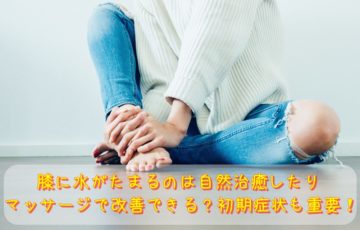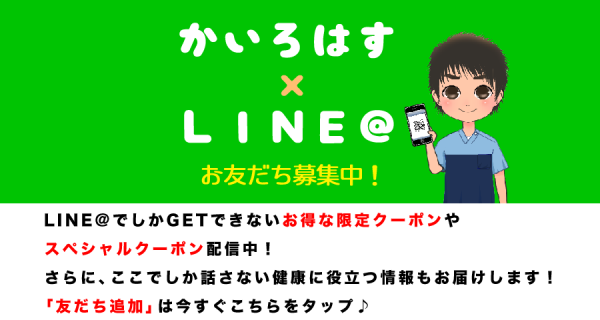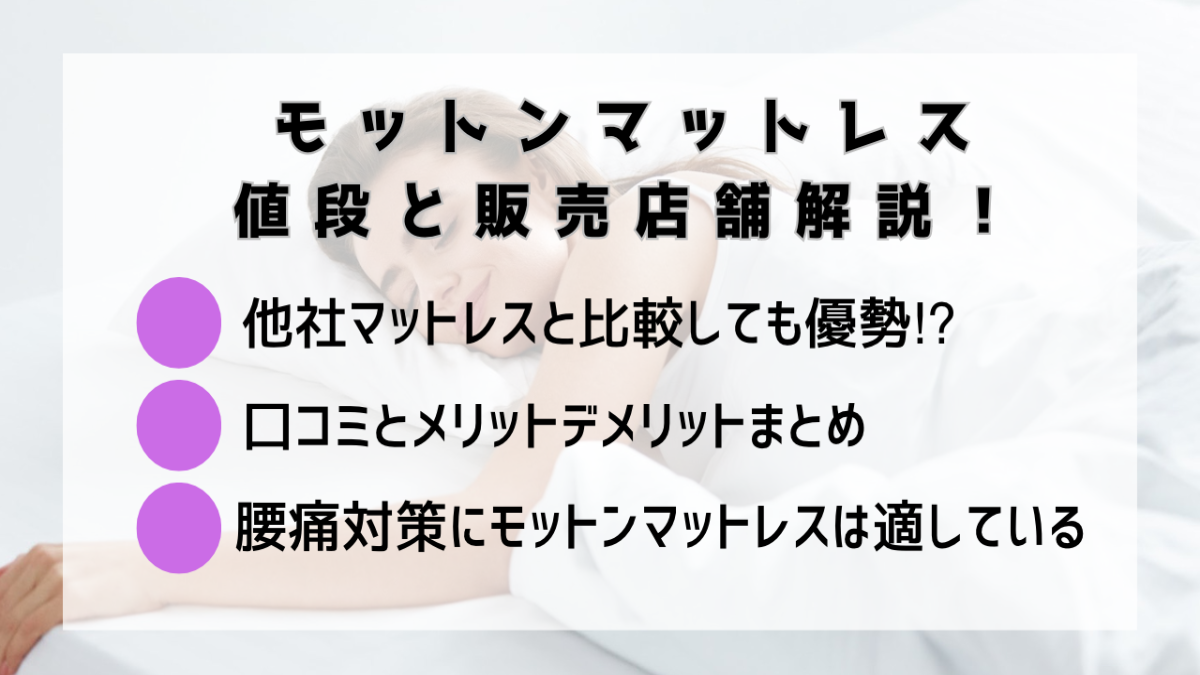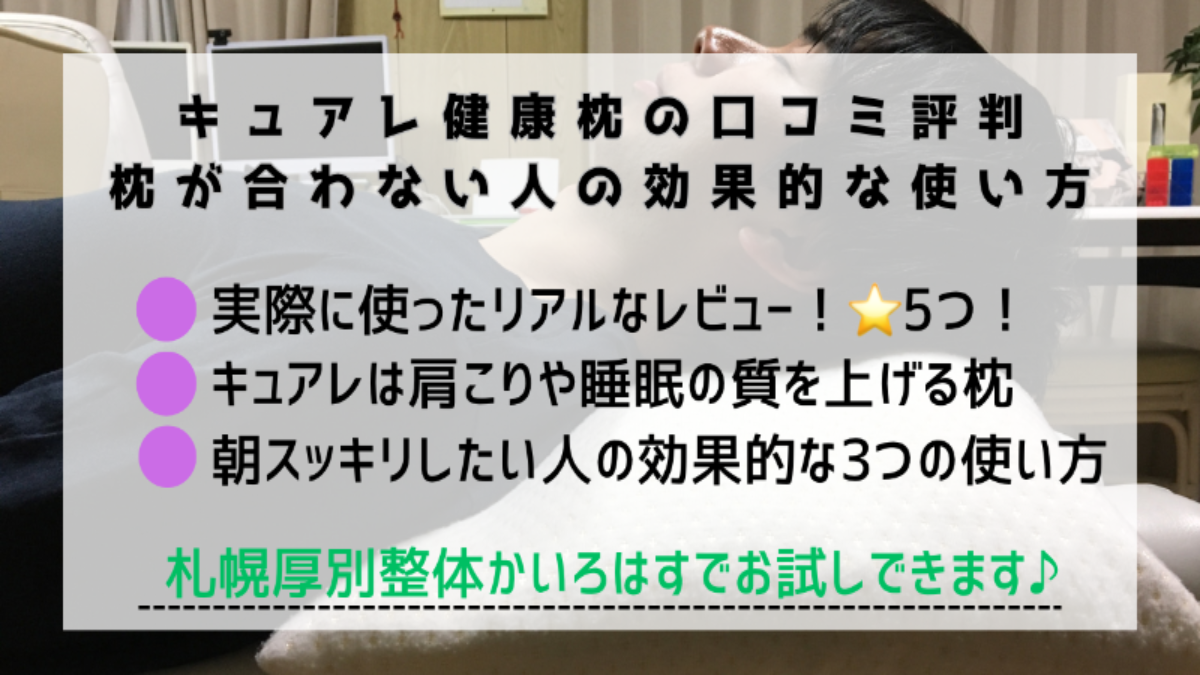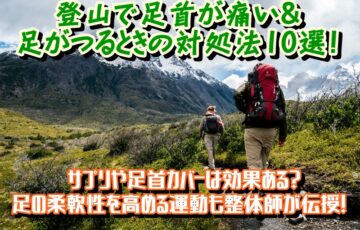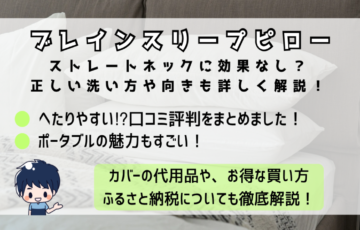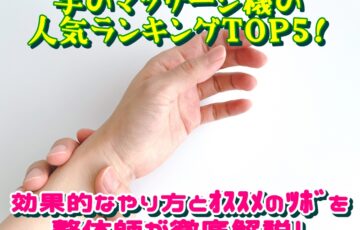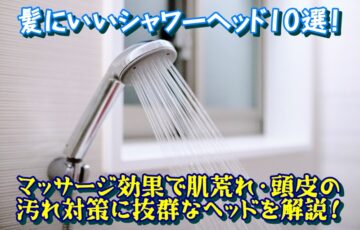肩が上がらない・肩が痛い…それ、肩だけの問題じゃないかもしれません…。
「肩が上がらなくて服を着るのもつらい…」
「デスクワークの疲れかと思って放っていたけど、だんだん痛みが強くなってきた」
「どの病院に行けばいいか分からないし、整体に頼ってもいいのかな…」
そんなふうに、肩の不調に悩みつつも対処方法が分からず、痛みを我慢してしまっている方は少なくありません。特に30〜40代の女性では、家事や育児・デスクワークなどによる負担が重なり、肩の動きが悪くなってくる方が非常に多いです。
しかし実は、「肩が上がらない・肩が痛い」といった症状の多くは、肩そのものに異常があるのではなく、姿勢の乱れや背骨・骨盤の歪み、筋肉のアンバランスが原因となっているケースが非常に多いのです。
そのため、痛いところだけをマッサージしたり湿布を貼ったりしても、根本的な解決にはつながらず、症状を長引かせてしまうこともあります。場合によっては病院の受診が必要になるケースもありますが、「病院は何科に行けばいいの?」「整体ってどうなの?」と迷ってしまうこともありますよね。
この記事では、整体師として現場で多くの肩の症例をみてきた私が、「肩が上がらない・肩が痛い人」のために、原因と正しい対処法をわかりやすく解説します。
自宅でできるストレッチや、病院を受診すべき目安、整体での施術が向いているケースなどもご紹介しています。
肩の不調は、早めに気づいて対処することで改善が早くなることがほとんどです。痛みを我慢せず、少しでも「おかしいな」と感じたら、まずは体のバランスを見直してみましょう。
私の整体院でも、「肩が痛くて上がらない」「寝返りをうつだけで肩がズキッとする」といった方が多く来院されています。
そうした方々が「もっと早く来ればよかった!」と笑顔でお帰りになる姿を見てきたからこそ、この記事を通してあなたのお悩み解決のきっかけになれば嬉しいです。
\肩が上がらない・肩が痛い人は身体のメンテナンスをしませんか?/
ページコンテンツ
肩が上がらない・痛いのはなぜ?整形外科?それとも整体?
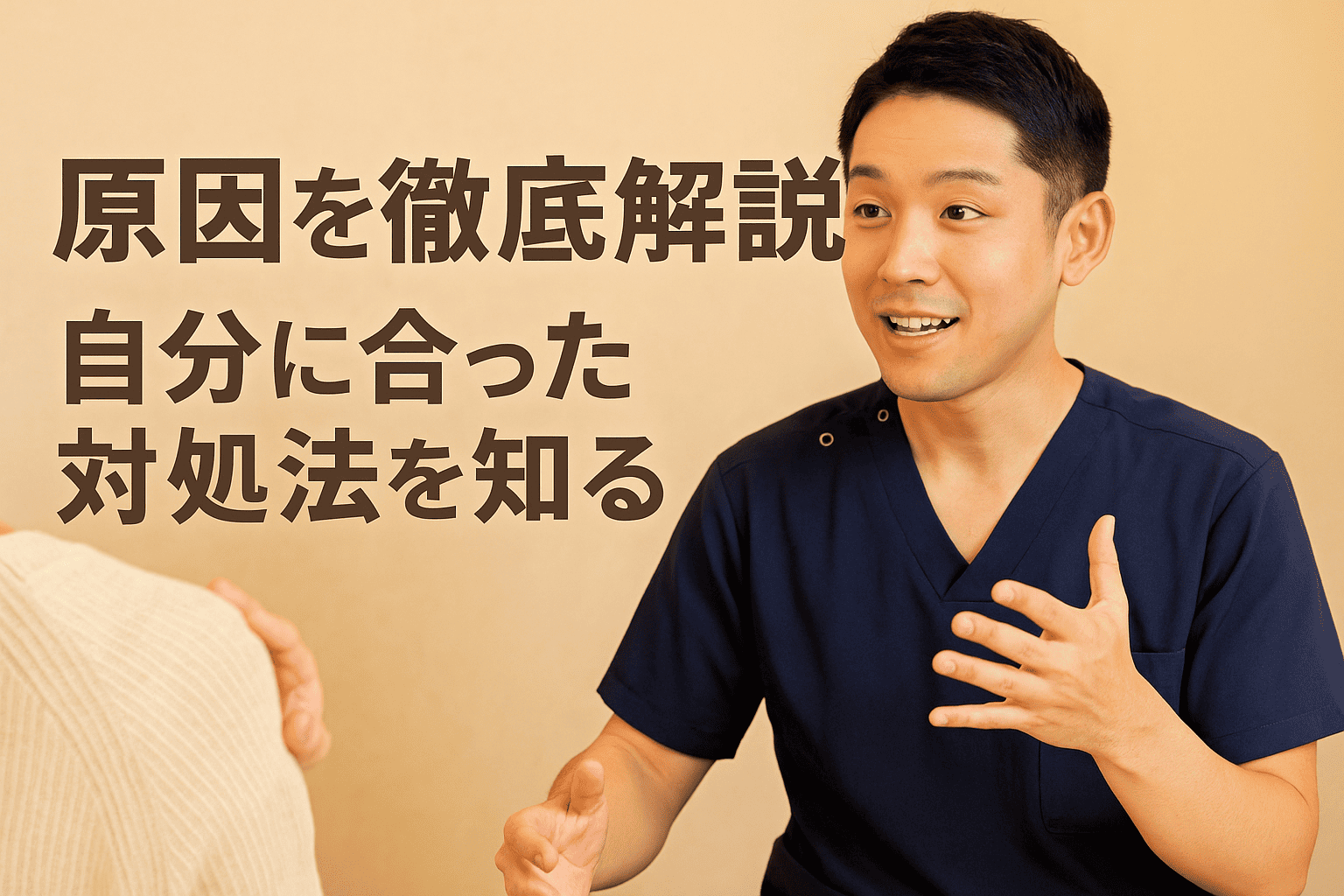
-
「肩が上がらない・痛い」の主な原因とは?
-
病院に行くべき症状と受診すべき診療科
-
整体が対応できるケースとアプローチ法
肩が上がらない・肩が痛い原因は一つじゃない
「肩が上がらない」「痛くて腕が上がらない」…そんな症状が出ると、多くの方は「年齢のせいかな?」「四十肩・五十肩かも」と考えるかもしれません。
たしかに、40代以降で肩の可動域が狭くなってくると「肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)」の可能性もあります。
しかし実際には、肩そのものに炎症や異常がないのに、肩が上がらない・痛いと感じる方もとても多いのです。
私の整体院に来られる方でも、検査では異常なしと言われたものの、「実際には洗濯物を干すのもつらい」「寝返りをうつたびに肩がズキッとする」といったリアルな不調を訴える方が少なくありません。
その理由は、肩の動きに関わる筋肉・骨格・神経が、実に多くの部位と連動しているから。
肩だけを診ても見逃してしまう原因が、背中・首・骨盤・腕・姿勢のクセなどに潜んでいるケースが多々あります。
肩の痛みはどこに相談する?病院に行くなら何科?
まず、「強い痛みが突然出た」「熱感や腫れを伴う」「夜中にズキズキして眠れない」といった場合は、整形外科の受診をおすすめします。
整形外科では、レントゲンやMRIを使って、骨や関節、腱などに異常がないかを調べることができます。
一方、「数週間様子を見たけど治らない」「病院で異常なしと言われたのに肩が痛いまま」といったケースでは、筋肉の緊張や体のゆがみが原因の可能性が高く、整体的なアプローチが有効なことも多いです。
特に、「ストレートネック」「猫背」「巻き肩」などがあると、肩まわりの可動域が制限され、関節にかかる負担が増してしまいます。こうした骨格のバランスを整えずに肩だけをケアしても、痛みの根本改善にはつながらないことが多いのです。
整体でわかる“肩の奥にある原因”
整体では、肩そのものの動きだけでなく、「なぜその肩がスムーズに動かなくなっているのか?」という原因に焦点を当てていきます。
たとえば――
-
首や背中の筋肉が硬直している
-
骨盤が傾いて姿勢が崩れている
-
肩甲骨が滑らかに動いていない
-
腕の使い方や肘のねじれにクセがある
こうした全身の歪みが重なり合うことで、肩の可動域が制限されたり、筋肉が炎症を起こして痛みが出ていることがよくあります。
また、日常生活での「足を組むクセ」「片側だけで荷物を持つ」「いつも同じ姿勢で作業する」といった習慣も、体のバランスを崩して肩に負担をかける原因となります。
整体の役割は、こうした全身のバランスを整え、「肩が痛くならない体」を根本からつくること。
痛みのある部分だけを対処するのではなく、「なぜそうなったのか?」を明らかにしていくことが、本当の意味での改善につながると私は考えています。
\肩が上がらない・肩が痛い人は身体のメンテナンスをしませんか?/
肩が上がらないときの意外な原因は「足」にあった!?

- 肩の不調と足・姿勢の関係とは?
- 足裏の崩れが肩に与える意外な影響
- 重心バランスと肩の動きの深い関係
足元が崩れると、肩に負担が集中する
「肩と足って関係あるの?」と驚かれる方も多いのですが、体はすべてつながっています。
人の体は、足の裏→足首→膝→骨盤→背骨→肩→首という順にバランスを取りながら機能しています。
このため、どこか一つでもバランスが崩れると、他の部分が代わりに負担を受けて不調が出るという仕組みです。
たとえば、足裏のアーチが崩れて偏平足気味になると、全身の重心がズレて肩や首に余計な緊張が生まれることがあります。
とくに長時間の立ち仕事やヒール靴、柔らかすぎる靴ばかり履いている方は、足元が不安定になりやすく、それが肩の可動域や痛みに影響している場合があるのです。
骨盤の傾きが肩の動きを制限する
足元の影響を受けやすいのが「骨盤」です。
骨盤は体の土台であり、ここが傾いてしまうと、背骨や肩甲骨の動きに大きく影響します。
たとえば、骨盤が前傾して腰が反っていると、背中が緊張しやすくなり、肩の可動域が制限されます。逆に骨盤が後傾すると、猫背になりやすく、巻き肩や肩こりがひどくなる傾向もあります。
このように、骨盤の傾きひとつで肩関節の動きは大きく変わるため、肩が痛いときには足元や骨盤を含めて全体をチェックすることが重要です。
整体では、足の着き方や左右の体重のかかり方なども細かくチェックしながら、肩の可動域に影響している全身のバランスを見ていきます。
重心のズレが「動きにくさ」と「痛み」の原因になる
立っているときに「片足重心」「つま先重心」「かかと重心」になっている方は要注意です。
一見すると関係なさそうですが、重心の位置がズレていると、その分だけ上半身が無理にバランスを取ろうとするため、肩や首に負荷がかかります。
特に片足ばかりに体重をかけるクセがある方は、骨盤が左右どちらかに傾き、肩の高さにも左右差が出てきます。
こうなると、肩の筋肉や関節にかかるストレスも偏り、炎症や可動域の低下につながりやすくなります。
実際、私の整体院でも「肩が痛い」と来られた方の多くが、足の左右の荷重差や重心バランスの崩れを抱えており、それを整えるだけで肩が軽くなるケースも多くあります。
肩の痛みや上がらない症状が「肩だけの問題ではない」とわかっていただけたでしょうか?
次のセクションでは、そんな症状を改善するための「自宅でできる簡単ストレッチ」を整体師の視点で紹介していきます。
\肩が上がらない・肩が痛い人は足や骨盤をチェックしましょう/
肩が痛い人におすすめ!自宅でできる整体ストレッチ5選

-
肩こり・痛みを和らげるストレッチ5選
-
肩甲骨・背中・足首まで意識した動き
-
続けやすく安全に行うコツも紹介
ストレッチ① 肩甲骨はがしで肩の可動域を回復
肩が痛いとき、肩甲骨の動きが悪くなっている方が非常に多く見られます。
肩甲骨は「肩を動かす土台」であり、ここが固まると肩関節の自由な動きが失われてしまいます。
【やり方】
-
両手を肩に乗せる
-
肘で円を描くように、前後に大きく回す
-
10回ずつゆっくり行う
ポイントは、背中が丸まらないように胸を軽く張ること。痛みが強い方は、無理せず小さな動きから始めましょう。
ストレッチ② 壁つき腕のばしで胸を開く
猫背や巻き肩の方におすすめのストレッチです。デスクワークで固まりやすい胸の筋肉を緩め、肩が後ろに引きやすくなります。
【やり方】
-
壁に片手をつけて肘を伸ばす(手のひらは壁にぴったり)
-
そのまま体を反対側にひねる
-
胸の筋肉が伸びているのを感じたら、20秒キープ
左右交互に行い、1日2セットが目安です。
ストレッチ③ 背骨ゆらしで上半身をしなやかに
肩の動きは背骨の柔軟性にも左右されます。背骨が固まっていると、肩を無理に動かして痛みを誘発しやすくなるため、体幹から緩めていきましょう。
【やり方】
-
椅子に座って両手を胸の前でクロス
-
ゆっくり左右に体をねじる(腰ではなく胸椎を意識)
-
呼吸を止めずに、左右10回ずつ行う
リラックスしながら行うのがポイントです。
ストレッチ④ 足首回しで体の土台を整える
意外かもしれませんが、足首の柔軟性も肩こりや痛みに関係しています。全身のバランスを整えるためには、末端の動きも大切です。
【やり方】
-
床や椅子に座り、片足を膝にのせる
-
つま先を持って円を描くように10回まわす
-
反対方向も10回行う
足首を回すことで、ふくらはぎや股関節も連動して緩みやすくなります。
ストレッチ⑤ 肘つき肩伸ばしで深層筋へアプローチ
これは肩の奥にあるインナーマッスルに働きかけるストレッチです。肩関節の安定性を高める効果が期待できます。
【やり方】
-
テーブルやベッドに両肘をつく
-
背中を丸めず、胸をゆっくり下げていく
-
肩の奥が伸びたところで20秒キープ
呼吸を止めずにゆったりと行いましょう。
これらのストレッチは、どれも自宅で簡単にできるものばかりです。
ただし、痛みが強いときや、動かすとズキンとする場合は無理せず中止し、整体や専門機関で相談しましょう。
次は、肩の不調が「肩以外に原因がある」ことを深掘りするために、姿勢や骨格バランスに注目していきます。
\ストレッチで改善できない人はこちら/
「肩が痛い=肩の問題」とは限らない!全身バランスで見る整体的アプローチ

- 肩の不調が「姿勢のゆがみ」から起こる理由
- 骨盤・背骨・肩甲骨の連動と影響
- 整体で見る“体のつながり”の視点
姿勢の崩れが肩に与える負担とは?
私の施術経験上、「肩が痛い」と来院される方の約7割は、肩そのものよりも姿勢の崩れや体の使い方に原因があります。
とくに多いのが「猫背・反り腰・巻き肩」の3つのタイプです。
これらの姿勢では、肩が本来あるべきポジションからズレてしまい、可動域が制限され、動かそうとすると余計な筋肉に力が入りやすくなります。
その結果、筋肉のこわばりや炎症、違和感といった症状が現れるのです。
現代人の多くが日常的にPCやスマホを使うことで、前かがみの姿勢が常態化しています。
このような状態では、肩は常に引っ張られ、筋肉にストレスが溜まりやすくなります。
「ただの肩こりかな?」と軽く見ていると、やがて腕が上がらなくなったり、痛みが慢性化したりすることもあるのです。
骨盤の傾きが全身のゆがみを引き起こす
骨盤は「体の土台」と呼ばれる重要なパーツです。
この骨盤が前傾・後傾・左右に傾いていると、その上に乗る背骨や肩のバランスも当然乱れます。
たとえば骨盤が前傾すると、腰が反って背中が緊張しやすくなり、肩甲骨が固まりやすくなります。
また、後傾すると猫背になりやすく、肩が内巻きになって「巻き肩」となり、肩の可動域が制限されやすくなります。
つまり、肩の症状を根本から改善するには、肩だけでなく骨盤や背骨の配列を見直す必要があるのです。
整体では、肩の高さの左右差や骨盤の傾き、立ち姿勢・座り姿勢なども丁寧にチェックしていきます。
それにより、「なぜ肩に負担がかかっていたのか?」を明らかにし、根本的なバランス調整を行うことができるのです。
肩甲骨と背骨の連動がカギを握る
肩の動きに大きく関わるのが「肩甲骨」と「背骨」です。
肩甲骨は肋骨の上を滑るように動くことで肩関節の動きを助けています。
ところが、デスクワークやスマホ操作などで長時間同じ姿勢を続けていると、肩甲骨が背中に張り付いてしまい、可動性が著しく低下します。
また、背骨(特に胸椎)が硬くなっていると、肩甲骨がうまく外側に開かず、腕を上に上げづらくなります。
これが「腕が耳の横まで上がらない」「途中で引っかかるような感覚がある」といった症状の原因になっていることも少なくありません。
実際の施術では、肩甲骨をゆるめ、背骨の柔軟性を引き出すだけで肩の動きが劇的に改善することもあります。
肩の可動域制限を解消したいなら、肩単体ではなく、背面全体の動きと連動性に目を向けることがポイントです。
次の章では、こうした体のバランスを乱す原因となる「デスクワーク中のNG習慣」について、具体的な行動と改善策をご紹介していきます。
\肩が上がらない・肩が痛い人はカラダ全体のバランスが崩れているかも?/
デスクワーク女子必見!肩が痛くなりやすいNG習慣5つ

-
デスクワークで肩が痛くなる習慣とは?
-
姿勢・動作・環境によるNGパターン
-
今日からできる改善アクションも紹介
NG習慣① モニターの高さが合っていない
ノートパソコンや低い位置のモニターを長時間使っていると、自然と顔が前に突き出た「ストレートネック姿勢」になってしまいます。
この姿勢は首や肩に大きな負担をかけるだけでなく、背中の筋肉が常に引っ張られた状態になり、肩の可動域を狭めてしまいます。
【改善策】
モニターの上端が目の高さにくるように調整し、首が前に出ないように意識すること。
スタンドや外部モニターの活用もおすすめです。
NG習慣② 肘を浮かせたまま作業している
デスクに肘をつけず、空中で腕を支えたまま作業を続けている方は要注意です。
この状態では常に肩の筋肉を緊張させているため、気づかないうちに肩こりや痛みが蓄積されやすくなります。
【改善策】
肘をデスクまたはアームレストに軽く乗せるようにし、肩を力ませずに作業するクセをつけましょう。
特にマウス作業は無意識に力が入りやすいため、こまめに腕を休ませることが大切です。
NG習慣③ 足を組む・片側重心で座る
足を組むクセがある方や、座ったときにどちらか一方の腰だけに体重をかけている方は、体がねじれて骨盤が傾き、背骨〜肩の高さまでズレが生じやすくなります。
このズレは肩関節の位置にも影響し、「左右で腕の上がり方が違う」と感じる原因にもなります。
【改善策】
イスに深く腰掛け、両足を床にしっかりつける基本姿勢を意識すること。
骨盤クッションやフットレストを活用すると、正しい姿勢を保ちやすくなります。
NG習慣④ 休憩時間もスマホを見続けている
「休憩時間くらい肩を休めたい」と思っていても、ついスマホを見ながら猫背姿勢になっていませんか?
スマホを下を向いて見続ける姿勢は、首・肩・背中に大きな負担をかけ、結果として肩の可動域を狭めてしまいます。
【改善策】
目線の高さまでスマホを持ち上げるか、短時間でも目を閉じて深呼吸する習慣を取り入れること。
可能であれば、休憩中はストレッチや軽い肩回しを行うと効果的です。
NG習慣⑤ 無意識の「歯の食いしばり」
実は、肩こり・首こりが強い方の多くに「歯の食いしばり」のクセがあります。
特に集中してPC作業をしているときや、ストレスを感じているときに無意識で食いしばることで、肩まわりの筋肉が硬直してしまいます。
【改善策】
「気づいたら食いしばっていないか?」をチェックするだけでも意識が変わります。
こまめに口元をゆるめ、深く呼吸するだけでも肩の緊張を和らげることができます。
こうしたNG習慣は、気づかないうちに肩の動きや柔軟性を奪ってしまう原因になります。
次のセクションでは、肩の不調が悪化しやすい「セルフケアの落とし穴」について、避けたい行動と正しい対処法をお伝えします。
\デスクワークで肩が痛い人はこちら/
痛みが長引く人がやりがちなセルフケアの落とし穴
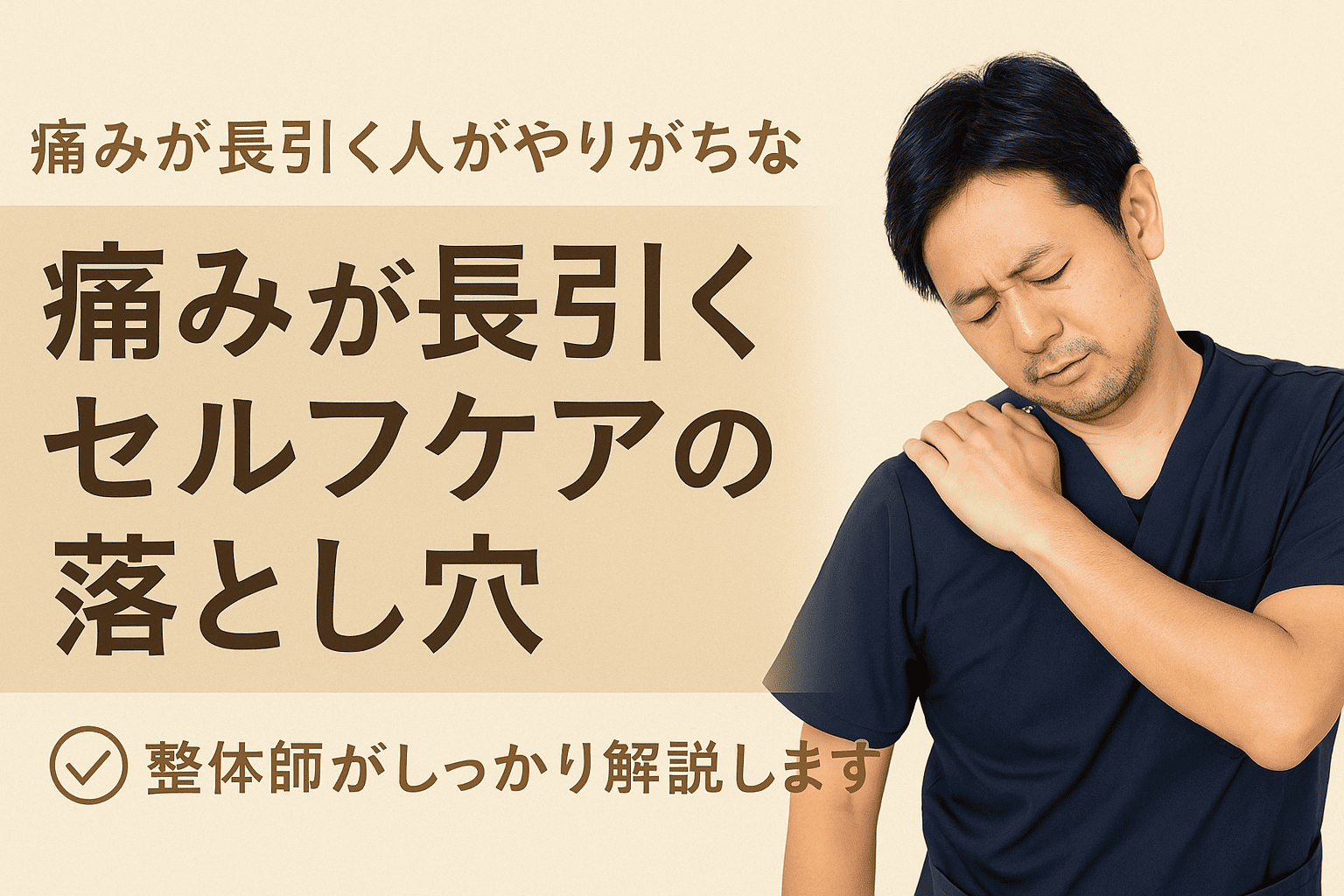
- 肩の痛みが悪化するセルフケアの例
- 温める?冷やす?の正しい使い分け
- 回復を早めるために必要な考え方
落とし穴① 痛くても無理やりストレッチしてしまう
肩が痛いとき、「固まっているから動かさなきゃ」と思い、無理にストレッチをしていませんか?
確かに可動域を広げることは大切ですが、強い痛みを感じながら無理に動かすのは逆効果になることもあります。
炎症がある状態で筋肉を引っ張ると、かえって組織を傷めてしまい、さらに動かしづらくなったり、慢性化する原因になることも。
「ストレッチ=良いこと」と思い込まず、自分の体の反応をよく観察することが大切です。
【正しい対処】
痛みがあるときは「痛気持ちいい」を超えない範囲でゆっくり伸ばすこと。
痛みのピーク時には一時的にストレッチを控える判断も重要です。
落とし穴② 湿布や冷却で冷やしすぎている
肩が痛いと「とりあえず冷やす」という方も多いですが、慢性的なこりや可動域制限の場合、冷やすことで筋肉が硬直しやすくなり逆効果になることがあります。
急な痛み(捻挫や打撲など)のような炎症性の症状には冷却が適していますが、肩こりや可動域低下のように血行不良が原因のケースでは、温めた方が回復を早めることが多いです。
【正しい対処】
症状が「腫れている・熱を持っている・ズキズキする」なら冷却。
「じんわり重い・こり固まっている・動かしにくい」なら温めを選びましょう。
落とし穴③ 放置しすぎて“動かない肩”になってしまう
「痛いけどそのうち治るかな」と放置し、何ヶ月も経過してしまうと、筋肉や関節が固まって本当に動かなくなる「拘縮(こうしゅく)」の状態に陥ることがあります。
ここまで進行すると、改善に数ヶ月〜半年以上かかることも少なくありません。
特にデスクワーク中心の生活では、日常的に肩を動かす頻度が少ないため、放置によって悪化しやすい傾向があります。
また、安静にしすぎて筋力まで落ちてしまうと、回復もさらに遅くなります。
【正しい対処】
痛みがある時期は安静にしつつ、徐々に「ゆるやかに動かす」ステップに移行しましょう。
放置ではなく「観察」と「適度な刺激」を大切にするのが整体的な考え方です。
肩の痛みは、ただマッサージやストレッチをすれば良くなるわけではありません。
間違ったセルフケアで悪化させてしまう前に、自分の状態を正しく判断する知識を身につけておくことが大切です。
次は、整体院での実際の施術の流れや、どんな人がどんな目的で通っているのかについてご紹介していきます。
\痛みが長引く人はこちらをチェック/
整体ではどう対応する?肩が上がらない人への施術アプローチ
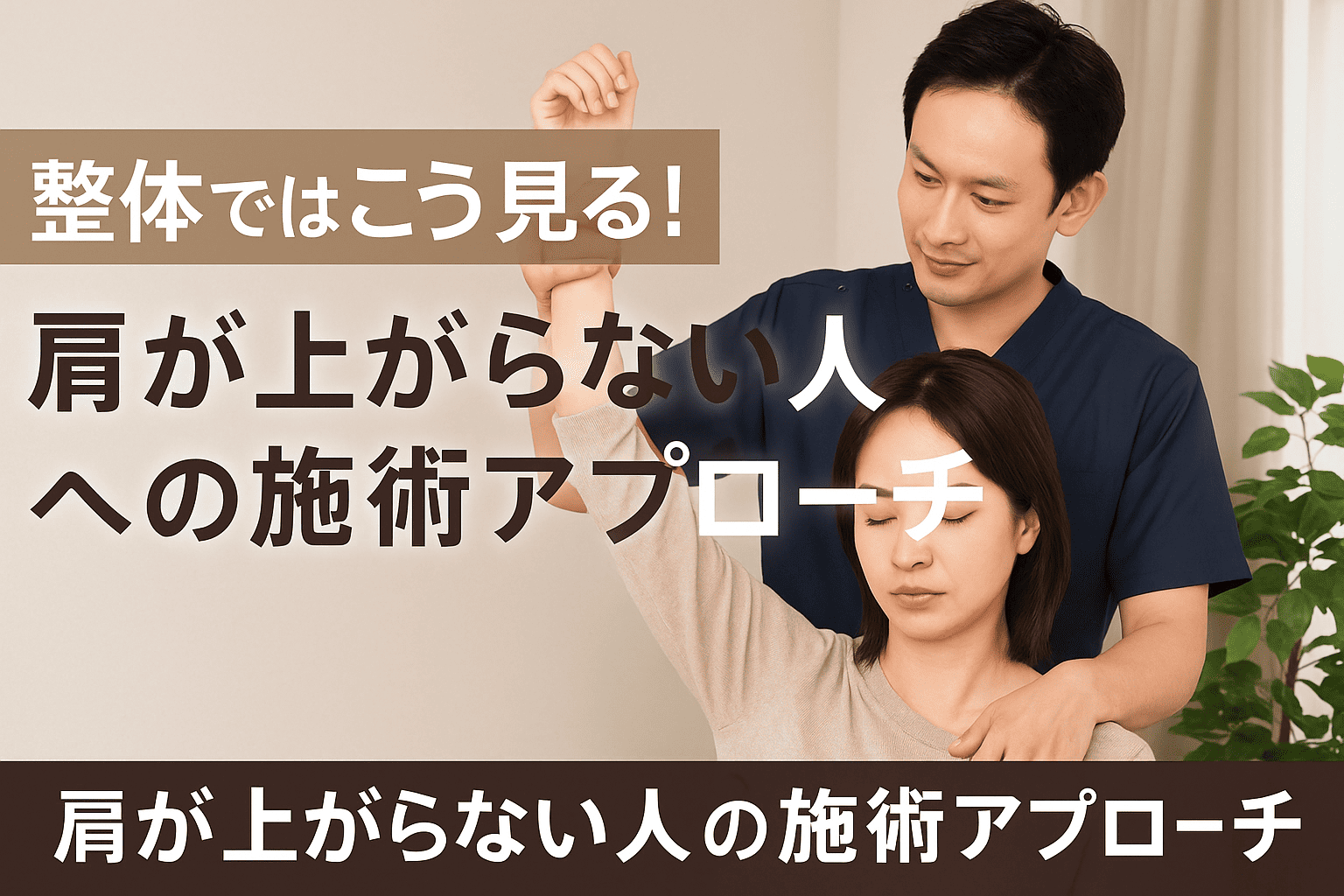
-
整体では肩の不調にどう対応する?
-
初回カウンセリングから施術までの流れ
-
改善に必要な通院頻度や期間の目安
姿勢チェックからスタート。まずは原因を見極める
整体院に来られる方の多くが、「病院で異常なしと言われたけど、やっぱり痛い」「肩が上がらない原因が知りたい」といったお悩みを抱えています。
こうした場合、整体ではまず「どこに原因があるのか?」を丁寧に見極めることからスタートします。
【初回の流れ(例)】
-
カウンセリングで症状・経過・生活習慣を確認
-
姿勢・骨格・肩の動き・左右差などを検査
-
肩だけでなく全身のバランスを評価
たとえば、肩の高さの左右差、骨盤の傾き、背骨のねじれ、肩甲骨の硬さなどを細かくチェックすることで、肩に負担がかかっていた理由を可視化していきます。
肩だけでなく“連動する部位”をゆるめる施術
肩が上がらない・痛いといった症状でも、実際の施術は肩だけにアプローチするわけではありません。
多くの場合、首や背中、骨盤、肩甲骨、腕のねじれなどが関係しているため、それらをトータルで調整していきます。
【よくある施術ポイント】
-
肩甲骨まわりの筋肉をゆるめて可動域を広げる
-
背骨の柔軟性を引き出し、上半身の動きをなめらかにする
-
骨盤や股関節の歪みを整え、体全体のバランスを調整する
痛みが強い方には、まずはゆるやかな手技で神経や筋肉を落ち着かせるアプローチから始め、無理なく整えていくことを重視します。
また、施術後にはセルフケアの方法や日常姿勢の注意点なども丁寧にアドバイスします。
「受けたら終わり」ではなく、「良い状態を保つためにどう動くか」をご自身でも意識できるようになるのが、整体の特長です。
通院頻度と期間の目安は?
通院の頻度や期間は、症状の強さや生活習慣によって個人差がありますが、一般的には以下のような流れで進むことが多いです。
【改善までの目安(例)】
-
初期:週1回を2〜3週(痛み軽減と可動域回復)
-
中期:2週に1回(姿勢の安定・再発予防)
-
安定期:月1回程度(メンテナンス・リフレッシュ)
肩の痛みは放っておくと慢性化しやすく、回復にも時間がかかる傾向があります。
特に「夜間痛」「日常動作での引っかかり感」がある方は、早めに体のバランスを整えることで回復スピードが格段に変わります。
\カラダのバランスを整えたい人はこちらをチェック/
まとめ|「肩が上がらない・肩が痛い」は体のサイン。早めに整えよう!
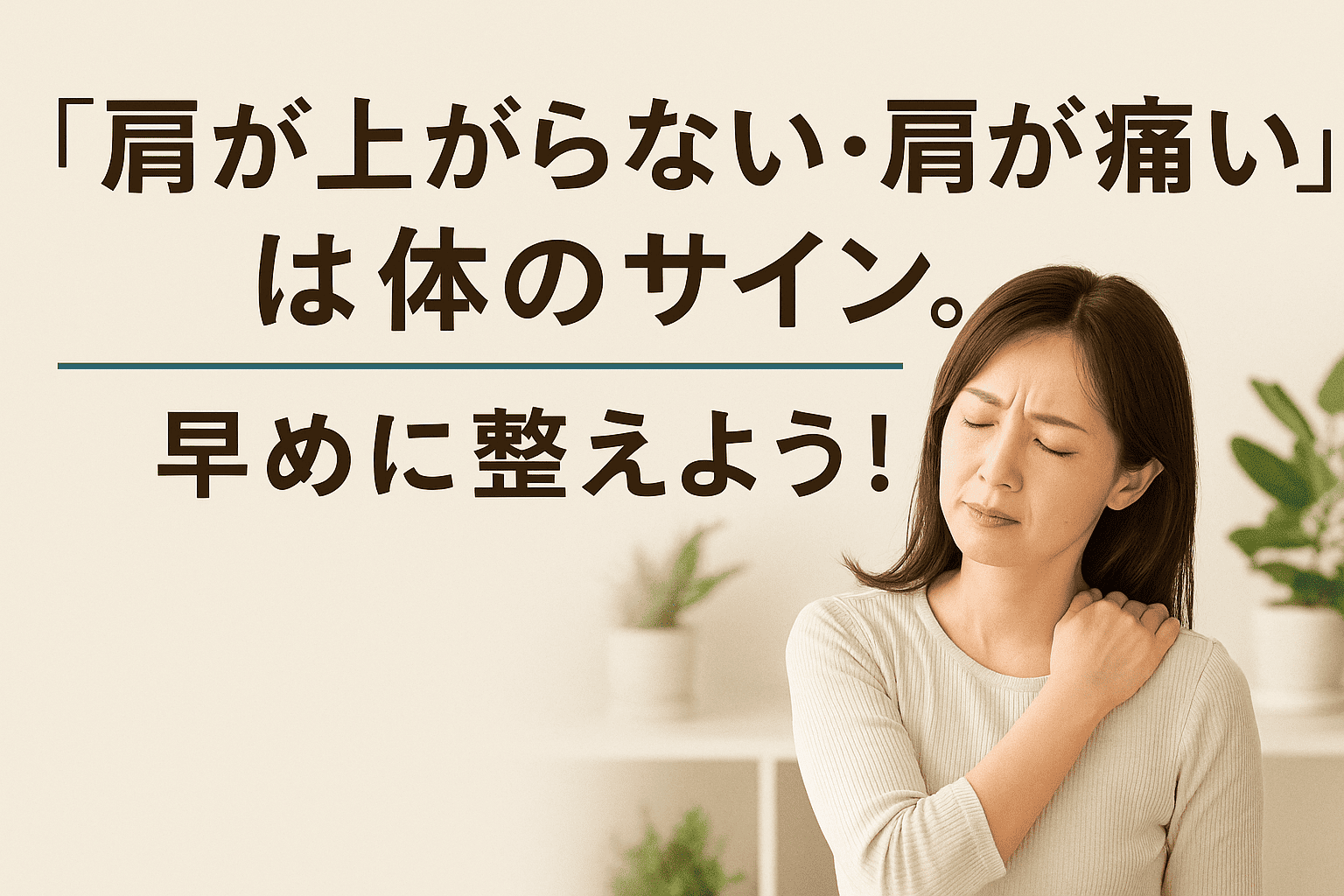
- 肩の痛みを放置してはいけない理由
- 自分でできること・プロに任せるべきこと
- 整体を活用するタイミングとメリット
肩の痛みや可動域制限は「体のSOS」
「肩が上がらない」「腕を動かすと痛い」といった症状は、日常生活に大きなストレスを与えるだけでなく、体が発している明確なサインでもあります。
これまで見てきたように、肩の問題は単純な筋肉疲労だけでなく、姿勢の崩れ・骨格バランス・体の使い方のクセなど、さまざまな要因が絡み合って起こっています。
そのため、痛みを一時的に抑えるだけの対処では、すぐに再発したり、慢性化してしまう可能性があります。
逆にいえば、肩の不調をきっかけに体の全体バランスを見直せば、不調を根本から改善するチャンスにもなります。
セルフケアとプロの施術、どう使い分ける?
肩の痛み対策には、もちろん自分でできるストレッチや生活習慣の見直しも重要です。
この記事でもご紹介したように、肩甲骨や背中・足首の柔軟性を高めることで、可動域が改善するケースも多くあります。
ただし、
-
痛みが長く続く
-
夜中にズキズキして眠れない
-
どこを動かしても改善の兆しがない
といった場合には、セルフケアだけでは限界があります。
そんなときは、体の状態を客観的にチェックし、根本から整えてくれる整体のような専門的なサポートを取り入れるのがおすすめです。
また、自分では気づかない姿勢のクセや重心バランスの崩れなどは、第三者の視点で初めて分かることも多くあります。
整体は「未病」のうちに通うのがおすすめ
「病院に行くほどではないけど、違和感がある」「なんとなく肩が重い日が続いている」
――そんなときこそ、整体を上手に活用するタイミングです。
痛みがひどくなってからでは、改善にも時間がかかります。
それよりも、「あれ?ちょっとおかしいかも」と感じたときに体をリセットしておくことで、症状の重症化や慢性化を未然に防ぐことができます。
私の整体院でも、
-
「肩が少し上がりにくい」段階で来られた方が短期間で回復
-
「五十肩かも…」と不安だった方が、施術とセルフケアでスムーズに改善
といった事例が多くあります。
「放っておけばよくなるかも」と我慢せず、早めに整えておくことで、将来的な不調を防ぐことにもつながります。
最後に
ここまでお読みいただきありがとうございます。
「肩が上がらない・肩が痛い」といったお悩みは、決して年齢や運動不足のせいだけではありません。
姿勢や日々のクセ、そして体の全体的なバランスが関係している場合がほとんどです。
私の整体院では、一人ひとりの体の状態に合わせた丁寧な検査と施術を行っており、はじめての方でも安心してご相談いただける体制を整えています。
「このままでいいのかな…」「もう少し様子を見ようかな」と感じているあなたへ。
その違和感、今こそ見直すタイミングかもしれません。
\肩が上がらない・肩が痛いのを放置したくない人はこちら/