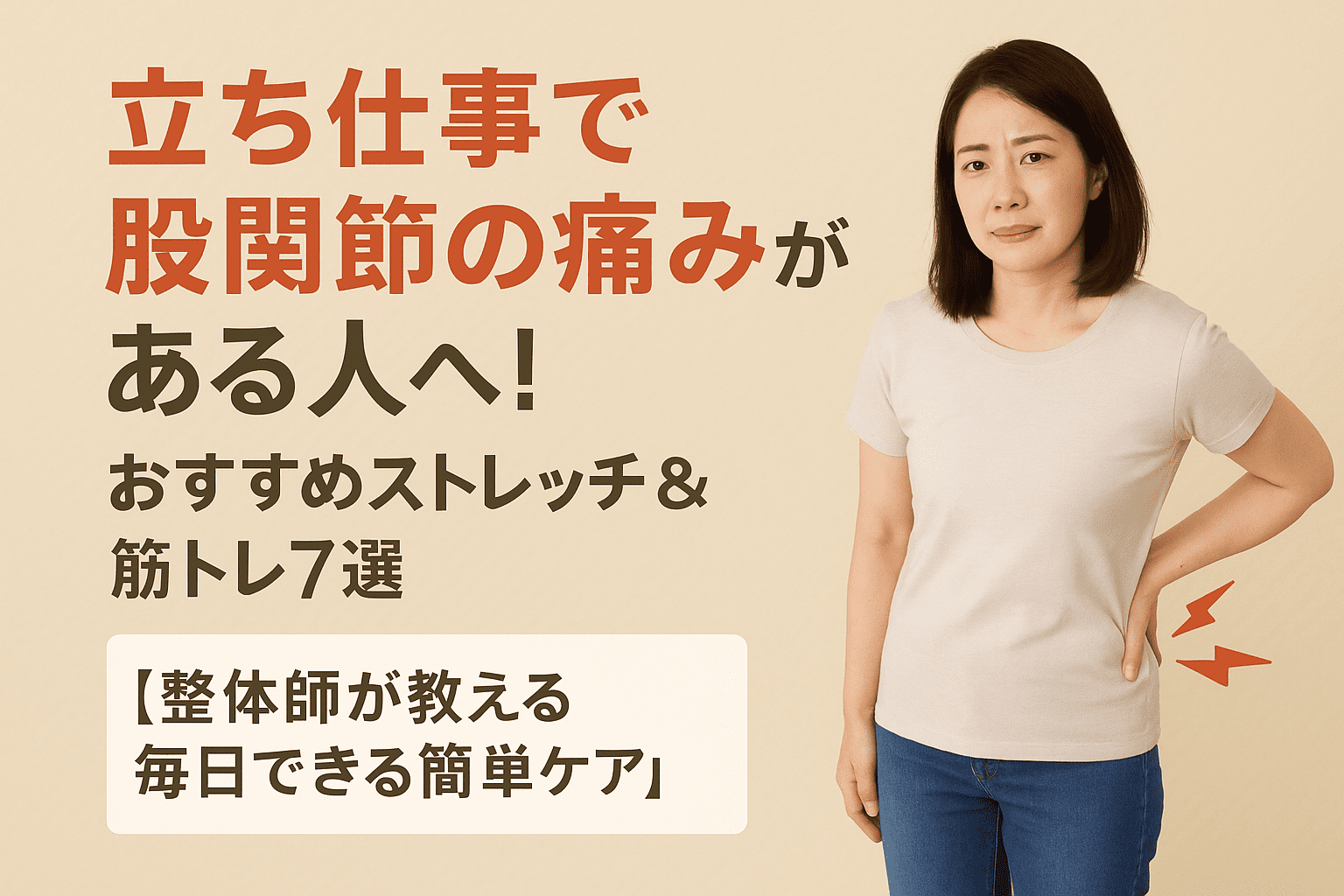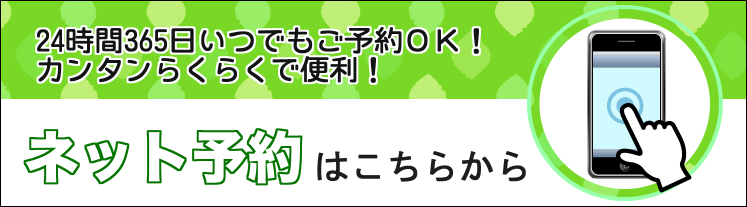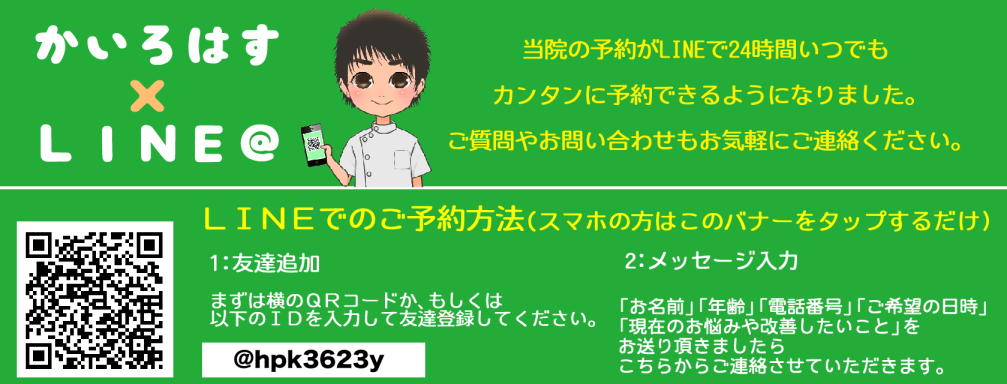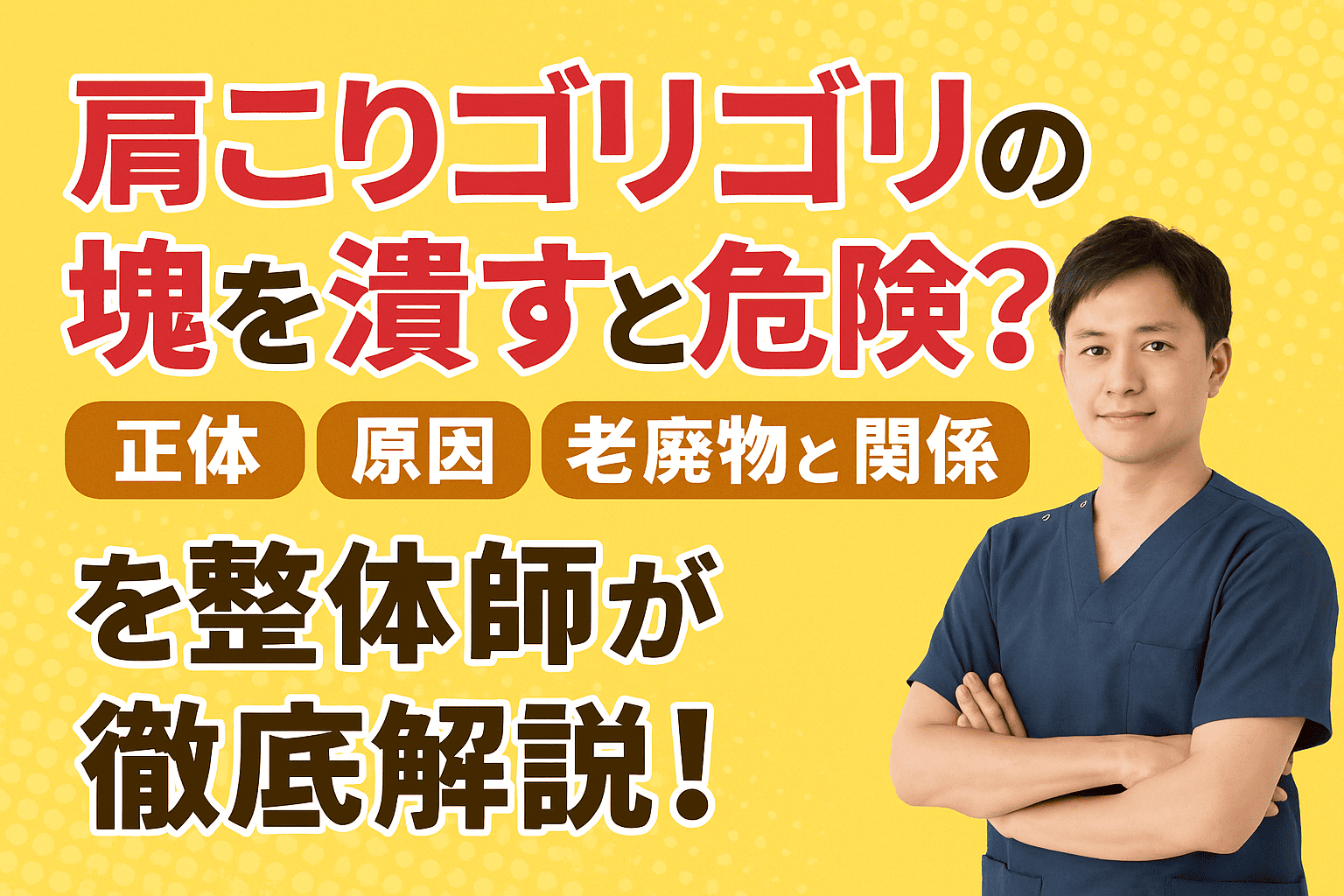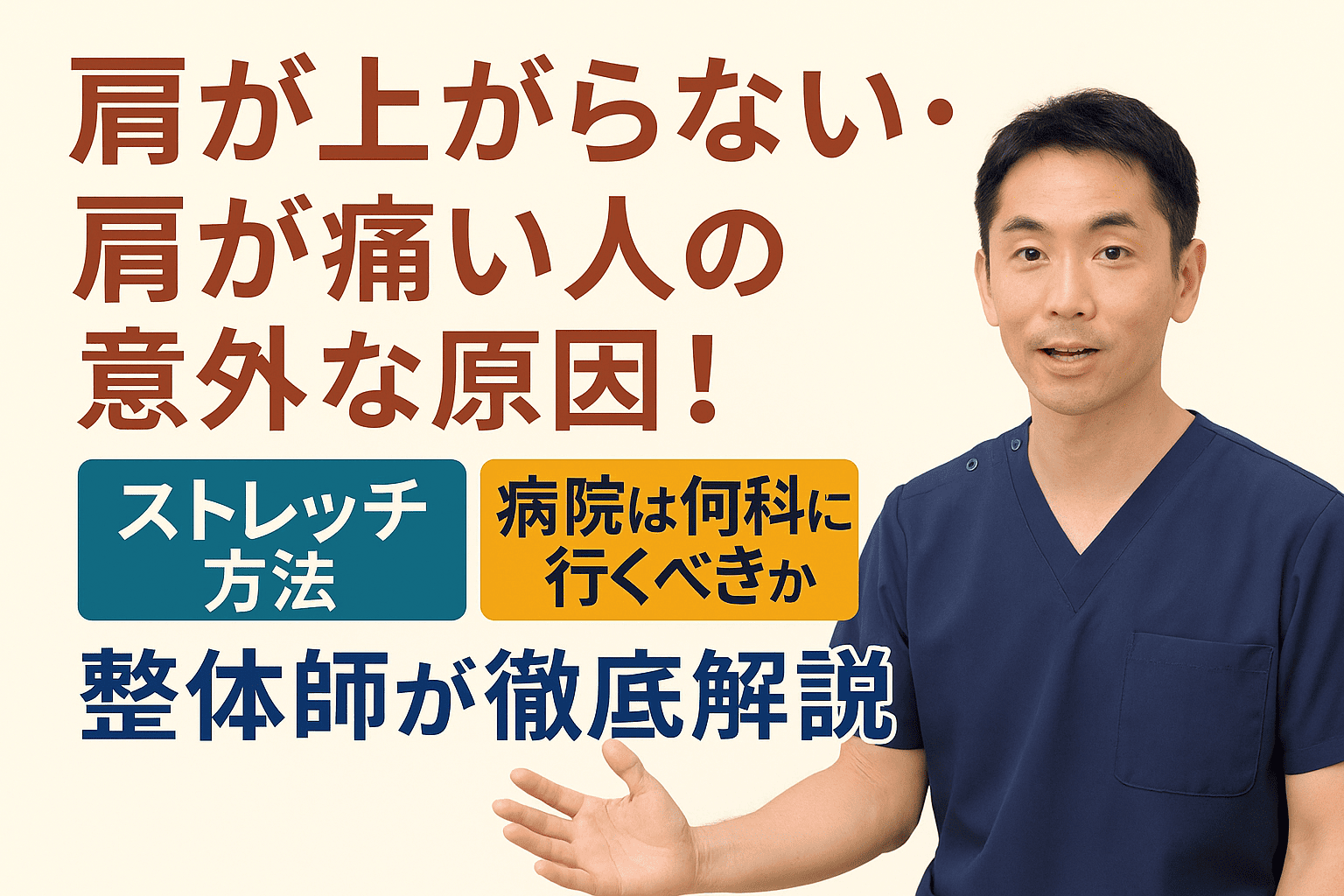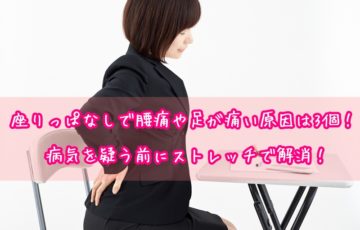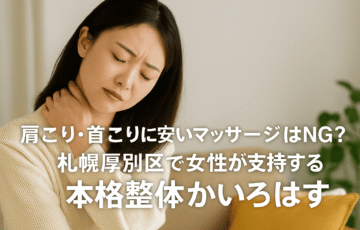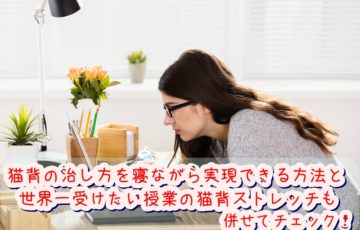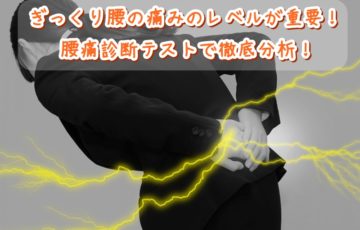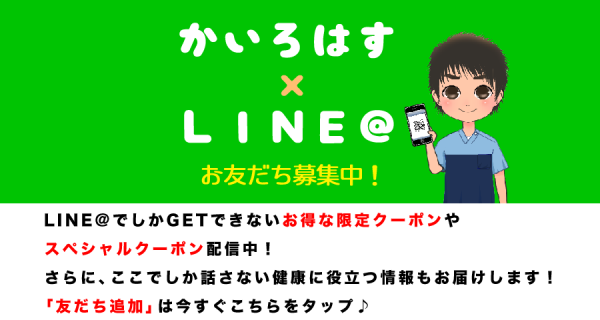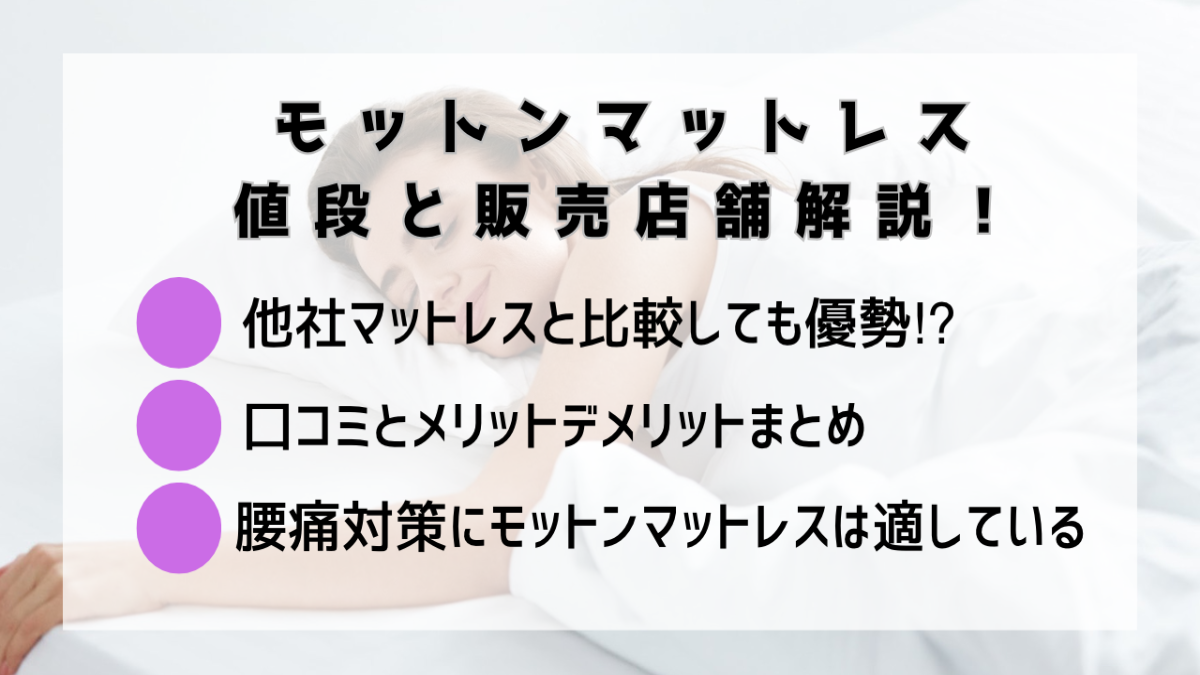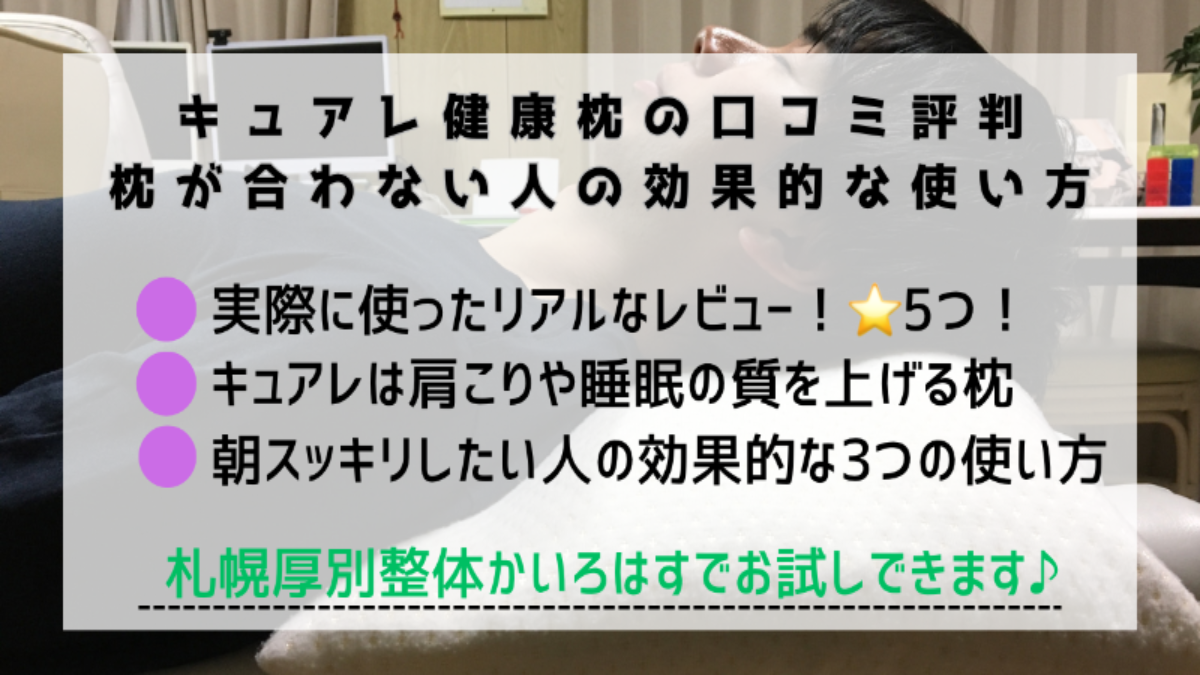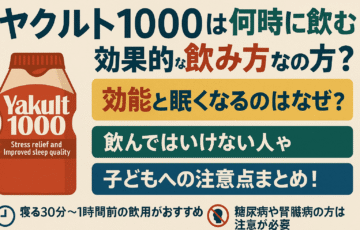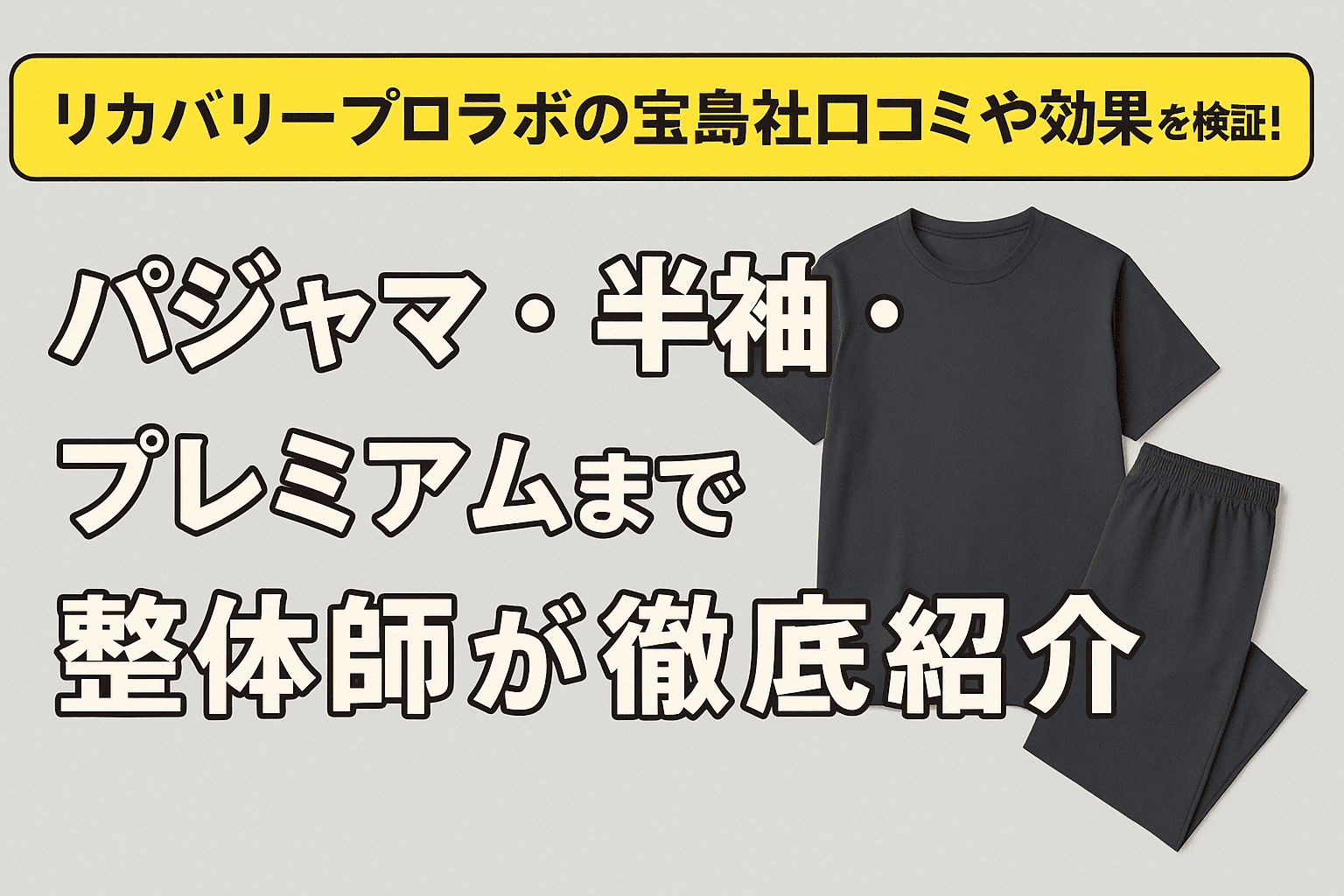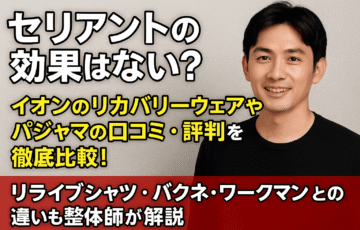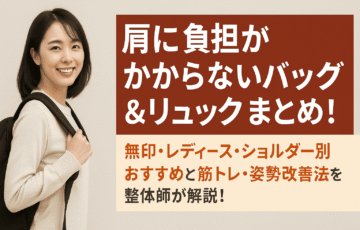「最近、立ち仕事が続くと股関節がジンジン痛む…」
「足のつけ根が重だるくて、立っているのがつらい…」
そんなお悩みを感じている方は、実はとても多いのではないでしょうか。
長時間の立ち仕事は、思っている以上に股関節に大きな負担をかけています。例えば、無意識に片足に体重をかける「片足重心」や、骨盤が前傾・後傾したまま立ち続けるクセなど、毎日の姿勢の積み重ねが、股関節まわりの筋肉や関節にストレスをかけてしまうのです。
さらに、30~40代の女性はヒールを履く機会が多かったり、冷えやすく代謝が落ちやすい体質も影響し、股関節の不調を感じやすい傾向にあります。「なんとなく疲れが取れない」「立っていると足のつけ根がズキズキする」…そんな症状を放っておくと、次第に腰や膝にも悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
とはいえ、「時間がない」「運動が苦手」「どんなケアをすればいいのかわからない」という方も多いのが現実。ですがご安心ください。実は、毎日5~10分程度の簡単なストレッチや筋トレを取り入れるだけで、股関節の痛みや違和感はグッとやわらぐことがあります。
この記事では、整体師として現場で多くの方に実践していただいているケア方法の中から、特に立ち仕事の女性に向けた股関節ケア法を厳選して7つご紹介します。どれも特別な道具は不要で、自宅でできるものばかり。無理なく続けられる内容なので、運動が苦手な方でも安心して取り組んでいただけます。
🔽 「何をやっても良くならない…」と感じているあなたへ
ストレッチや筋トレを試しても改善しない場合、根本的な原因が姿勢のゆがみ・骨盤のズレ・筋肉のアンバランスなど、セルフケアだけでは解決しにくいものにあることも少なくありません。
私の整体院では、股関節の痛みの背景にある骨格の動き方や筋肉の使い方のクセを細かくチェックし、お一人おひとりに合った施術とアドバイスをご提供しています。慢性的な不調でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
関連➤股関節の歪みや姿勢を整えたい方は、こちらの記事もどうぞ
\立ち仕事で股関節の痛みがある人は身体のメンテナンスをしませんか?/
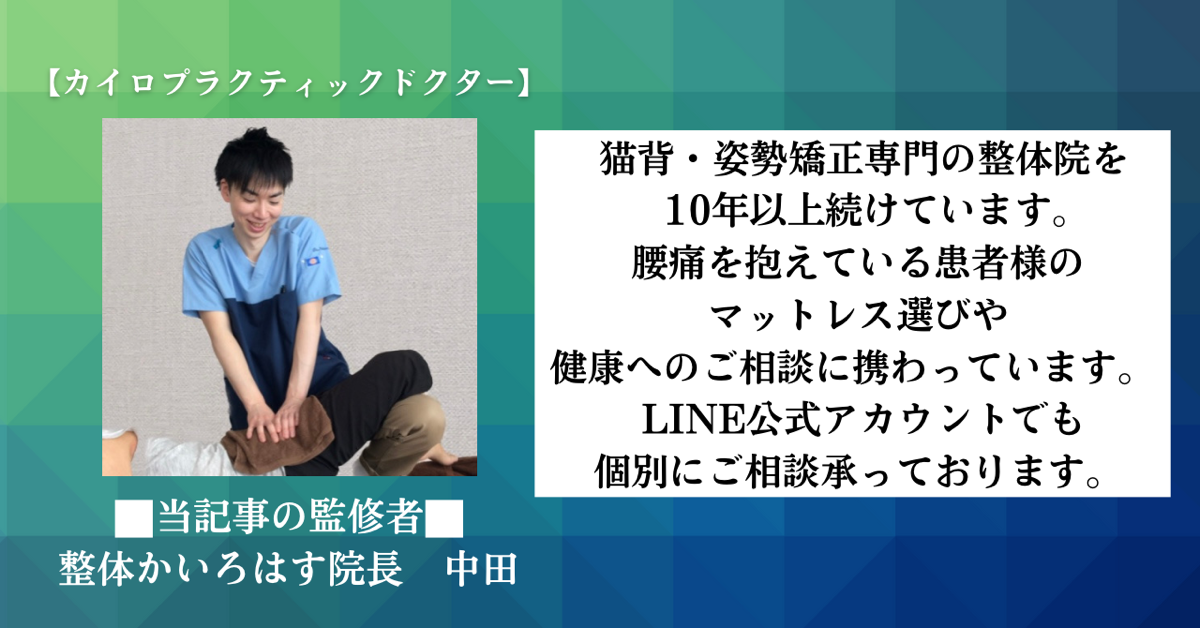
ページコンテンツ
股関節が痛くなる原因は「立ちっぱなし」かも?

- 長時間の立ち姿勢で筋肉が固まりやすい
- 片足重心や姿勢の崩れが股関節に負担
- 骨盤のゆがみが痛みを引き起こすことも
長時間立っていると、筋肉が縮んで固まる
立ち仕事が続くと、太ももやお尻、股関節まわりの筋肉が硬直しやすくなります。これは、同じ姿勢を維持し続けることで、筋肉が収縮したまま血流が悪化してしまうためです。特に、股関節の前側(腸腰筋)や内もも(内転筋)、お尻の筋肉(中殿筋)などが緊張しやすくなり、動かしにくさや痛みへとつながっていきます。
こうした筋肉のこわばりは、歩き出しや階段の上り下りの際に「足のつけ根が引っかかる感じ」「歩き方がぎこちない」といった違和感となって現れます。最初は軽いハリや違和感でも、慢性化すると痛みに変わることもあるため注意が必要です。
無意識の「片足重心」が股関節に負担をかける
立ち仕事中、知らず知らずのうちに片足に体重をかけて立っていることはありませんか? これは日常的なクセのひとつですが、長時間の偏った重心姿勢は、股関節への負担が左右で偏る原因になります。
その結果、片側だけ股関節が痛い・片足だけ疲れる・スカートが回りやすいなど、左右差のある不調が出やすくなります。骨盤も引っ張られて傾くため、結果的に姿勢全体がゆがみやすくなり、腰痛や膝痛にも波及する恐れがあるのです。
骨盤のゆがみが股関節の動きを制限する
骨盤が前に傾いたり、ねじれてゆがんでいる状態だと、その影響を最も受けるのが股関節の動きです。骨盤と太ももの骨(大腿骨)のつなぎ目にズレが生じることで、関節がうまくかみ合わず、動きがぎこちなくなります。
「足を開くと痛い」「靴下が履きにくい」「股関節がゴリゴリ鳴る」といった症状があれば、関節の可動域が狭くなっている可能性があります。こうしたサインは、早めに気づき対処することが大切です。
このように、立ちっぱなしの姿勢は想像以上に股関節や骨盤にストレスを与えている状態です。痛みや不調は突然起こるものではなく、日々の姿勢やクセの積み重ねによって少しずつ表れてきます。
「何となく違和感がある」という段階から、毎日のセルフケアを始めてみましょう。
\立ち仕事で股関節の痛みがある人は身体のメンテナンスをしませんか?/
立ち仕事で股関節が痛くなる理由と放置のリスク
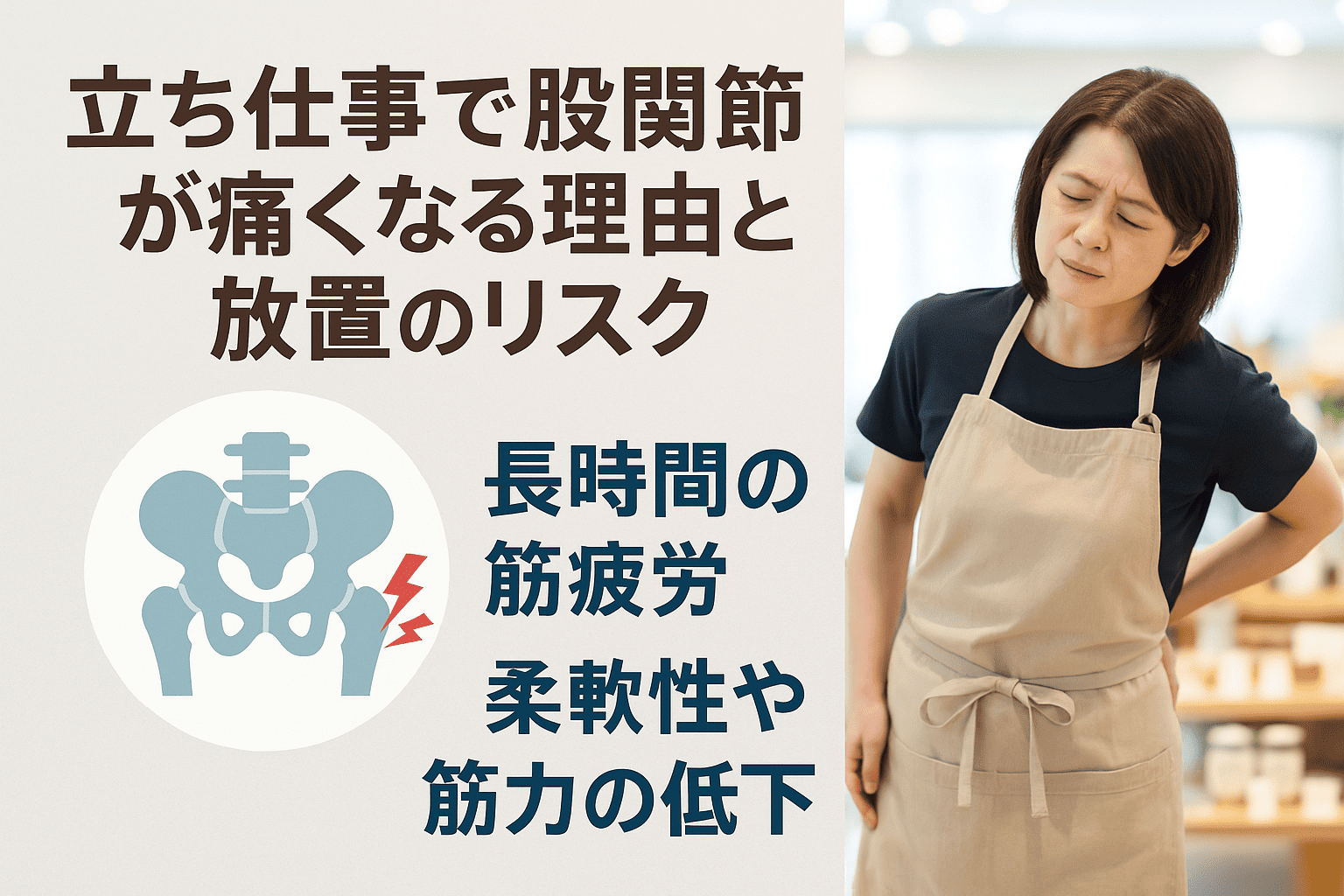
姿勢の崩れや筋力低下が痛みの引き金に 放置すると股関節だけでなく膝・腰にも影響 早期対策が将来の体づくりにも重要
姿勢の崩れと筋力の低下が痛みを招く
立ち仕事では、長時間にわたり同じ姿勢を維持し続けることが多くなります。この状態が続くと、筋肉や関節にかかる負担が一方向に集中しやすくなり、特に股関節まわりでは筋肉のアンバランスや動きの偏りが生じやすくなります。
また、仕事に集中するあまり、背中が丸まりやすくなったり、骨盤が後傾することで、本来股関節で受けるべき衝撃を腰や膝に分散してしまうケースも少なくありません。これが続くと、一見関係のなさそうな部位にも連鎖的な不調が波及していくのです。
放っておくと痛みが広がっていく
「今日はちょっと足のつけ根が痛いな…」
「でも、しばらくすれば治るから大丈夫」
そんなふうに小さな違和感を放置していると、症状は徐々に慢性化し、悪化していきます。
特に注意が必要なのは、痛みをかばって歩き方が変わること。股関節が痛いからといって無意識に庇って歩くと、今度は反対側の膝や腰に負担がかかってしまい、新たな痛みを引き起こします。こうした悪循環は、時間の経過とともに体全体のバランスを崩す原因になります。
また、股関節の可動域が狭くなると、日常の動作(しゃがむ・歩く・階段の上り下り)にも支障が出てくるため、日常生活の質(QOL)にも影響を及ぼすようになります。
将来の体のために「今」から対策を
股関節は、体重を支える非常に重要な関節です。だからこそ、痛みや違和感があるうちに対策を講じることが、将来的な歩行障害や関節疾患の予防にもつながります。
特に40代以降は、女性ホルモンの影響などで骨や筋肉の状態が変化しやすくなる時期です。そのため、「歳のせいかな…」とあきらめず、早いうちから柔軟性や筋力を保つケアを習慣にしておくことが大切です。
「まだ動けるから大丈夫」と思っていても、体の中では少しずつ負担が積み重なっていきます。違和感を感じたら、それは体からのSOSサイン。
しっかり耳を傾けて、早めのケアを始めましょう。
\立ち仕事で股関節の痛みがある人は身体のメンテナンスをしませんか?/
整体師おすすめ!股関節の痛みに効くストレッチ5選

ストレッチは「筋肉の柔軟性」を取り戻すカギ
股関節まわりのストレッチは、硬くなった筋肉をやわらかくし、関節の動きをスムーズに保つために重要です。
特に立ち仕事のあとに行うことで、疲労物質の蓄積を減らし、血流を改善する効果が期待できます。
ここでは、整体師の私が現場で多くの女性にすすめている、簡単で続けやすいストレッチを5つご紹介します。
① 開脚ストレッチ(内もも・骨盤の柔軟性アップ)
足を開いた状態で座り、上体を前に倒すストレッチです。内ももの筋肉(内転筋)を伸ばすことで、骨盤の動きを柔らかくし、足の動きも軽くなります。
ポイントは「背中を丸めず、おへそを床に近づけるイメージ」。呼吸を止めずに、20秒~30秒を1セット行いましょう。
② ワイパーストレッチ(股関節の可動域を広げる)
仰向けに寝て、膝を立てて左右にパタンパタンと倒す動きです。車のワイパーのような動きから名づけられています。股関節の回旋可動域を高め、股関節のつまり感を緩和します。
寝たままでできるので、寝る前のリラックスタイムにもおすすめです。
③ 腸腰筋ストレッチ(足のつけ根の張り解消に)
片膝をついた状態で、もう片方の足を前に出し、体を前に押し出していきます。足のつけ根がグーッと伸びるのを感じたらOK。
これは、立ち姿勢で縮みやすい「腸腰筋」を伸ばすストレッチで、腰痛予防にもつながります。
ヒールを履く女性や、反り腰気味の方には特におすすめです。
④ 寝ながらお尻ストレッチ(中殿筋のリリース)
仰向けで片足を反対側にクロスして倒し、お尻の外側(中殿筋)をじっくり伸ばします。
この筋肉は股関節の安定性に関わる重要な部分で、硬くなると足を引きずるような歩き方になりがちです。
ゆっくりと呼吸をしながら、左右30秒ずつを目安に行いましょう。
⑤ 椅子を使ったもも裏ストレッチ(ハムストリングスの柔軟性)
椅子に浅く腰掛け、片足を前に伸ばしてつま先を上に向けます。その状態で背筋を伸ばしながら前傾姿勢をとると、太ももの裏側(ハムストリングス)が心地よく伸びます。
立ち仕事後のクールダウンとしてぴったりで、疲労感の解消にも役立ちます。
これらのストレッチは、1日1~2種目でもOK!「続けること」が何より大切です。
体がほぐれてくると、股関節だけでなく姿勢や歩き方も軽やかに変わっていきますよ。
\立ち仕事で股関節の痛みがある人は身体のメンテナンスをしませんか?/
立ち仕事女性に合う股関節まわりの筋トレ3選

股関節の安定性を高める筋トレを厳選紹介 ストレッチと筋トレを組み合わせて相乗効果 自宅でできる簡単な内容なので初心者でも安心
筋トレの目的は「関節を支える力」をつけること
ストレッチで柔軟性を高めるのは大切ですが、それだけでは不十分。
関節を正しく支える「筋力」も同時に養うことで、痛みの出にくい体が作られていきます。
とくに股関節まわりは、骨盤・太もも・お尻と連動して動く複雑な構造。それらを支える筋肉が弱っていると、関節に余計な負担がかかってしまい、不調を引き起こします。
ここでは、立ち仕事女性におすすめの負担の少ない股関節筋トレを3つ厳選してご紹介します。
① ヒップリフト(お尻の筋肉を鍛えて股関節安定)
仰向けに寝て膝を立て、お尻を持ち上げるヒップリフト。お尻の大きな筋肉(大殿筋)や太ももの裏(ハムストリングス)を鍛えることで、骨盤の安定性が向上し、股関節への負担が減少します。
10〜15回を1セットとして、ゆっくり行うのがコツ。腰ではなくお尻を使う意識を持ちましょう。
② クラムシェル(中殿筋を鍛えて横ぶれを防止)
横向きに寝て、膝を軽く曲げた状態から上の膝だけをパカッと開く動作です。中殿筋(お尻の外側)を鍛えることができ、立ち姿勢でのブレやぐらつきを防ぐのに効果的です。
こちらも10〜15回を目安に。ゴムバンドを使うと負荷アップにも対応できます。
③ 内転筋リフト(太ももの内側を強化)
仰向けに寝た状態で、片足を立てたままもう片方の足をまっすぐ持ち上げます。これは太ももの内側の筋肉(内転筋)に効くトレーニングで、骨盤のゆがみ防止や姿勢の安定化に貢献します。
足を上げ下げする時は、勢いをつけずにコントロールしながらゆっくりと行うのがポイントです。
続けるコツは「短時間・低負荷・毎日少しずつ」
筋トレは「きつい」「ハード」というイメージがあるかもしれませんが、股関節ケアの場合は“軽めに毎日”が基本です。
回数や負荷よりも、正しいフォームで動かすことの方がずっと重要。
お風呂あがりや寝る前の習慣として取り入れて、少しずつ「筋肉を使う感覚」に慣れていきましょう。デスクワーク中の筋力低下が気になる方にはこちら。
\立ち仕事で股関節の痛みがある人は身体のメンテナンスをしませんか?/
筋トレとストレッチの組み合わせが大事な理由

片方だけでは改善しないこともある 両方やることで血流と筋力を同時に高められる 継続しやすい工夫もあわせて紹介
ストレッチだけ・筋トレだけでは不十分なことも
「ストレッチでほぐしているのに痛みが取れない…」
「筋トレしてるのに改善されない…」
そう感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
実は、ストレッチと筋トレはセットで行うことで本来の効果を発揮します。
ストレッチで筋肉をゆるめて柔軟性を高めることはもちろん大切ですが、それだけでは関節を支える力が足りないことも。また逆に、筋トレだけをしても、筋肉がガチガチに固まってしまって動きが悪くなることがあります。
両方組み合わせることで動きやすい体に
筋トレとストレッチをバランスよく行うことで、股関節まわりの筋肉が柔らかくて強い状態になります。
柔軟性だけでなく、可動域の中で安定して動かせる力が備わることが、痛みの出にくい身体づくりには欠かせません。
たとえば、ストレッチで腸腰筋をほぐし、そのあとにヒップリフトでお尻を鍛えるような流れがおすすめです。
この順番で行うことで、「動かしやすくなった筋肉をそのまま鍛える」ことができ、より効果的に体を整えることができます。
続けやすい工夫で習慣化するのが成功のカギ
どちらも大切とわかっていても、**忙しい日々の中で続けるのは難しい…**と感じてしまうこともありますよね。
そんなときは、1日1種目ずつ交互にやるだけでもOK!
たとえば、月・水・金はストレッチ、火・木・土は筋トレといった具合に、無理のないペースで取り入れるだけでも体は変わっていきます。
また、テレビを見ながらや寝る前の5分間など、日常生活の中に組み込む習慣化が成功のポイント。
とにかく「やらなきゃ」ではなく「ついでにやっておこう」くらいの感覚で始めるのが長続きの秘訣です。
ストレッチと筋トレは、まさに表と裏のような関係。
両方をバランスよく取り入れることで、股関節の痛みを予防し、しなやかで安定した身体が作られていきますよ。
\立ち仕事で股関節の痛みがある人は身体のメンテナンスをしませんか?/
運動以外にもできる!股関節ケアの生活習慣
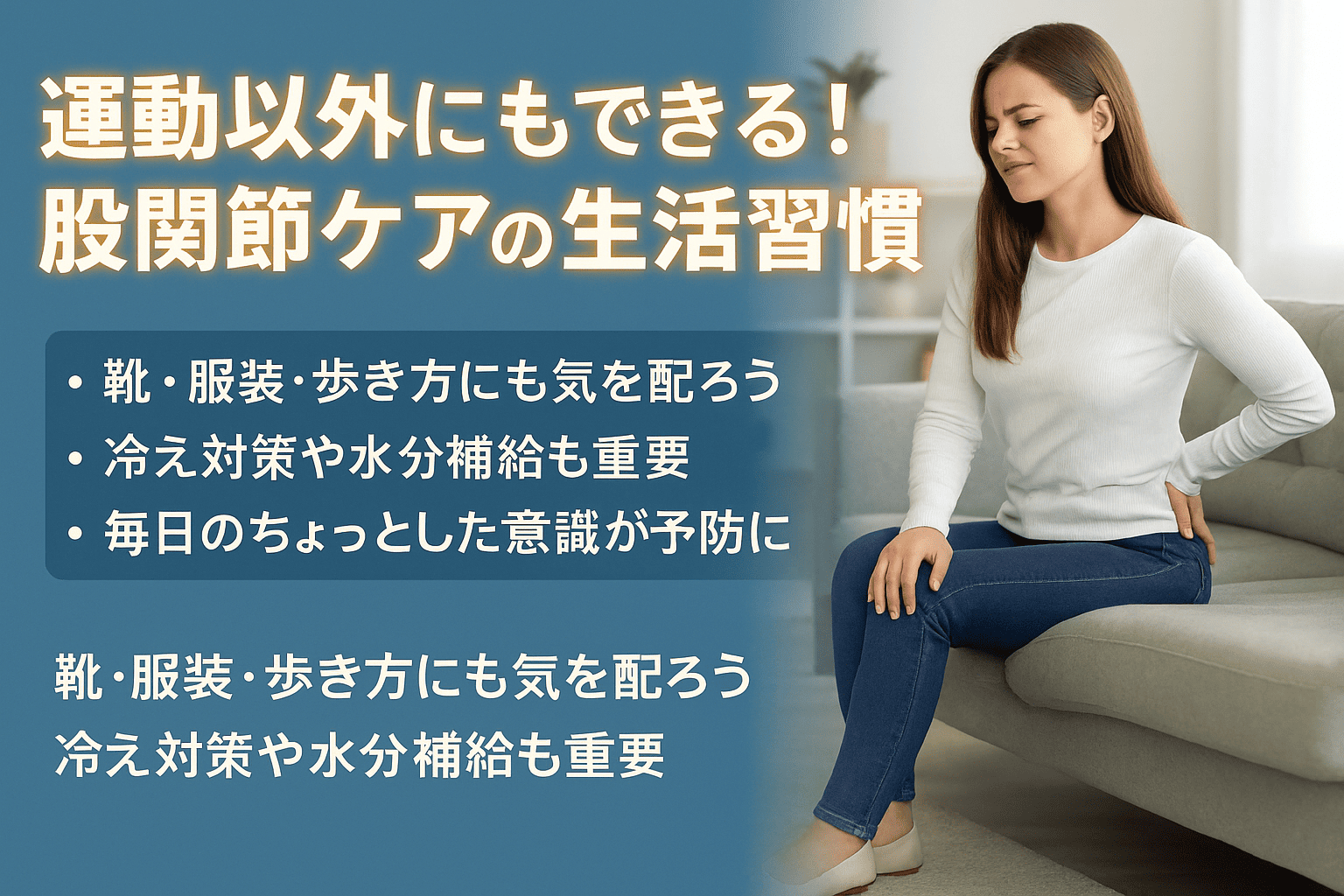
日常の歩き方や姿勢が痛みの原因になることも 靴・服装・座り方など小さな習慣が大切 生活習慣の見直しでケア効果が倍増
靴の選び方ひとつで負担が変わる
意外と見落とされがちなのが「靴の影響」。ヒールが高すぎる靴や、クッション性のないペタンコ靴を履いていると、股関節にかかる衝撃がそのまま伝わってしまいます。
足に合っていない靴を長時間履いていると、歩き方が乱れ、股関節〜膝〜腰にかけてゆがみが起きやすくなるため、毎日使う靴こそ慎重に選ぶ必要があります。
おすすめは、クッション性があり、つま先とかかとに程よく厚みのあるスニーカータイプ。仕事柄ヒールが必要な方は、帰宅後のセルフケアをしっかり行うようにしましょう。
座り方や立ち方に要注意
座るとき、無意識に「足を組む」クセがある方は要注意。これは骨盤のゆがみを引き起こし、結果的に股関節の動きにも影響を与えることがあります。
また、立っているときに片足重心になったり、どちらか一方に体を傾けるクセがあると、股関節の片側だけに過剰な負担がかかってしまうことも。
こうした日常の姿勢は、積み重なることで痛みや不調の原因になります。「左右均等に立つ・骨盤を立てて座る」という意識を持つだけでも、大きな予防効果があります。
水分不足や冷えにも注意
股関節まわりの筋肉や関節は、血流や体温の影響を強く受けます。
水分が不足すると筋肉が硬くなりやすく、冷えによって血流が悪化することで関節の動きがぎこちなくなってしまうことも。
特に女性は冷えやすい体質の方が多く、冷房の効いた室内に長時間いると知らずに体が冷えてしまうこともあります。レッグウォーマーやブランケットなどで股関節まわりを冷やさない工夫も大切です。
「ちょっとした意識」が積み重なると差になる
股関節のケアというと、「運動しなきゃ」「ストレッチしなきゃ」と思いがちですが、実はこうした生活の中のちょっとした行動の積み重ねが大切です。
-
靴を見直す
-
座り方を整える
-
水分を意識的にとる
-
股関節を冷やさない工夫をする
こうした意識を日々持つことで、自然と股関節に優しい生活が身についていきます。
「ストレッチも筋トレも苦手…」という方でも、こうした習慣の改善だけでも痛みの予防や軽減に十分つながります。
まずは今日からひとつだけでも意識してみてくださいね。
\立ち仕事で股関節の痛みがある人は身体のメンテナンスをしませんか?/
それでも股関節の痛みが取れないときは?
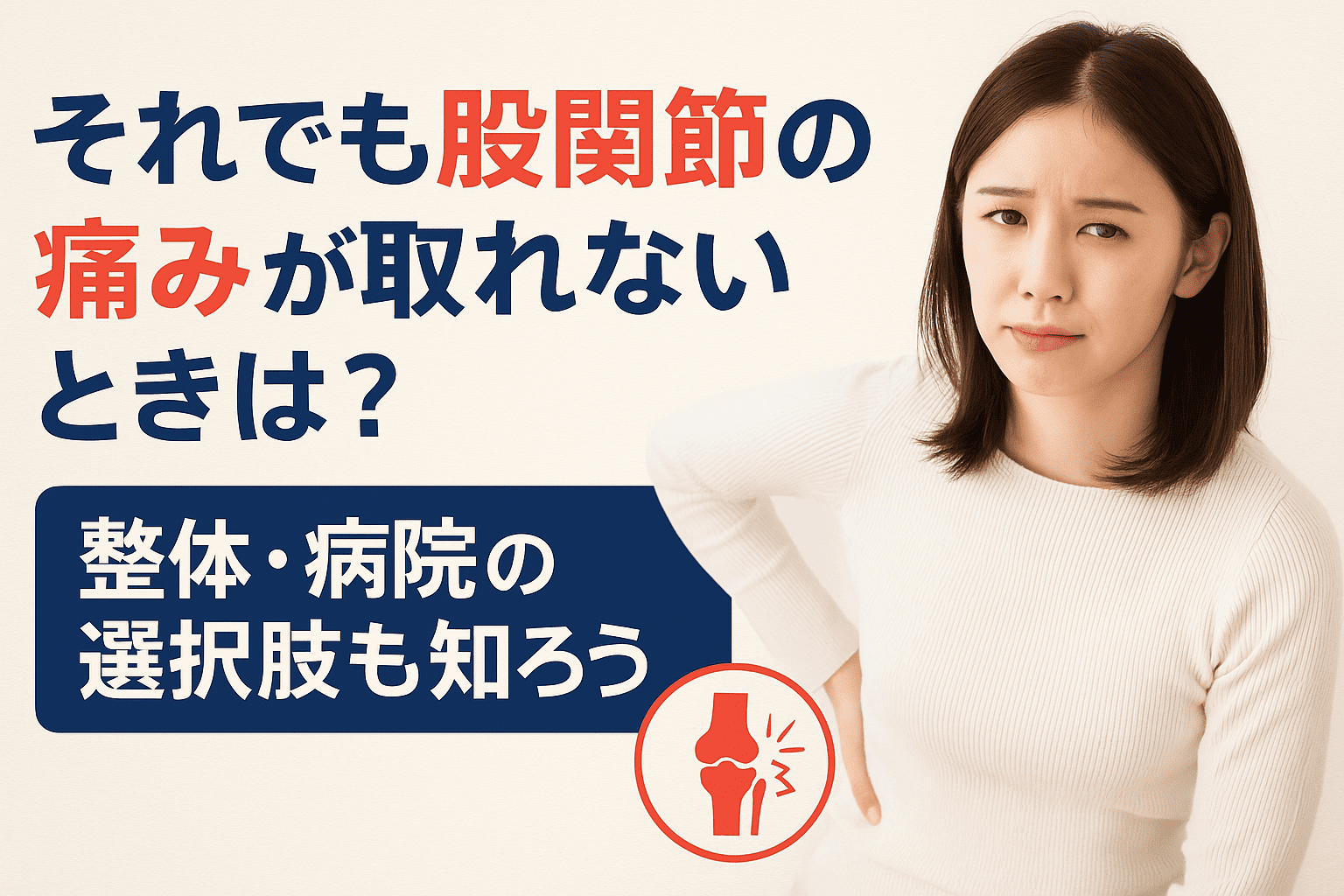
セルフケアで改善しない場合の対処法 整体と病院の違い・使い分けを解説 プロに頼ることで早期回復につながることも
セルフケアで変化がなければ「体の使い方のクセ」が原因かも
毎日ストレッチや筋トレを頑張っているのに、なかなか痛みが取れない・改善を感じない。
そんなときは、体の使い方や動作のクセが深く関係している可能性があります。
例えば、歩き方・立ち方・骨盤の動き方など、日常の何気ない習慣の中に痛みの根本原因が隠れていることもあります。こうしたクセは自分ではなかなか気づけないため、専門家の視点で体をチェックしてもらうことが大切です。
関連➤整体を受ける前に読んでおきたい「整体 vs 病院の違い」
病院と整体の違いって? どう使い分ければいい?
股関節に痛みがあると「病院に行くべきか」「整体に行ってもいいのか」迷う方も多いのではないでしょうか。
まず、以下のようなケースでは病院(整形外科)を受診するのが基本です。
-
痛みが鋭く、じっとしていても辛い
-
関節が変形している、歩行が困難
-
発熱や腫れ、赤みなどがある
一方で、慢性的な痛みや違和感、姿勢の歪みが関係していそうな場合は整体がおすすめです。
整体では、関節や筋肉の動き、骨盤のバランスなどを細かくチェックし、痛みの原因を根本から見直す施術を行うことができます。
整体を活用するメリットと通う目安
整体のよいところは、「痛みが出る前の段階」や「軽い違和感のうち」にケアを始められること。
特に股関節の不調は、姿勢や筋肉のアンバランスに起因するケースが多いため、整体との相性が非常に良い部位でもあります。
通院の頻度は、痛みの程度や生活習慣にもよりますが、最初のうちは週1回ペースで3〜4回を目安に通うことで体の変化を実感しやすくなります。そこからは状態に応じて、2週に1回や月1回のメンテナンスに移行していくのが理想です。
自分の体を「知る」ことが早期回復への第一歩
「整体に行くのはちょっと勇気がいる…」という方もいらっしゃると思いますが、自分の体がどう歪んでいて、どこに負担がかかっているのかを知ることは、今後のセルフケアにとっても非常に大きなヒントになります。
一度専門家に見てもらうことで、間違った動きやクセを修正しやすくなり、結果的に早く楽になるケースも多いんです。
ストレッチや筋トレをしても変化がないと感じたら、自分の体の状態を見直すチャンス。
必要に応じて整体や専門機関も上手に活用して、長く動ける体づくりを一緒に目指していきましょう!
\立ち仕事で股関節の痛みがある人は身体のメンテナンスをしませんか?/