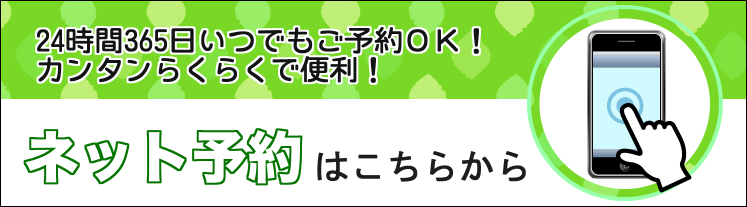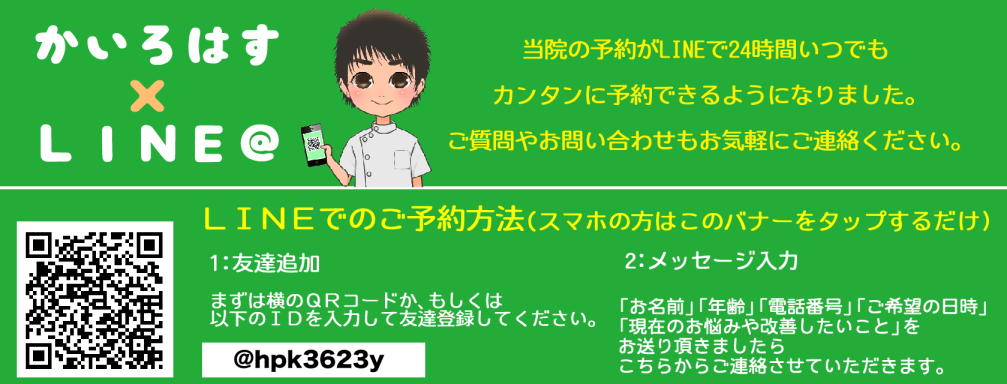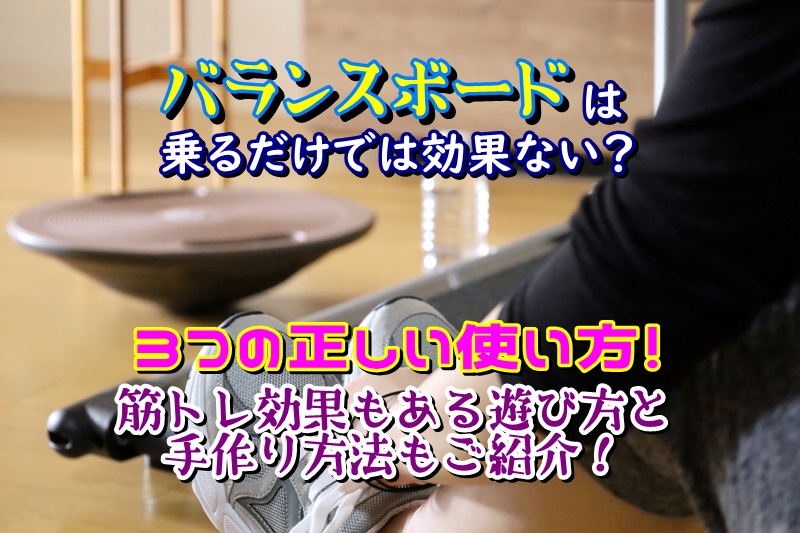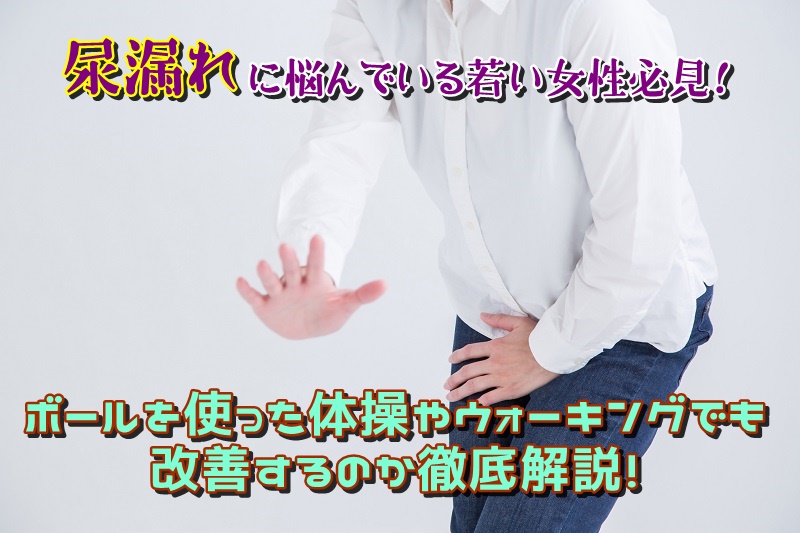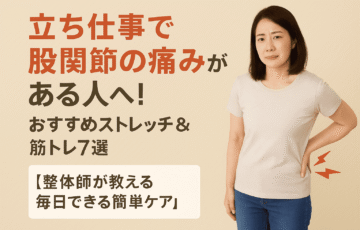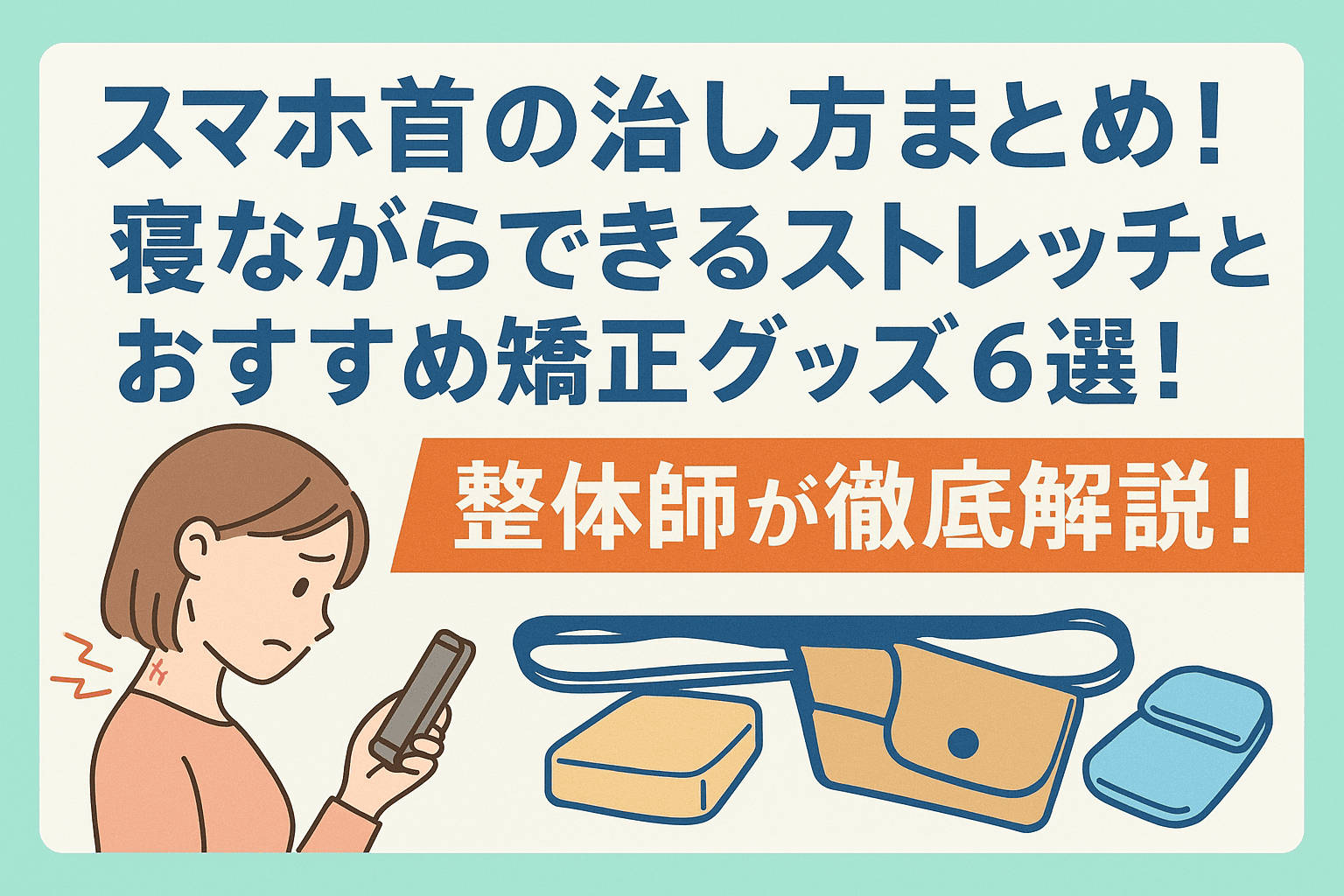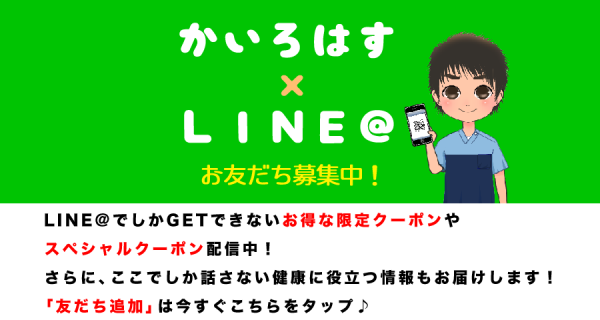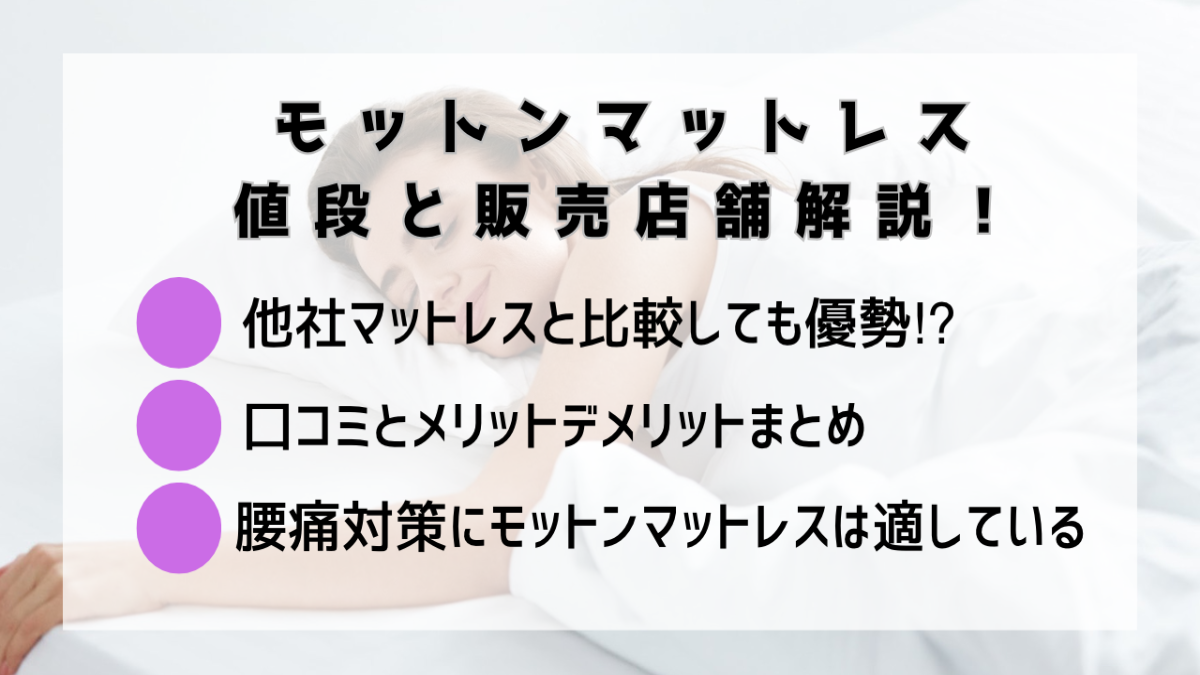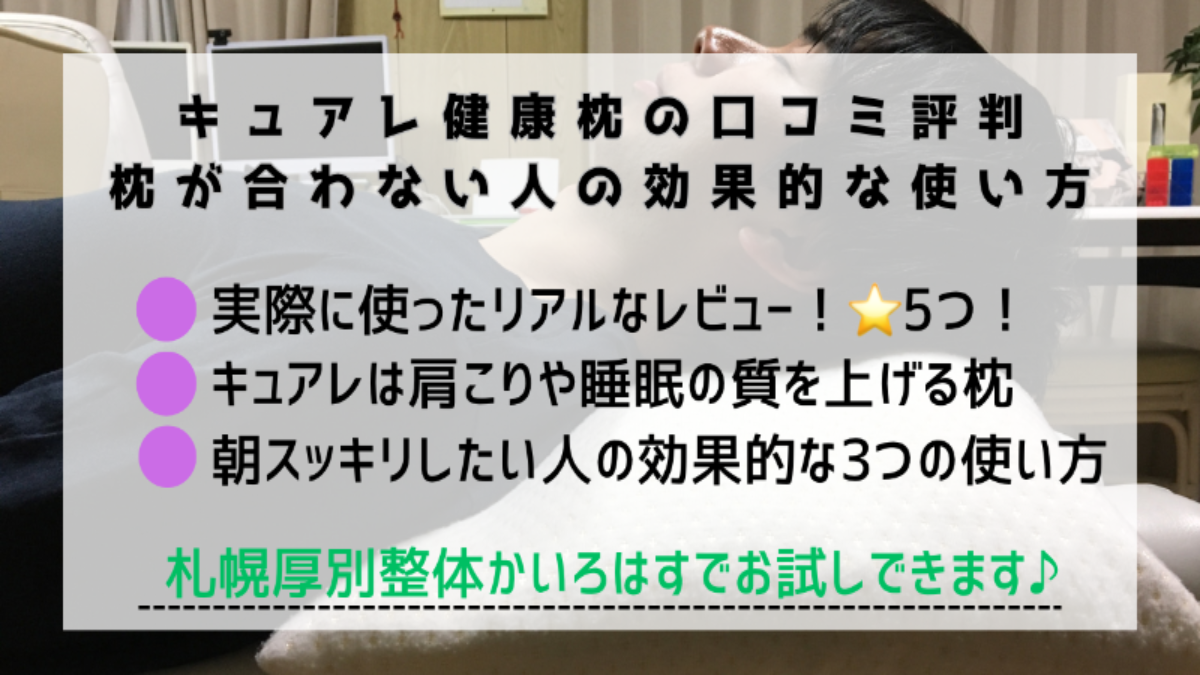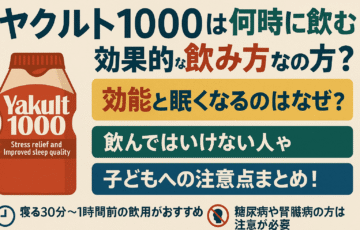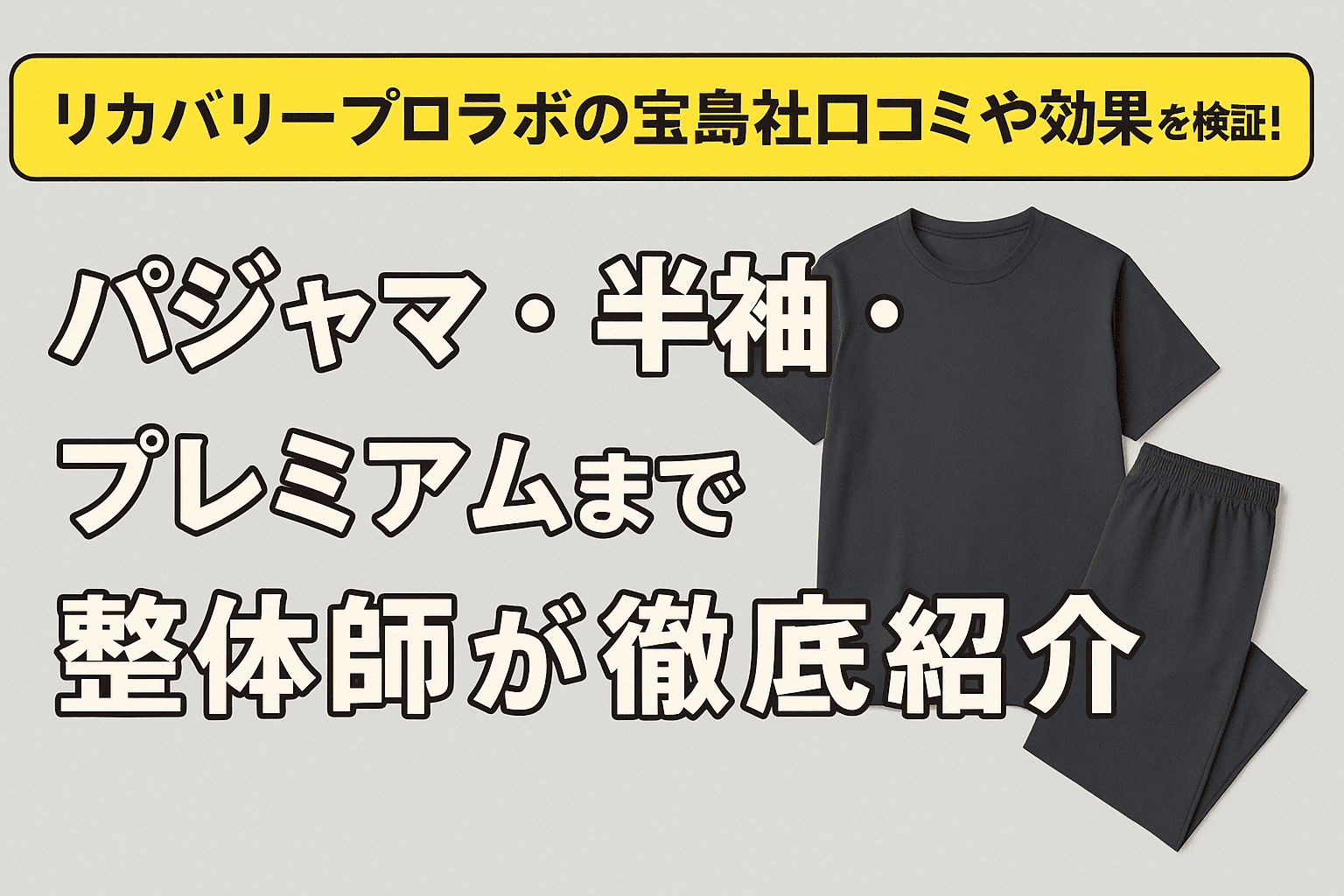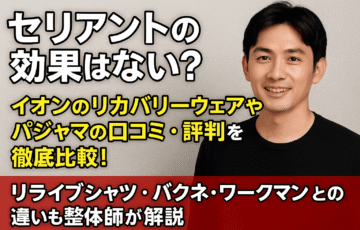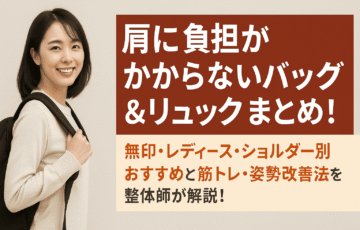「腕が後ろに回らない」「服を脱ぐときに肩がズキッとする」「夜中に肩の痛みで目が覚めてしまう」
そんな症状に心当たりがある方は、五十肩(正式名称:肩関節周囲炎)かもしれません。
五十肩は40代後半〜50代にかけて多く見られ、肩まわりの筋肉や関節が硬くなり、肩を自由に動かせなくなる状態です。
とくに「後ろに手が回らない」「背中に手が届かない」といった制限は日常生活に大きな支障をきたし、下着の着脱・髪を結ぶ・エプロンの紐を結ぶ・トイレで衣類を整えるといった動作が苦痛になります。
しかもこの症状、片方の肩だけに現れることが多く、利き手に出ると仕事にも家事にも大きな影響が出るため、多くの方が悩みを深めてしまいます。
さらにやっかいなのが、肩だけでなく「肘・手首・背中・腕全体」まで痛みが広がるケース。
これは「関連痛」と呼ばれ、炎症や神経の影響によって、痛む場所が肩から離れているように感じる現象です。
また、「夜間痛」によって眠れない・目が覚める・寝返りが打てないといった二次的な悩みを抱えている方も多くいらっしゃいます。
「五十肩を一瞬で治す方法ってある?」「マッサージしたら治る?」「バンテリンやサポーターは使っていいの?」
こうした疑問を持ち、ネットやSNSで情報を探しながらも、自己流のケアで症状を悪化させてしまう人も少なくありません。
そこで本記事では、整体師の視点から以下のようなテーマを丁寧に解説していきます。
✅ 五十肩で後ろに手が回らない原因と癒着・拘縮の関係
✅ 急性期の注意点と“温める場所”の正しい知識
✅ 自宅で安全にできる「寝ながらストレッチ」
✅ 肩に関係する「手足のツボ」への刺激方法
✅ サポーター・バンテリン・サプリの正しい使い方
✅ 痛みがいつまで続くのか、寝れない夜への対策
✅ 肘まで痛い・片方だけの症状が出たときの考え方
五十肩は“焦らず・痛みを悪化させずに動かす”ことが回復の鍵です。
この記事を通じて、あなたに合った正しいセルフケアと整体的アプローチを知っていただければと思います。
札幌市厚別区の「かいろはす整体院」では、癒着や可動域のチェックをもとに、あなたに合ったやさしいケアを提供しています。
肩の痛み・不自由さが長引いている方は、ぜひ一度ご相談ください。
\五十肩は正しくケアすれば改善できます!/
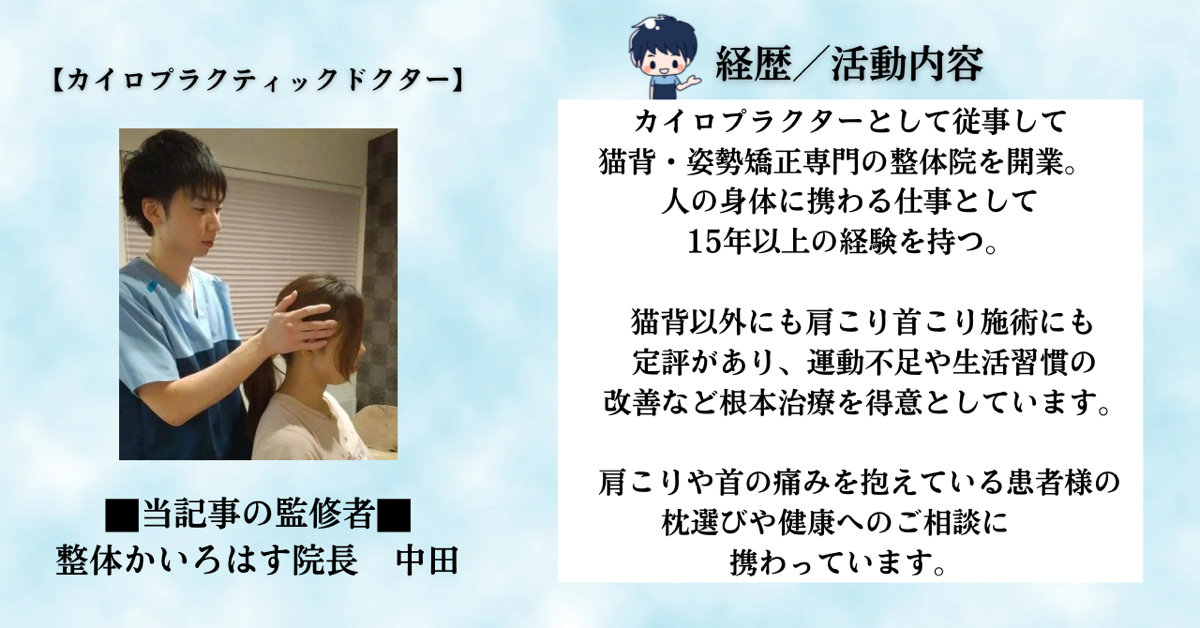
ページコンテンツ
- 1 五十肩で後ろに手が回らないのはなぜ?癒着や拘縮の仕組みと急性期の注意点
- 2 五十肩を一瞬で治す方法はある?整体師が教える本当のケアとNGマッサージ
- 3 寝ながらできる!五十肩ストレッチで可動域を広げるおすすめ3選
- 4 五十肩に効くツボ刺激とは?手と足から肩をゆるめるセルフケア
- 5 サポーターやバンテリンは効果ある?アイテム活用の正しい方法
- 6 五十肩はどこが痛む?肩だけじゃない「痛みの場所」の違いと理由
- 7 五十肩の痛みはいつまで続く?改善までの期間とやるべきこと
- 8 五十肩を“早く治したい人”がやりがちな間違い5選!整体師が見たNG例
- 9 五十肩は片方だけ?反対側も痛くなる理由と再発リスク
- 10 五十肩の本当の原因は肩以外?肘・背中・骨盤から整える整体的アプローチ
- 11 まとめ|五十肩の痛みは“体のサイン”。焦らずじっくり向き合おう
五十肩で後ろに手が回らないのはなぜ?癒着や拘縮の仕組みと急性期の注意点
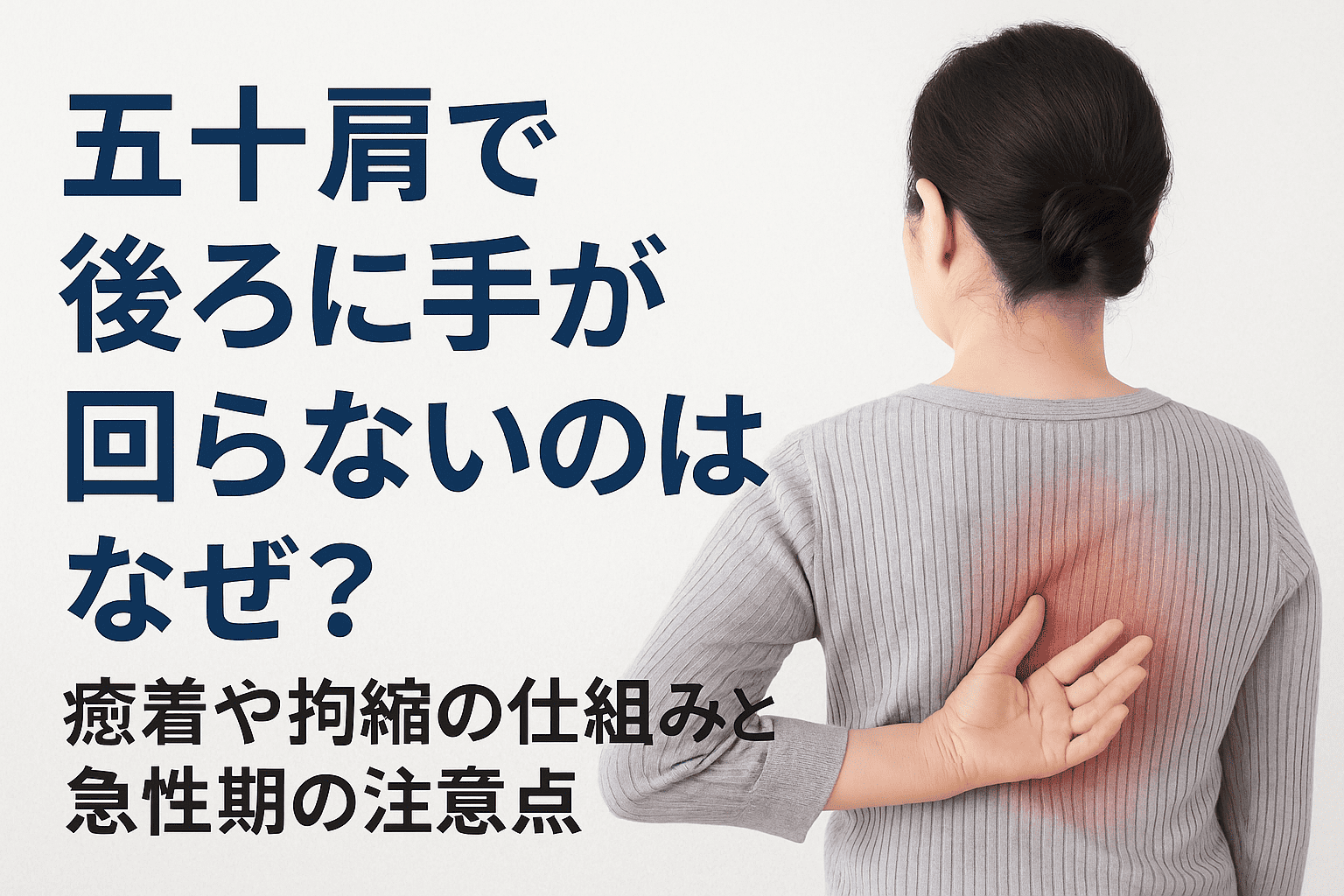
-
腕を後ろに回す動作ができない理由は「関節の癒着」と「拘縮」
-
肩の炎症がピークになる「急性期」は無理に動かさないのが正解
-
姿勢や肩甲骨の動きも関係しているため、全身のバランスも要チェック
「エプロンの紐が結べない」「背中のファスナーに手が届かない」――
五十肩の症状で多いのが、腕を後ろに回せなくなる可動域制限です。
この状態を引き起こす主な原因が、「癒着(ゆちゃく)」と「拘縮(こうしゅく)」です。
癒着とは、肩関節周囲の組織が炎症によって硬く結びつき、滑らかな動きができなくなる状態。
そして拘縮とは、筋肉や関節の動き自体が制限され、柔軟性が失われている状態を指します。
これらが組み合わさることで、「腕を上げる・ひねる・回す」といった動作が極端に制限されてしまうのです。
五十肩は、発症から回復までに以下の3つの時期を経ます。
-
急性期(炎症期)
-
拘縮期(凍結期)
-
回復期(解凍期)
このうち「急性期」こそ最も注意が必要な期間です。
炎症によって肩の中で腫れや熱感が生じ、ズキズキとした鋭い痛みを伴います。
この時期に無理に動かしたり、強いマッサージを受けると、炎症が悪化し、癒着がさらに進行する恐れがあります。
基本的には安静が望ましいのですが、「まったく動かさない」と筋肉が固まり、拘縮が進んでしまう可能性も。
そのため、痛みが出ない範囲での軽い可動域運動や、温めるケアの導入が有効です。
肩だけじゃない!「肩甲骨まわり」や「背骨の柔軟性」も影響
実は「腕が後ろに回らない」という状態は、肩関節だけの問題とは限りません。
日常的に猫背になっていたり、肩甲骨が動かしづらくなっていたりすることで、肩の可動域が制限されるケースも多く見られます。
とくにデスクワーク中心の方や、姿勢が前傾気味の方は要注意。
姿勢の崩れや筋バランスの乱れが、肩関節に余計な負荷をかけ、炎症や癒着を助長してしまうのです。
急性期を過ぎたら、少しずつ肩甲骨を動かすようなストレッチや体操を取り入れることで、拘縮の悪化を防ぎやすくなります。
温める場所はどこ?五十肩ケアの基本
急性期を過ぎたあとは、「温める場所」にも注意が必要です。
おすすめは、肩だけでなく「肩甲骨まわり」や「首まわり」も同時に温めること。
血流が促進されることで、硬くなった組織が少しずつ緩み、痛みや動きの制限が和らぎやすくなります。
ただし、炎症が残っている場合や、ズキズキと痛む場合は冷却が適していることもあるため、自身の状態にあわせた判断が重要です。
\五十肩の初期対応を間違えると長引くリスクも!/
五十肩を一瞬で治す方法はある?整体師が教える本当のケアとNGマッサージ
-
SNSでよく見る「一瞬で治る方法」は本当?
-
痛みがある時にやってはいけない自己流マッサージとは?
-
整体師が伝える“早く楽になる”現実的なアプローチを解説!
❌一瞬で治す方法は基本的に存在しない!その理由とは?
YouTubeやSNS、ブログなどでよく見かける「五十肩を一瞬で治すストレッチ」「1回で改善!魔法のマッサージ」などの動画や記事。
ついつい気になって試してしまいたくなる気持ち、よくわかります。
ですが、実際の五十肩は「癒着・炎症・拘縮」の段階が複雑に絡み合っている状態であり、
痛みが強い急性期に強引なストレッチやマッサージを行うと、かえって悪化する可能性があります。
とくに後ろに手が回らないタイプの五十肩は、関節包の深部に硬さ(癒着)があるため、
表面的なマッサージや肩を強く引っ張るような動きでは根本改善にはつながらないのです。
➤肩の痛みを病院で診てもらう前に知っておきたいセルフチェック方法
🛑やってはいけないNGケア例
五十肩の急性期・拘縮期にありがちな誤ったセルフケアは以下の通りです。
-
痛みを無視して肩を後ろに引っ張るストレッチ
-
ゴリゴリと肩をもみほぐす強刺激のマッサージ
-
誰かに腕を無理に上げてもらう可動域運動
-
気合いで「動かせば治るはず」と毎日腕を振るトレーニング
これらはすべて、炎症を悪化させたり、癒着を深めたりしてしまう危険な行為です。
「一瞬で治したい」という焦りはとてもよくわかりますが、五十肩には“時期に合った対処”が不可欠です。
✅整体師が考える“早く良くなる”現実的なアプローチ
五十肩を最短で改善に導くには、以下のような段階的なアプローチが大切です。
-
急性期(ズキズキ痛い時):温める・安静・軽い振動や深呼吸などの緩和ケア
-
拘縮期(動かしづらくなる時):痛みの出ない範囲でのストレッチ・肩甲骨の可動域ケア
-
回復期(少しずつ動く時):本格的な可動域改善・セルフ体操・整体での調整サポート
このように時期に応じてアプローチを変えることが、結果的に早期改善への最短ルートとなります。
💡整体ではどんな施術をするの?
当院では、五十肩の方に対して以下のような施術を組み合わせています。
-
肩や肩甲骨まわりの可動域チェック
-
動かせる範囲を広げる軽いモビリゼーション
-
姿勢・骨盤・背中のバランス調整
-
自宅でできるストレッチ・生活指導の提案
大切なのは、「その方の今の状態」に合わせて、無理のない施術を段階的に行っていくことです。
\早く治したい方ほど、“焦らず正しい段階”がカギです!/
寝ながらできる!五十肩ストレッチで可動域を広げるおすすめ3選
-
痛みが強い人にもできる“寝ながら”ストレッチを紹介!
-
五十肩に合った安全な動き方とやってはいけないことも解説
-
継続しやすく“可動域改善”を目指す3つのセルフケア法
🌙寝ながらストレッチが有効な理由とは?
五十肩で肩を動かすのが怖い・痛い…という方におすすめしたいのが、寝ながら行えるストレッチです。
床やベッドに体を預けることで、筋肉の緊張がゆるみやすく、関節に負担がかかりにくいというメリットがあります。
特に、肩関節に“癒着”や“拘縮”が起こっている時期は、痛みの出ない範囲での小さな動きが最も効果的。
ここでは、私が整体の現場でもアドバイスしている「寝たままできるストレッチ」3選をご紹介します。
✅① 仰向けで両手バンザイ|肩甲骨をゆるめる簡単ストレッチ
-
仰向けで寝て、両膝を立てる(腰が反らないように)
-
息を吐きながら、痛みの出ない範囲でゆっくりと両手をバンザイのように上へあげる
-
ゆっくり戻す。10回ほど繰り返す
※片側だけ痛い方は、痛みのない方と“左右差”を感じるだけでも十分効果があります。
✅② 横向き寝で“下側の腕”を肩から前後にスライドさせる
-
横向きに寝て、痛くない方を下にする
-
下になった方の腕をゆっくり前→後ろとスライド
-
背中側に行きにくい時は無理せず、呼吸を深めながら小さく動かす
このストレッチは、後ろに手が回らない五十肩に特に効果的。
肩甲骨の動きをサポートする筋肉群(前鋸筋・小円筋など)にじわっとアプローチできます。
✅③ 寝たまま「肘まわし」運動でインナーマッスルを刺激
-
仰向けで肘を曲げ、手を肩に軽く添える
-
肘で円を描くように、ゆっくり外回し・内回し
-
1日10回×2セットを目安に
肩のインナーマッスル(特に棘上筋)を刺激し、関節の深層から可動域改善を促します。
肘まで痛い方は、小さな動きから始めることが大切です。
❗注意点|ストレッチで痛みが増すときは即中止!
-
「ズキン」と刺すような痛みが出たらすぐにストップ
-
呼吸を止めながら無理に伸ばすのはNG
-
温めてから行うと効果が高まりやすい(特に夜がおすすめ)
「効かせよう」と意識しすぎると、逆に炎症が悪化することもあるので要注意です。
あくまで「心地よく動かせる範囲でゆっくり行う」ことが、寝ながらストレッチのコツです。
\続けることで“少しずつ動く”を取り戻せます!/
五十肩に効くツボ刺激とは?手と足から肩をゆるめるセルフケア
-
五十肩はツボ刺激でもサポートできる!
-
手・足にある代表的なツボとその押し方を解説
-
安全なツボ刺激のコツや注意点も紹介します
🤲手のツボで肩の緊張をやわらげる
五十肩に悩む方は、「肩そのもの」を触って刺激しようとしがちですが、実は手のひらや指先のツボも肩まわりと深くつながっています。
特に以下のツボは、五十肩の緊張緩和に有効とされ、整体現場でもよく使用されています。
✅「合谷(ごうこく)」
-
場所:親指と人差し指の骨が交わるくぼみ
-
効果:肩・首・頭の緊張緩和、全身の巡りUP
-
押し方:やや強めに、息を吐きながら5秒押す×3セット
✅「肩井(けんせい)」※自分では届きづらいが、押すと痛気持ちいい
-
場所:首の付け根と肩先の中間(肩の中央付近)
-
効果:肩こりや肩の可動域制限に◎(人に押してもらうと効果大)
これらのツボは、毎日少しずつ刺激することで肩の可動域が回復しやすくなります。
🦶足裏のツボも侮れない!肩とつながる意外なゾーン
足には全身の臓器や筋肉に対応する“反射区”が集中しており、肩と関連するツボも存在します。
✅「肩の反射区」
-
場所:足の小指側、足の甲から側面にかけたエリア
-
方法:親指でグーッと圧をかけてから、指でさするように流す
✅「太衝(たいしょう)」
-
場所:足の甲、親指と人差し指の骨の間のくぼみ
-
効果:肝の巡り・自律神経・肩の緊張緩和にもつながる
ツボ押しに慣れていない方は、足湯や蒸しタオルで温めてから押すと、筋肉もゆるみやすくなります。
❗ツボ刺激の注意点|「痛いほど効く」はウソ!
-
強く押しすぎない(青あざや炎症の原因に)
-
食後・飲酒後・発熱時の刺激は避ける
-
気持ちよく「いた気持ちいい」と感じる範囲が理想
また、ツボ押しだけで治そうとせず、ストレッチや生活習慣の見直しと並行して行うことが大切です。
\毎日3分でも続ければ、カラダは変わります!/
サポーターやバンテリンは効果ある?アイテム活用の正しい方法
-
五十肩に市販アイテムは有効?
-
サポーターやバンテリンの使い方と注意点を解説!
-
使うタイミング・効果を最大化するコツとは?
🩹サポーターは五十肩の痛みを和らげる“サポート役”
五十肩に対して「サポーターって使っていいの?」と質問されることは非常に多いです。
結論から言えば、正しいタイミングと方法で使用すれば、負担軽減や保温にとても役立ちます。
ただし、サポーターは「治すための道具」というよりも、あくまで“補助”の役割です。
✅サポーターを使うのに適した場面
-
買い物や家事など、日常動作で痛みが出る時の負担軽減
-
肩の冷えがつらいときの保温・安定サポート
-
寝返りで肩を動かしてしまう方の夜間ケア
サポーターを選ぶときは、肩だけでなく腕全体を覆うタイプや伸縮性のある柔らかい素材を選ぶのがおすすめです。
💊バンテリンは炎症期に使ってもいい?
市販の塗り薬として有名な「バンテリン」も、**五十肩に使っていいのか?**という声をよく聞きます。
結論:急性期(痛みがズキズキする時期)には“冷感タイプ”、拘縮期・回復期には“温感タイプ”が推奨されます。
❄冷感タイプのバンテリンが向いている人
-
腫れているような感覚がある
-
肩の表面が熱っぽい
-
動かしてもいないのに痛む(炎症反応が強い)
♨温感タイプが向いている人
-
関節が硬くて動かしにくい
-
痛みよりも“張り感”や重だるさがある
-
可動域を少しでも広げたい時期
注意点としては、「塗ったらすぐ動かせるようになる」わけではないので、塗布後は数分〜10分程度安静にして、じんわり温まってからストレッチや運動を行うのが理想です。
🧼貼るタイプの湿布・塗るタイプの違いと使い分け
-
湿布(パップ剤・テープ剤):広範囲に貼れて便利。動きのある部位では剥がれやすいことも
-
塗るタイプ:手軽に使用可能。肩まわりの細かい凹凸にフィットしやすい
特にバンテリンのゲルタイプは関節や筋肉にしっかりなじむので、使いやすくおすすめです。
⚠間違った使い方に注意!
-
強く押し込むように塗らない(刺激過多で逆効果)
-
肌が弱い方はパッチテストをしてから使用
-
サポーターと併用する場合は、通気性や温感の持続時間を意識すること
\アイテムは“補助”として上手に使うのがコツ!/
五十肩はどこが痛む?肩だけじゃない「痛みの場所」の違いと理由
-
五十肩の痛みが出る“場所”は人によって異なる!
-
肩だけでなく肘・腕・手首・背中にも広がるケースあり
-
片方だけに出る理由と“関連痛”の仕組みを整体師が解説!
🔍「五十肩は肩だけが痛い」とは限らない
「五十肩」と聞くと「肩だけが痛くなる」と思われがちですが、実は多くの方が肩以外の部位にも痛みを感じています。
特に多いのが次のような場所です:
-
肩関節の外側や前側(腕を上げると痛い)
-
二の腕の中ほど(じんわり痛む・筋肉痛のような痛み)
-
肘まわり・手首(ズキッと走るような放散痛)
-
背中や肩甲骨まわり(重だるさ・張り感)
こうした広がる痛みは、「関連痛(かんれんつう)」と呼ばれる現象によるものです。
本来の原因が肩関節にあっても、神経や筋膜の影響で別の場所に“痛み”として現れることがあります。
🦴「肘まで痛い」「腕全体がだるい」は珍しくない症状
「五十肩なのに肘が痛い」「手までしびれるような違和感がある」という声は珍しくありません。
これは、肩の炎症や癒着により腕神経叢(わんしんけいそう)という神経の束に影響が出ているケースが多く、
とくに「首~肩~腕」へと連なる神経ラインが圧迫・過敏になると、肘や指先にまで痛みやしびれが及びます。
また、肩の動きが悪くなることで無意識に他の筋肉でカバーしようとする“代償動作”が起こり、
結果として「肩以外も痛くなってきた」という状態に陥りやすいのです。
🧍「片方だけ」に出るのはなぜ?利き手側に多い理由
五十肩は、ほとんどの場合「片側だけ」に発症します。
その原因は以下のような背景が考えられます。
-
利き手を使いすぎて肩に負担が集中していた
-
姿勢の歪み(片側ばかりに重心をかけるクセなど)
-
仕事や家事で片側だけ酷使する環境が続いた
また、五十肩になった側とは逆の肩にも数年後に出ることがあるというケースもあるため、
「片方だけだから大丈夫」と油断せず、反対側の肩も同時にケアしていくことが大切です。
💡整体師からのアドバイス:痛みの場所=原因とは限らない!
「肘が痛いから肘をマッサージする」「二の腕が痛いから筋トレする」といった局所的な対応だけでは逆効果になることも。
痛みが出ている場所は“結果”であり、“原因”は肩の深部にある可能性が高いからです。
整体では、以下のように全身のバランスを見てアプローチしていきます。
-
肩関節の可動域チェック
-
背骨・肩甲骨・骨盤の動きやねじれ確認
-
痛みの出る動作の癖や、かばい方の評価
\「痛む場所」だけじゃなく「原因の場所」も見直してみませんか?/
五十肩の痛みはいつまで続く?改善までの期間とやるべきこと
-
痛みのピークは「急性期」の数週間が多い
-
改善までの平均は6ヶ月~1年が目安
-
急がず“適切な段階的ケア”が早期改善のカギ!
五十肩の痛みは3つの時期で変化する
五十肩の痛みは、「急性期→拘縮期→回復期」と進行していきます。それぞれの特徴を知っておくことで、不安なく対応できるようになります。
① 急性期(発症~1ヶ月ほど)
強い痛みと炎症が起こり、夜間のズキズキとした痛みがつらい時期。無理に動かすと悪化することがあるため、まずは安静にしつつ炎症を鎮めるケアが大切です。
② 拘縮期(1ヶ月~6ヶ月)
痛みが落ち着き始めますが、肩の可動域が大きく制限され「後ろに手が回らない」「髪を結べない」といった動作障害が目立ってきます。ストレッチや温めケアなどを段階的に取り入れる時期です。
③ 回復期(6ヶ月~1年)
徐々に可動域が戻り始めます。この時期のリハビリや整体などのアプローチによって、回復のスピードや完成度が左右されます。
「五十肩はいつまで続くの?」のリアル
個人差はありますが、半年〜1年程度で症状が落ち着く人が多いです。ただし、急性期に無理をしたり、何も対処せずに放置すると2年、3年と長引いてしまうこともあります。
「夜も眠れない」「寝返りを打つと痛くて起きる」「肩だけでなく首や肘も痛む」といった状態が続いている方は、単なる自然回復では追いつかない可能性もあります。
寝れないほどつらい時はどうする?
「五十肩 寝れない」という悩みを抱える方も多く見られます。夜間痛がひどい場合は、以下の対処法がおすすめです。
-
肩の下にバスタオルをたたんで敷く(角度をつけることで安定)
-
炎症が強い時は一時的に冷やす
-
肩周囲の血行を促すために軽めのマッサージやツボ刺激を取り入れる
とくに「肘まで痛い」「肩が熱を持っている」などの症状がある場合、自己判断せず専門家の評価を受けることが大切です。
整体的に見る“回復しやすい人”と“長引く人”の違い
回復が早い人に共通しているのは、以下のような特徴です。
-
痛みの時期を見極めて、適切なケアを段階的に行っている
-
肩だけでなく、肩甲骨・背骨・骨盤など全身のバランスにも目を向けている
-
姿勢や日常動作のクセを見直している
反対に、「自己流ケア」「無理なストレッチ」「安静すぎて動かさない」などは、癒着や拘縮が悪化する要因になるため注意が必要です。
五十肩の痛みがいつまで続くか不安な方へ
五十肩の痛みが「いつまで続くのか」は人によって異なりますが、適切な対応をすれば半年〜1年以内に改善していくケースがほとんどです。
ただし、何もせずに放置したり、自己流のリハビリで逆に悪化させたりすると、2年、3年と長引く例もあります。
「なかなか良くならない」「今どの時期なのかわからない」と不安な方は、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。
特に、肩以外の不調(首・肘・腰など)も同時に出ている場合は、全体のバランスが崩れているサインかもしれません。
そうした場合は、ストレッチや体操だけでの改善には限界があるため、整体で「全身の調整」や「日常動作の見直し」を取り入れることで、根本的な原因にアプローチできる可能性が高まります。
つらい痛みを我慢せず、状態に合わせた対策を始めていきましょう。
\五十肩の“今の状態”に合わせたケアで、無理なく改善を/
五十肩を“早く治したい人”がやりがちな間違い5選!整体師が見たNG例
-
すぐに治そうとして逆効果になるケースも
-
NG行動で「癒着」や「拘縮」が悪化することも
-
改善には“今の状態”に合ったステップが大事!
「五十肩を一瞬で治す方法」を求めるのは危険?
ネットやSNSでよく見かける「五十肩を一瞬で治す方法」や「魔法のマッサージ」のような情報に飛びつきたくなる気持ち、よくわかります。
ですが、整体師の立場からはっきり言えることがあります。
五十肩は“今の状態”に合った対応をしないと悪化することがあるということ。
特に「急性期」と呼ばれる痛みが強い時期に、間違った対処をしてしまうと、炎症が悪化したり、癒着が広がるなど、かえって回復を遅らせることになりかねません。
NG例①:痛いのに無理やりストレッチ
「動かさなきゃ固まる」と思って、激痛があるのに無理に腕を上げたり、背中に回したりしてしまう方が多く見られます。
しかし、これは炎症の悪化や関節包の癒着につながり、余計に可動域が狭くなってしまう可能性があります。
NG例②:YouTubeのセルフマッサージを毎日続ける
最近はYouTubeなどでセルフマッサージやストレッチ法が多数紹介されています。
しかし、「誰にでも合うもの」ではなく、急性期や拘縮期には逆効果になるものも多いです。
特に、「寝ながら腕を回す」「壁を使って無理に引っ張る」などの方法は、炎症がある場合にはおすすめできません。
NG例③:「温めれば治る」と長時間温熱を続ける
温めは血流促進に役立つ反面、急性期の炎症時に過度な温熱を与えると腫れや痛みを助長することもあります。
五十肩は「温めれば治る」わけではなく、時期に応じた冷温交代法や短時間温熱が適切です。
NG例④:サプリや塗り薬に頼りきる
「五十肩サプリ」「関節に効くクリーム」などを試す方も多いですが、それだけで根本的な原因にアプローチすることは難しいのが現実です。
あくまで補助的なものとして考え、体の動かし方やバランスの改善が不可欠です。
NG例⑤:痛みが少し落ち着いたからと放置する
「急性期を抜けて痛みが軽くなったから」と自己判断でケアをやめてしまうと、可動域の改善が不十分なまま癒着が残ってしまうことがあります。
特に“肘まで痛い” “寝れないほど痛かった”ケースでは、慎重な段階的アプローチが必要です。
五十肩の回復には“段階に合わせた対応”がカギ!
五十肩の改善には、【急性期→拘縮期→回復期】と段階ごとにアプローチを変えることが何よりも大切です。
整体では、
-
急性期には炎症を鎮める施術や、負担を減らす調整
-
拘縮期には無理のない可動域回復のサポート
-
回復期には姿勢や筋肉バランスの調整で再発予防
といったように、段階に応じた方法で回復をサポートしていきます。
「早く治したい」という気持ちこそ、正しい情報と専門的な判断が必要です。
無理せず一緒に改善を目指していきましょう。
\焦らず、正しい順序で回復へ!/
五十肩は片方だけ?反対側も痛くなる理由と再発リスク
-
「片方だけの五十肩」が両肩に広がるケースもある
-
日常のクセ・姿勢・生活習慣が再発リスクを高める
-
整体的には“体の左右差”がカギ!
「片方の肩だけ五十肩だったのに、今度は反対側が痛い…」という方へ
実は五十肩は、最初は片側だけでも、数ヶ月~数年後にもう一方の肩が痛くなるケースが多いです。
これは単なる偶然ではなく、体の使い方や姿勢のクセが大きく関係していると考えられます。
なぜ反対側にも起こる?日常生活に潜む落とし穴
人は利き手や生活スタイルにより、片側の肩ばかりに負担をかけやすい傾向があります。
たとえば…
-
重いバッグをいつも右肩にかける
-
片手だけでスマホを持ち続ける
-
寝るときはいつも同じ向きで横向きに
このようなクセがあると、左右の筋肉バランスが崩れ、最初に痛めた肩をかばって反対側に無理がかかるようになります。
片方が治っても油断は禁物!
五十肩が片側で収まったように見えても、「肩まわりの筋肉の使い方」や「姿勢のゆがみ」が残っていると、反対側の肩に痛みが出るリスクが高いのです。
特に、
-
デスクワークが長い
-
体をひねる作業が多い
-
運動習慣がない
という方は、知らず知らずのうちに体のバランスが崩れやすく、肩の関節に偏った負担がかかりやすい状態にあります。
肘・背中・骨盤との連動がカギ
整体的な視点では、「五十肩は肩だけの問題ではない」と捉えます。
背中・肘・首・骨盤のバランスが崩れていると、肩の動きが制限されて負担が集中し、反対側の肩にも影響が及ぶのです。
肩の動きは単独ではなく、肩甲骨・鎖骨・肘・背骨との連動で成り立っているため、「全体を整えること」が再発防止につながります。
日常でできる再発予防のポイント
-
バッグを左右交互に持つように意識する
-
スマホやPC作業の姿勢を見直す(目線・肘の角度・背もたれ活用)
-
ストレッチや肩甲骨体操を継続的に行う
-
寝返りがうちやすい寝具・寝姿勢を選ぶ
-
体の左右差に気づいたら早めにケアする
たとえば、片手だけでバッグを持つクセや、いつも同じ方向を向いて寝る習慣があると、無意識のうちに肩の使い方に偏りが生じ、反対側の肩に負担が蓄積していきます。
さらに、姿勢のゆがみや背骨・骨盤の傾きなどがあると、筋肉のアンバランスによって肩関節の可動に無理が生じ、同じ動作をしても片側にばかり負担が集中してしまうことも。
整体の現場では、こうした「身体の左右差」や「癖」を見極め、再発リスクの高い人を早めにケアすることで症状のぶり返しを予防しています。
セルフケアだけでは見抜きにくい部分こそ、プロの視点が役立ちます。
\肩の不調が再発する前に、カラダ全体のバランスチェックを!/
五十肩の本当の原因は肩以外?肘・背中・骨盤から整える整体的アプローチ
-
肩だけをケアしても改善しないことが多い
-
背中・肘・骨盤など“連動部分”が原因のことも
-
整体では全身のゆがみを整えて根本改善を目指す
五十肩=肩の病気ではない?
「肩が痛いんだから、肩が原因でしょ?」と思う方も多いのですが、実は肩以外の部分に根本原因があるケースがとても多いのが五十肩の特徴です。
肩関節は、腕の骨(上腕骨)と肩甲骨、鎖骨などで構成される“複合関節”で、単独ではなく他の部位との連動でスムーズに動く構造になっています。
よくある肩以外の原因部位
-
背中(胸椎・肩甲骨周辺)
→ 猫背姿勢が強いと肩甲骨が外に広がり、腕が後ろに回らない -
肘や前腕のねじれ
→ 手首や肘に日常的な負担があると、上腕の筋肉が固まり肩に影響 -
骨盤や腰椎のゆがみ
→ 骨盤が傾くと姿勢全体が崩れ、肩の位置が左右でズレる
こうした部位の不調が「肩だけに症状が出ている」ように見える原因です。
痛みの“場所”と“原因”が一致しないことが多いのが五十肩の特徴でもあります。
肩の可動域と背骨・肋骨の関係性
特に「後ろに手が回らない」動作に関係するのが、肩甲骨・胸椎・肋骨の柔軟性です。
デスクワークやスマホ操作などで猫背姿勢が続くと、胸が縮こまり、腕を後ろに引く動きが制限されます。
さらに、背骨が硬いと腕を上げる際に代償動作が増え、肩関節そのものに過剰な負担がかかって痛みや癒着を起こしやすくなります。
整体での対応:全体バランスを整えて根本ケア
私の整体院では、五十肩の方には肩だけでなく「骨盤~背骨~肘・手首」まで全身の連動を見ながら調整していきます。
たとえば…
-
肩甲骨の動きを引き出す胸椎アプローチ
-
上腕のねじれをほどく前腕の筋膜リリース
-
骨盤の傾きを整えて、左右の肩の高さをリセット
といった手法を通じて、肩が動くための“全体の土台”を整えることが五十肩改善の近道だと考えています。
「肩のストレッチだけで良くならない」と感じたら
-
湿布やサポーター、サプリを使っても変わらない
-
寝ながらのストレッチでも可動域が広がらない
-
手や肘、反対側の肩にまで違和感が出てきた
こういった方は、肩以外の場所に原因がある可能性が高いです。
表面的なケアでは届かない“奥の要因”を見直すタイミングかもしれません。
\あなたの肩、実は「肘」や「骨盤」が原因かも?/
まとめ|五十肩の痛みは“体のサイン”。焦らずじっくり向き合おう
-
五十肩は「肩だけの問題」ではない
-
焦って動かすほど悪化するリスクあり
-
体全体を整えることで改善のスピードも変わる
五十肩の本質は「体からのサイン」
五十肩の痛みや可動域制限は、単なる「年齢による衰え」ではありません。
日常生活のクセ・姿勢の乱れ・体の使い方の偏りが積み重なって現れた“体からのメッセージ”だと捉えるべきです。
無理をして肩だけを動かすよりも、まずは痛みのサインに耳を傾け、根本から体を見直すことが回復の第一歩になります。
この記事でお伝えした主なポイント
-
「五十肩で後ろに手が回らない」原因と対策
-
急性期や拘縮期の過ごし方
-
寝ながらできるストレッチやツボ刺激
-
肘や背中、骨盤まで含めた全身アプローチ
-
再発防止のための生活習慣と整体活用法
どれも“痛みを和らげながら、無理なく改善していくためのヒント”です。
あなたに合ったケアを選ぼう
五十肩の症状や回復スピードは人によって異なります。
サプリやツボ刺激、温めるケアも効果的ですが、「痛みが長引いている」「動きが一向に良くならない」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。
\五十肩をきっかけに、体をリセットしませんか?/